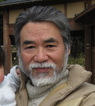分娩予定日は、かつて最終月経の最初の日から数えて280日(=40週)とされていました。
この決め方だと、実際に卵子が受精するまでの期間(月経が28日周期の場合、ふつう14日前後)も妊娠週数に加わってしまいます。
たとえば、月経の周期が42日で来るとすれば、排卵の時期は28日周期の人にくらべて2週間くらい遅くなります。ということは、妊娠期間を280日で決めてしまうと、赤ちゃんの発育は実際受精してからの期間が28日周期の人より2週間ぐらい小さいことになってしまいます。
ですから、単純に最終月経から計算するというのでは、超音波の発達した現在では「時代遅れ」の計算法とも言えます。
もしきちんと計算で出すのであれば、排卵した日から266日というのが正しい表現です。
では、実際排卵した日はどうやって知ることができるのでしょう?排卵する瞬間を実際見ることが出来ないので、ほかの方法で推測ことになります。比較的正しい方法は、基礎体温表の高温期の前日とする方法です。高温期の最初の日としても、差は1~2日程度です。
もし基礎体温表をつけていなければ、妊娠反応が陽性になった時点から補正する場合と、(経腟)超音波により実際に胎児をみて決める場合があります。この場合は使う妊娠反応が陽性になる単位数に気をつける必要があります。
市販されているものにも25単位のものと50単位のものがあります。
袋が経腟超音波で見えるようになるのは、ふつう4週頃です。
超音波で決める場合は、胎のう(=袋)の大きさで決めることはふつうありません。
胎のうはきれいな球形であることはまずありません。よって大きさは測り方によりまちまちで、週数を決めるには無理があります。
では何で決めるのでしょう。以前は8週頃の頭殿長(頭からお尻までの長さ)が最も正確といわれていましたが、これは経腹(おなかにあてる)音波の場合です。経腟超音波では、(おおまかに言うと)5週で心臓の動きが見えるようになります。
6週で胎児の形がみえてきます。
7週で約1センチの大きさになります。8週まで過ぎれば、まず安心していいでしょう。
妊娠週数は通常「満」で数えます。昔の「ヶ月」は「数え」です。(妊娠10ヶ月といえど36週では早産になってしまいます。)
この決め方だと、実際に卵子が受精するまでの期間(月経が28日周期の場合、ふつう14日前後)も妊娠週数に加わってしまいます。
たとえば、月経の周期が42日で来るとすれば、排卵の時期は28日周期の人にくらべて2週間くらい遅くなります。ということは、妊娠期間を280日で決めてしまうと、赤ちゃんの発育は実際受精してからの期間が28日周期の人より2週間ぐらい小さいことになってしまいます。
ですから、単純に最終月経から計算するというのでは、超音波の発達した現在では「時代遅れ」の計算法とも言えます。
もしきちんと計算で出すのであれば、排卵した日から266日というのが正しい表現です。
では、実際排卵した日はどうやって知ることができるのでしょう?排卵する瞬間を実際見ることが出来ないので、ほかの方法で推測ことになります。比較的正しい方法は、基礎体温表の高温期の前日とする方法です。高温期の最初の日としても、差は1~2日程度です。
もし基礎体温表をつけていなければ、妊娠反応が陽性になった時点から補正する場合と、(経腟)超音波により実際に胎児をみて決める場合があります。この場合は使う妊娠反応が陽性になる単位数に気をつける必要があります。
市販されているものにも25単位のものと50単位のものがあります。
袋が経腟超音波で見えるようになるのは、ふつう4週頃です。
超音波で決める場合は、胎のう(=袋)の大きさで決めることはふつうありません。
胎のうはきれいな球形であることはまずありません。よって大きさは測り方によりまちまちで、週数を決めるには無理があります。
では何で決めるのでしょう。以前は8週頃の頭殿長(頭からお尻までの長さ)が最も正確といわれていましたが、これは経腹(おなかにあてる)音波の場合です。経腟超音波では、(おおまかに言うと)5週で心臓の動きが見えるようになります。
6週で胎児の形がみえてきます。
7週で約1センチの大きさになります。8週まで過ぎれば、まず安心していいでしょう。
妊娠週数は通常「満」で数えます。昔の「ヶ月」は「数え」です。(妊娠10ヶ月といえど36週では早産になってしまいます。)