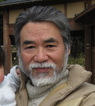今度は、こまった行政栄養士の指導について書きます。
離乳食教室の対象月齢を2~4か月、自治体によっては5~6か月など様々です。
厚生労働省が出した授乳離乳食ガイドでは「離乳の開始
離乳の開始とは、なめらかにすりつぶした状態の食物を初めて与えた時をいう。その時期は生後、5、6ヶ月が適当である。」としています。
5~6か月から始めるとしています。
これには、疑問を感じています。
6か月までに始めなければならないと言っているようである。
本当に離乳食は必要なのだろうか?
離乳準備食と離乳食を混同しているように思います。
個人的に離乳準備食はいらないと思っています。
2子、3子など子どもが多くなれば、離乳食なんか作るひまはない。
それでも子どもは育っている。
離乳食メーーカーやミルクメーカーの影が国にも影響を与えているように思う。
企業利益の優先、国民が犠牲者、無知は犯罪。その無知を助長するのが商業広告雑誌である育児雑誌。
マニュアル世代をだます、育児マニュアル。育児雑誌は、人工乳やベビーフードなどの広告だらけ。
出版社は読者をだまして購入させればいいのです。その戦略に載せられてはいけません。
これらの雑誌が廃刊になると、この国は良い方向に行くかも知れませんね。
正しい情報を身につけないと、10年後20年後の我が子に大きく影響しますよ。
子育てはファッションやゲームではない。
我が子に、問題行動をおこされたら苦しむのは「親」です。
先を見た子育てをしてください。
ある自治体の離乳食講座に参加されたお母さんの話です。
「もらったプリントには離乳開始が5~6ヶ月からとなっている。
「WHOやユニセフでは、6ヶ月までは完全母乳を推奨していますが、あえて5ヶ月から離乳を開始する理由は?」と聞きました。
栄養士さんの回答は「先日受けた研修(どこの主催かは分かりません)では、厚労省から出ている「授乳・離乳食ガイドライン」(記憶は曖昧なので、名称が違っているかもしれません)に沿った指導をするように言われました。そのガイドラインでは5ヶ月からとなっています」とのことでした。
実際に私達が配られたプリントも、そのガイドラインだそうです。
また、「早期離乳に伴うリスクやデメリットは色々言われるようになってきましたが、そういうお話はして頂けないのですか?」と聞いてみましたが、栄養士さんの回答は「立場上お答えできません」とのことでした。
ただ「どこも、このガイドラインに沿って同じような指導をしています」と言っていました。」
ガイドでは、たしかに「5~6か月から始めましょう」となっていますがそれ以降いつでもいいと思います。
この行政栄養士は、質問に答えられるほど知識がないのですね。
「立場上お答え出ません」ではなく「知りません」と答えればいいのです。答えられませんとは「公務員」の逃げ言葉です。
このような人に、母乳哺育や栄養のことをまかせておくのは、国益を考えると大変に危険です。
離乳食を早期に進めることは、アレルギーなどを誘発するリスクもあります。
行政栄養士は母親や子どもの心や身体を傷つけることを知って欲しい。
育児不安を増大させるようなことはやめて欲しい。
このような良識をもったお母さんを「問題のある」母親として捉えて欲しくない。
※次に母子手帳のことについて
「私の持っている母子手帳の話です。
3~4ヶ月のページには、「薄めた果汁やスープを飲ませていますか?(5ヶ月頃から離乳が始められます)」という記載があります。
この記載は全国共通なんでしょうか?
私も、たまごママネットを見ていなかったら、「3ヶ月から果汁やスープをあげていいのね」と思い、息子に飲ませていたと思います。
そして、記載の通り、5ヶ月で離乳を開始していたと思います。
我が家の息子は相変わらず母乳大好きっ子なのですが、最近は私達が食事を始めるとわざわざ私達の方に向き直って、食べづらくなるほどにジ~っと見つめています。
手を伸ばしてきたり、ヨダレをダラダラ流したり、下をペロペロ出したり引っ込めたりしてくるようになりました。
ひげ爺
まだまだゆっくりでいいよ。あせらないで、のんびりいきましょうね。
多くの親が成長を急ぐあまり子どもにとって酷なことをしています。
焦りや成長を急ぐのは禁物です。
「妊婦教室で知り合ったお友達と話していたら、彼女も「6ヶ月までは離乳を開始しない」を信念に、周囲の「果汁を飲ませたら?」「離乳は5ヶ月から」「早くしないと、知能が発達しない」などの騒音を無視して頑張っていたという話を聞きました。
話してみると、たまごママネットに書いてあるようなことを勉強して実践しているとのことでした。
同じような考えのママが近くにいるのって、心強いなぁって思えました。
彼女も、昨日の離乳食相談の内容には疑問を感じたり「まだまだ遅れてるのかなぁ」って言っていました。」
ひげ爺
離乳はやめて「卒乳」だよ。
2歳でも3歳でもいいよ。こそもが求めてくる間は授乳しようね。
僕のサポートしているお母さんは5歳と3歳の子に授乳しています。
時にはタンデムでしています。
卒乳は子どもが決めるものです。
親やまわりが決める物ではありません。
心の強い、いい子に育てるためには大切な栄養です。
でも与え方を間違えば、人工乳の方がいい場合もあります。
ゆったり抱いてお話をしながら楽しい雰囲気で授乳してあげてください。
楽しくが肝心です。人工乳も楽しくあげることが大切です。
母乳哺育で育った子どもでも、殺人を犯します。
愛のない授乳はよくありません。
携帯をしながら電話をしながらテレビやパソコンをしながら授乳は、もってのほかです。
サイレントベビー、物言わぬ心を病んだ人になります。
母子保健に関わる人々はもっともっと学びなさい。
母子にとって「本当に必要な支援」を間違っても指導はするな!!!!
母子に寄り添うことを続けていけば母子が教えてくれます。
何を学ぶべきかを。
国や学校、大学では教えてくれせん。
教授や教師が知らないのだから教えられるわけがない。
離乳食教室の対象月齢を2~4か月、自治体によっては5~6か月など様々です。
厚生労働省が出した授乳離乳食ガイドでは「離乳の開始
離乳の開始とは、なめらかにすりつぶした状態の食物を初めて与えた時をいう。その時期は生後、5、6ヶ月が適当である。」としています。
5~6か月から始めるとしています。
これには、疑問を感じています。
6か月までに始めなければならないと言っているようである。
本当に離乳食は必要なのだろうか?
離乳準備食と離乳食を混同しているように思います。
個人的に離乳準備食はいらないと思っています。
2子、3子など子どもが多くなれば、離乳食なんか作るひまはない。
それでも子どもは育っている。
離乳食メーーカーやミルクメーカーの影が国にも影響を与えているように思う。
企業利益の優先、国民が犠牲者、無知は犯罪。その無知を助長するのが商業広告雑誌である育児雑誌。
マニュアル世代をだます、育児マニュアル。育児雑誌は、人工乳やベビーフードなどの広告だらけ。
出版社は読者をだまして購入させればいいのです。その戦略に載せられてはいけません。
これらの雑誌が廃刊になると、この国は良い方向に行くかも知れませんね。
正しい情報を身につけないと、10年後20年後の我が子に大きく影響しますよ。
子育てはファッションやゲームではない。
我が子に、問題行動をおこされたら苦しむのは「親」です。
先を見た子育てをしてください。
ある自治体の離乳食講座に参加されたお母さんの話です。
「もらったプリントには離乳開始が5~6ヶ月からとなっている。
「WHOやユニセフでは、6ヶ月までは完全母乳を推奨していますが、あえて5ヶ月から離乳を開始する理由は?」と聞きました。
栄養士さんの回答は「先日受けた研修(どこの主催かは分かりません)では、厚労省から出ている「授乳・離乳食ガイドライン」(記憶は曖昧なので、名称が違っているかもしれません)に沿った指導をするように言われました。そのガイドラインでは5ヶ月からとなっています」とのことでした。
実際に私達が配られたプリントも、そのガイドラインだそうです。
また、「早期離乳に伴うリスクやデメリットは色々言われるようになってきましたが、そういうお話はして頂けないのですか?」と聞いてみましたが、栄養士さんの回答は「立場上お答えできません」とのことでした。
ただ「どこも、このガイドラインに沿って同じような指導をしています」と言っていました。」
ガイドでは、たしかに「5~6か月から始めましょう」となっていますがそれ以降いつでもいいと思います。
この行政栄養士は、質問に答えられるほど知識がないのですね。
「立場上お答え出ません」ではなく「知りません」と答えればいいのです。答えられませんとは「公務員」の逃げ言葉です。
このような人に、母乳哺育や栄養のことをまかせておくのは、国益を考えると大変に危険です。
離乳食を早期に進めることは、アレルギーなどを誘発するリスクもあります。
行政栄養士は母親や子どもの心や身体を傷つけることを知って欲しい。
育児不安を増大させるようなことはやめて欲しい。
このような良識をもったお母さんを「問題のある」母親として捉えて欲しくない。
※次に母子手帳のことについて
「私の持っている母子手帳の話です。
3~4ヶ月のページには、「薄めた果汁やスープを飲ませていますか?(5ヶ月頃から離乳が始められます)」という記載があります。
この記載は全国共通なんでしょうか?
私も、たまごママネットを見ていなかったら、「3ヶ月から果汁やスープをあげていいのね」と思い、息子に飲ませていたと思います。
そして、記載の通り、5ヶ月で離乳を開始していたと思います。
我が家の息子は相変わらず母乳大好きっ子なのですが、最近は私達が食事を始めるとわざわざ私達の方に向き直って、食べづらくなるほどにジ~っと見つめています。
手を伸ばしてきたり、ヨダレをダラダラ流したり、下をペロペロ出したり引っ込めたりしてくるようになりました。
ひげ爺
まだまだゆっくりでいいよ。あせらないで、のんびりいきましょうね。
多くの親が成長を急ぐあまり子どもにとって酷なことをしています。
焦りや成長を急ぐのは禁物です。
「妊婦教室で知り合ったお友達と話していたら、彼女も「6ヶ月までは離乳を開始しない」を信念に、周囲の「果汁を飲ませたら?」「離乳は5ヶ月から」「早くしないと、知能が発達しない」などの騒音を無視して頑張っていたという話を聞きました。
話してみると、たまごママネットに書いてあるようなことを勉強して実践しているとのことでした。
同じような考えのママが近くにいるのって、心強いなぁって思えました。
彼女も、昨日の離乳食相談の内容には疑問を感じたり「まだまだ遅れてるのかなぁ」って言っていました。」
ひげ爺
離乳はやめて「卒乳」だよ。
2歳でも3歳でもいいよ。こそもが求めてくる間は授乳しようね。
僕のサポートしているお母さんは5歳と3歳の子に授乳しています。
時にはタンデムでしています。
卒乳は子どもが決めるものです。
親やまわりが決める物ではありません。
心の強い、いい子に育てるためには大切な栄養です。
でも与え方を間違えば、人工乳の方がいい場合もあります。
ゆったり抱いてお話をしながら楽しい雰囲気で授乳してあげてください。
楽しくが肝心です。人工乳も楽しくあげることが大切です。
母乳哺育で育った子どもでも、殺人を犯します。
愛のない授乳はよくありません。
携帯をしながら電話をしながらテレビやパソコンをしながら授乳は、もってのほかです。
サイレントベビー、物言わぬ心を病んだ人になります。
母子保健に関わる人々はもっともっと学びなさい。
母子にとって「本当に必要な支援」を間違っても指導はするな!!!!
母子に寄り添うことを続けていけば母子が教えてくれます。
何を学ぶべきかを。
国や学校、大学では教えてくれせん。
教授や教師が知らないのだから教えられるわけがない。