退職者会ニュースの作成はようやく50%余りが出来た。今月号は思ったよりも時間がかかっている。11日(月)に第一稿を送ることになっているが、明日中に出来上がるであろうか。かなり心もとない。基本的な原稿は出来上がっているのだが、文書の打ち込み、写真の貼り付け、校正などどうしても2日位はかかりそうである。
原稿と写真を送って割り付けから校正まですべて頼んでしまえば簡単なのだが、それでは費用もかかるし、意外と自分なりの紙面づくりにこだわっている自分の生きがいに近いものがある。
本日はこのこの辺で作業は終了としたい。
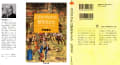
昼間、雨の中を横浜駅まで出かけて、友人から原稿と写真のデータを受け取り、プリンターのインクを購入。その後喫茶店で「詩文のなかに歴史をよむ」(阿部謹也、ちくま文庫)を読了。中高生向けの本ということで、語り口は確かにやさしいようだが、なかなか著者の思想にとって重要なポイント、本質的なことを述べている。
要約を載せるほどの力量はないが、気になった個所はとりあえず印だけはつけておいた。
明日は朝から団地の管理組合の諮問機関の会議。午後からの作業となる。
原稿と写真を送って割り付けから校正まですべて頼んでしまえば簡単なのだが、それでは費用もかかるし、意外と自分なりの紙面づくりにこだわっている自分の生きがいに近いものがある。
本日はこのこの辺で作業は終了としたい。
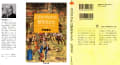
昼間、雨の中を横浜駅まで出かけて、友人から原稿と写真のデータを受け取り、プリンターのインクを購入。その後喫茶店で「詩文のなかに歴史をよむ」(阿部謹也、ちくま文庫)を読了。中高生向けの本ということで、語り口は確かにやさしいようだが、なかなか著者の思想にとって重要なポイント、本質的なことを述べている。
要約を載せるほどの力量はないが、気になった個所はとりあえず印だけはつけておいた。
明日は朝から団地の管理組合の諮問機関の会議。午後からの作業となる。













