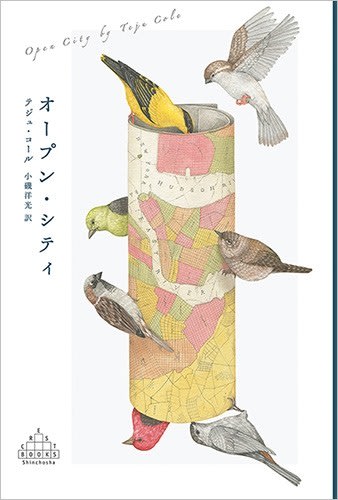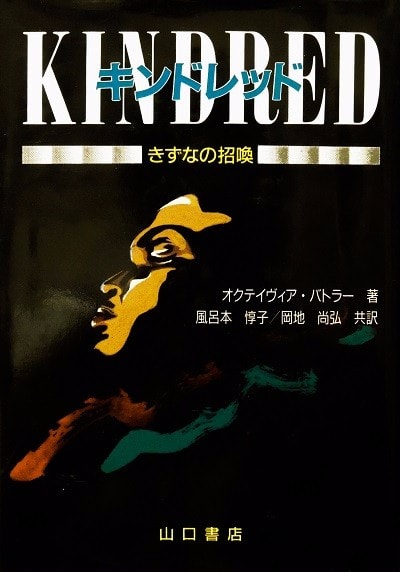ノーム・チョムスキー『アメリカンドリームの終わり あるいは、富と権力を集中させる10の原理』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、原著2017年)を読む。

ノーム・チョムスキーのこれまでの発言に接してきたならば、何もいまになってその内容が変わっていたり特別に新奇なものが入っているわけではないことがわかる。しかし、あらためて驚くことがふたつある。
ひとつは、トランプ現象が必然であったように感じられることである。すなわち、金成隆一『ルポ トランプ王国―もう一つのアメリカを行く』においても実状がまとめられているように、「中流」の崩壊(=アメリカンドリームの崩壊)、製造業の衰退、排外主義をもたらしてしまう社会構造、それらにより鬱積した不満といったものが、トランプ政権誕生の原動力となった。そしてチョムスキーが指摘するのは、それは結果としての社会構造・産業構造の変化などではなく、「富める者がより富を蓄積するため」の意図された変化であったことである。
もうひとつは、訳者も言うように、この極端なアメリカという世界が「明日の日本」であること。この20年ほどで進められた政治のエリート独裁(民意を敢えて取り入れない仕組み)、抵抗手段の骨抜き、教育の高コスト化、市民を敢えて不安定な位置に置くという手段、医療の高コスト化、政界と財界とを行き来する「回転ドア」(特定の人物が思い浮かぶ)、実に狭い範囲での選択肢を演出することによる「合意の捏造」、・・・。おそらく現在の問題意識をもって読むと、むしろ、「今日の日本」であることが見出されるだろう。
まるで陰謀論本のような装丁にされていることが残念である。日本の問題をとらえなおすために広く読まれるべき本。
●ノーム・チョムスキー
ノーム・チョムスキー『我々はどのような生き物なのか ソフィア・レクチャーズ』(2015年)
ノーム・チョムスキー講演「資本主義的民主制の下で人類は生き残れるか」(2014年)
ノーム・チョムスキー+アンドレ・ヴルチェク『チョムスキーが語る戦争のからくり』(2013年)
ノーム・チョムスキー+ラリー・ポーク『複雑化する世界、単純化する欲望 核戦争と破滅に向かう環境世界』(2013年)
ノーム・チョムスキー+ラレイ・ポーク『Nuclear War and Environmental Catastrophe』(2013年)
ノーム・チョムスキー『アメリカを占拠せよ!』(2012年)