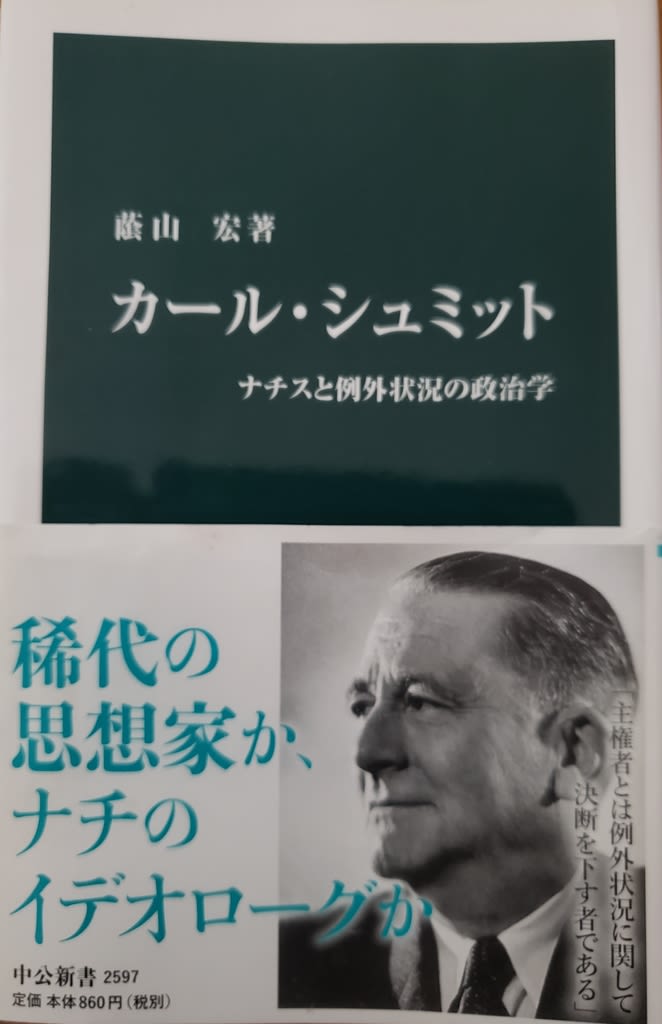
ウクライナ侵攻で地政学や独裁体制というものが改めて注目されたのを契機に、ロシア側の行動の背景となったネオ・ユーラシア主義やアレクサンドル・ドゥーギンをこのブログで紹介したわけだが、それらを理解する上でカール・シュミットという人物を深く知ることも有益であろう。
彼が唱えたものは様々あるが、例えば「友ー敵」理論はアメリカ・イギリスという大西洋国家(≒海洋国家)とドイツやロシアのようなユーラシア国家(≒大陸国家)との対立を軸に情勢を見る世界観につながるし、「例外状況」での決断を重視する姿勢は独裁の理論的正当化としてロシアなどを含む国家の体制(が求められる理由)を説明するのに資するものである(もちろん、これらが全てシュミットの独創ということではない。例えば後者なら、マックス・ウェーバーが「システムの中で判断し、それを維持しようとする官僚」に対し、「たとえシステムや市民の意思を無視したことで後に断罪されようとも、超法規的に決断を下すのが政治家」であるという趣旨の対立図式で説明したことが想起される)。
このように書くと、彼の理論が専ら外交や政治思想のみを扱っている印象をもたれるかもしれないが、実際にはもっと広い射程を扱っている・・・というのを理解する上で、表題にて紹介した蔭山宏の『カール・シュミット ナチスの例外状況の政治学』は参考になるだろう。
例えば第二章では、「近代的市民の批判」という見出しで『現代議会主義の精神史的地位』『政治的ロマン主義』を主に扱っているが、そこでは政治から距離を取ることを是とする態度とその背景、そしてそれに対するシュミットの批判が述べられている。ここでは、「ロマン主義」というワードとともに、統一的な自己にとらわれない=多様な、あるいは分裂的自己との戯れを称揚するような精神性が抉り出されているが、このような発想は後期近代の「シミュラークル」といった言葉とともに、むしろ今日の我々にとって馴染みのエートスと言えるのではないだろうか?
こう考えると、シュミットの分析・評価はワイマール共和国期の市民が持っていた傾向・それが当時の政治的混乱にもたらした影響・それへの苛立ちが彼を決断主義という方向に導いた、といった同時代的な事情のみならず、現代にもしばしば見られる政治からのデタッチメントとその思想的背景や正当化の理論を理解する一助にもつながるという意味で、非常に示唆に富んでいるのである(少し前『反逆の神話』という本に触れたが、そこでも現代のカウンターカルチャーにおける「政治と距離を取ることこそが最も体制を破壊する(反体制的)行為だとするメンタリティ」が取り上げられ、その非現実性が繰り返し批判されている[反体制とは違うが、前回取り上げた毒親や虐待について言うなら、ロマン主義的な発想はただ心の在り方だけを問題視し、親権に関する法整備やシェルターのような環境整備といったシステムについての議論・行動については等閑視するようなものだ]。そこでもロマン主義と、それに加えてエマーソンらの超自然主義が取りざたされているが、よくよく考えてみれば、国民の政治参加がクローズアップされる主権国家体制以前の世界でも、このような発想は存在する。たとえばポリスが崩壊し個人主義が前景化したヘレニズム時代生まれのストア派においても政治から距離を取ることを奨励する思考態度が観察されるのであり、それを踏まえればより普遍的に「人間の政治に対する態度の一類型」と言うべきなのかもしれない)。
また、ナチスとの関わりについてのシュミットの自己弁護も興味深い。例外状況と決断を理論化し、さらにはパーペン内閣などにおいては世界恐慌による諸々の混乱という「例外状況」を踏まえてワイマール憲法を逸脱し議会制民主主義から外れた政策を正当化しただけでなく、ナチス政権が成立したらそちらへも積極的に秋波を送っていたのに、第三帝国が崩壊したら「私もまた被害者であり、命がけの反政府運動に関与しなかったことを外野から論難される筋合いはない」などと主張するのはさすがに通るまい。
とはいえ、彼のそのような態度や自己弁護に、シュミットの理論の限界のみならず、独裁を希求することの危険性がそのまま表れている点には注目すべきであろう。なるほど、例外状況において強権的に決断する独裁的体制を是とするのはいい(特に政権が弱体で混乱が続くようなら、そう願いたくなる心性は理解できる)。しかしでは、その独裁体制が機能不全になったら、いったいどのようにしてその状況を改善・打破するのであろうか?そもそも機能不全に陥った状態からリカバリーするために(三権分立のように)権力は分散されチェックアンドバランスの仕組みが作られているわけだが、独裁状態では外側からコントロールするのはもちろん、異議申し立てすら命がけになりかねない(から結局状況を変えることが困難になる)、ということをシュミットは予測できなかったのだろうか?
著者の蔭山は、「批判こそ鋭いが、対案の提示はできない類の論者であった」とシュミットを批判的に評価しているが、まさしくそのような弱点の現実化がシュミットのナチス政権に対する態度と、また事後的な正当化理論であったと言えそうだ。そしてそのような問題の噴出に対し、己の理論の限界や認識の誤りと真摯に向き合うのではなく、「いやだってどうしようもないじゃん」という類の居直り的自己弁護をするしかなかったところに、シュミットのみならず、独裁というものを支持する人間や理論の欠陥部分が端的に表れているということができるだろう。
なお、こういった重大な欠点に基づいて、シュミットを取るに足らない学者と断罪するならば、それは大きな間違いである(そうであれば丸山真男らが危険視しつつ評価することにはならない)。
先ほどシュミットの理論の背景がワイマール共和国の政治的混乱だったことに触れたが、このような混乱と決断力のある独裁者の希求(行動力ある勢力の渇望)は様々な場面でみられる。それはフランスで言えば、1830年・1848年革命に伴う混乱と各種階層の利害対立、そしてそれを収拾する存在として期待されたルイ・ボナパルト(後のナポレオン3世)の大統領当選および皇帝就任が想起される(これをマルクスは『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』として取り上げ、「歴史は繰り返す。一度目は悲劇、二度目は喜劇として」と述べた)。
日本では、1925年より憲政の常道が始まったにもかかわらず、止まぬ派閥争いに加えて金融恐慌・世界恐慌といった社会・経済的危機への対応力のなさの露呈、ヴェルサイユ体制・ワシントン体制という新たな国際秩序への参画と反発といった中で期待が減衰していき、具体的な成果(?)を上げる軍部への期待が相対的に高まり、それが満州事変を支持する世論形成や、五・一五事件(首相暗殺を始めとする破壊工作)に対する助命嘆願へとつながっていった。これが後に貴族院出身の近衛文麿内閣のポピュリズム的政策などを経て、最終的には大政翼賛会へ・・・という道筋を経ていくわけである。
このように見ていけば、政治的カオスの中で強権的指導者による断固・決然たる姿勢での政策実行を期待するのは、ありふれた精神構造だということがわかるし、となれば、冷戦崩壊後にエリツィン政権の中でアノミーを経験した人々が、プーチンの強権体制に期待し続ける背景もまた、類似のメンタリティであると理解できるのではないかと思う(念のため言っておくと、戦前日本の政治システムは幕藩体制の再現を避けるため権力分散の仕組みを徹底しており、ゆえにどれだけ権力集中を目指しても結局ナチス的な体制にはならず、セクショナリズムとも呼ばれるそのキメラ的構造が、全体を見渡せず勢いに流される事態を生み出してしまった。つまり、一言で強権的構造とか独裁体制と言っても、中身は様々違っている点には注意を要する)。
そのような意味で、改めてシュミットの理論と行動は、独裁を理論的にどう見るかだけでなく、独裁を希求する精神構造やその問題点を浮き彫りにする示唆に富んだものだと述べつつ、この稿を終えたい。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます