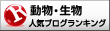今日の定置網漁で採集したトビウオ類幼魚とナンヨウサヨリ幼魚と最後のもう1種、ウスバハギ幼魚である。ウスバハギの幼魚は昨年の11月にも定置網で採集したが(ブログ2019 11.21)、あれから半年ちょっと経ち、さらに成長した個体を見つけ、今回も丁寧にタモ網で掬いとる。折れやすい背鰭棘も無事である。こちらも持ち帰り撮影。撮影する為に鰭を立てようとすると臀鰭、尾鰭に寄生虫が吸着しているではないか。背鰭棘が折れないか心配し、背鰭棘だけ集中して見ていたのか、それとも撮影個体が多くよく見ていなかったのか、寄生虫には展鰭するまで全く気付かなかった。寄生虫を取り除いてから撮影しようと思ったが、これも記録かなと思いそのまま吸着した状態で撮影する。魚ボラの標本用にもそのまま吸着した状態で冷凍保存する。