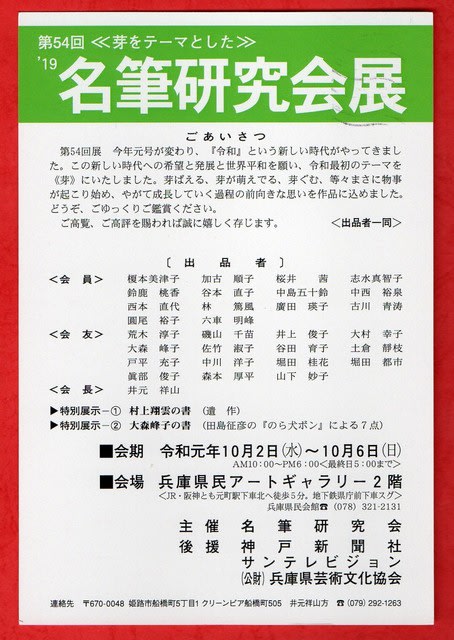和歌山の詩人、中尾彰秀氏よりお贈り頂きました。
詩集『万樹奏』(竹林館・2019年8月8日発行)です。
これが第25詩集だというから精力的ですねえ。
わたしが最も印象に残った「蝉の時間」です。 ←クリック。
←クリック。
「蝉」と「禅」とは字が似ているな、とはわたしも思っているものですが、このような作品に仕上げる手並みは素晴らしいですね。
わたしは何げなくこの詩を上げたのですが、あとで詩集の裏表紙を見ると、帯にこの詩の部分が印刷されていました。
作者も気に入った作品だったのかもしれません。
次にこれ。
「福石」です。表紙写真をモチーフに書かれた詩とのこと。
「あの石はどこへ行ってしまったの」と言いながら、自宅へ持って帰られたのではないでしょうか?
よくこんな石がありましたね。
 「黒板」です。
「黒板」です。
少し説明臭くもありますが、好きな詩の一つです。最終行、いいですねえ。「誰しもが永遠の自分自身の発見者なのだ」に、ハッとさせられました。
「あとがき」を紹介しておきましょう。
「あとがき」は最も読んでほしいものだったりする場合もあるような、ないような。少なくとも、作品と共に読んでもらいたいものでありましょう。
 ←クリック。
←クリック。
詩集と共に、氏が作曲演奏されたピアノ曲のCDもお贈り頂きました。今、それを聴きながらこのブログを書いています。
中尾さん、ありがとうございました。
詩集『万樹奏』(竹林館・2019年8月8日発行)です。

これが第25詩集だというから精力的ですねえ。
わたしが最も印象に残った「蝉の時間」です。
 ←クリック。
←クリック。「蝉」と「禅」とは字が似ているな、とはわたしも思っているものですが、このような作品に仕上げる手並みは素晴らしいですね。
わたしは何げなくこの詩を上げたのですが、あとで詩集の裏表紙を見ると、帯にこの詩の部分が印刷されていました。
作者も気に入った作品だったのかもしれません。
次にこれ。

「福石」です。表紙写真をモチーフに書かれた詩とのこと。
「あの石はどこへ行ってしまったの」と言いながら、自宅へ持って帰られたのではないでしょうか?
よくこんな石がありましたね。
 「黒板」です。
「黒板」です。少し説明臭くもありますが、好きな詩の一つです。最終行、いいですねえ。「誰しもが永遠の自分自身の発見者なのだ」に、ハッとさせられました。
「あとがき」を紹介しておきましょう。
「あとがき」は最も読んでほしいものだったりする場合もあるような、ないような。少なくとも、作品と共に読んでもらいたいものでありましょう。
 ←クリック。
←クリック。詩集と共に、氏が作曲演奏されたピアノ曲のCDもお贈り頂きました。今、それを聴きながらこのブログを書いています。
中尾さん、ありがとうございました。