宮崎さんの書評は本当に面白くて分り易い。何時も本の内容より宮崎さんの考えに引き込まれて島します。
今回も、渡邊惣樹さんの本を分り易く解説してくれています。いよいよ民主党の崩壊のようです。と言うか、誰が見てもあの民主党は完全に狂っているでしょう。日本の反日売国左翼・在日野党と比べても甲乙付け難いバカとしかおもえません。
世界の人々は行き過ぎたリベラリズムのおかしさに気が付き出したということじゃないでしょうか。これもやはりネットのお蔭と言えそうです。既存のマスメディアのフェイクに気が付いたということでしょう。
「宮崎正弘の国際情勢解題」より 令和元年(2019)12月24日(火曜日) 通巻6318号
書評
政治理想は濃霧の中に行方不明、米国民主党には陳腐な議論だけが残った
アメリカ崩壊の危機を救ったのはトランプではなかったのか?
渡邊惣樹『アメリカ民主党の崩壊 2001-2020』(PHP研究所)
日本には所謂「アメリカ通」が多い。
しかし『アメ通』達の分析はかれらの知っている範囲のアメリカであり、とくに日本の大手メディアの特派員、大学教授、シ ンクタン クの人々は、かれらのプリズムからアメリカを眺めた報告でしかない。自称「アメリカ通」が書いたものを含めてあまたの書籍が本屋 へ行くと並んでいるが、およそ読むに値するものは少ない。無内容というより意味のないことを書き連ねる「論客」ばかりが 目立つ昨 今である。
特派員も学者も、大半がリベラル偏向で、結論的にトランプは人種差別、ナチなどとするアメリカ民主党の政治プロパガンダ を真に受 けている。
日本人特派員はニューヨークタイムズとワシントンポストを読んでから記事を書く。アメリカ人の多くがすでに愛想をつかし たCNN が、「かくかく報じた」などと、さも正統な分析のように、極左ジャーナリズムの二番煎じをテレビ局が得意げに流している。だから 大方が、予測を外すばかりか、分析が根本的に間違っているのだ。
ならば在ワシントンの日本大使館はちゃんとした情報を取っているのか?
2016年に「ヒラリー当確」と満腔の自信を持って「予測」し、トランプ陣営と一切のコネクションがなかったのが、わが 外務省で あったことをお忘れなく。
本書は数々のスクープ的著作で知られる渡邊惣樹氏の新作だが、ワシントン分析に乗り出した。
しかも、民主党の2001年から2020年の荒削りながら大統領府に巣くったリベラル、左派の動向と政治ロビィスト、そ の政治イ ベントや綱領、政策などの民主党の基本骨格の変遷を提示した「歴史」本であり、しかも「アメリカ本」が夥しき市場にあって、独特 な持ち味がある。
本書は感情的に民主党を論じたものでもなければ、徒らに一方的に盲目的にトランプを称賛してもいない。あくまでも客観 的事実を 照らし合わせ、現実を照合すれば(そのためのグラフや数字データは貴重な資料だ)、アメリカ民主党の運命は、冷酷なひびきを伴う が「崩壊の危機」に直面しているという。
読み終えると、そういう印象が強烈に浮かんでくる。
本質的な分析箇所は次の箇所だ。
アメリカの民主党はリベラル政党ではなく、「フェミニスト、グローバリスト、社会主義者、弱者利権政治家らに乗っ取ら れた極左 政党」に成り下がった。
その若き人たちの極左に引っ張られて党幹部が右往左往している。
「弱者は、けっして他者に寛容ではない。弱者の側にたって途端に、彼らが正しいと考える思想を他者に強要する。妥協を 探るリア リストの視点を欠く原理主義者となる。アメリカ社会では、すでに弱者が権力者になると起こるおぞましい現象が起きている」。
したがって冒頭にはやくも大胆な予測である。
2020年大統領選挙はトランプ再選が確実だが、最大の関心事は「民主党がどんな負けかたをするのかにある」とし、 「場合に よってはアメリカ型二大政党制の崩壊もある」。
▲トランプが大転換をもたらした
ブッシュ・ジュニア、ビル・クリントン、ドナルド・トランプという三人の大統領は、じつは同じ1946年生まれであ り、共通す る戦後体験が基底になるものの。三人は出自もバックグランドも異なるために、それぞれが戦後の認識に巨大な乖離がある。
大統領になった順番は、ビル・クリントン(1993-2001)、ブッシュ・ジュニア(2001-2009)、そして ドナル ド・トランプ(2017-)。
三人とも戦後の1946年生まれなことは述べたが、生年月日の順番は逆になり、トランプが「年長」の1946年6月 14日、 ブッシュは7月6日、そしてクリントンが8月19日である。ちなみにどうでもよいことだが、評者(宮崎)も、1946年生まれで ある。
したがって彼らとは同世代ゆえに世界を見る目に共通の世界観が被さる。
なぜこんなことを書いたかと言えば、戦後四分の三世紀、世界は激変したからだ。
第一にアメリカ一極体制が終わったこと、軍事的政治的に、である。アメリカは「世界の警察官を降りた」というオバマの 発言がそ れを象徴する。アメリカ・アズ・ナンバーワンの時代は、気がつかない裡に終わっており、単独での軍事行動をとることは珍しくなっ た。
第二にドル基軸体制は、その性格を変質させていること。ブレトンウッズ体制の基軸だったドル決済は金本位制の下でこそ 信任が篤 かった。けれどもニクソン・ショック以後は英国ポンドに加えて、ユーロ、円という多国籍通貨がIMFのSDRに加わり、2016 年からは人民元も加わった。となるとドルが基軸通貨を継続している所以はペトロダラーに変質しているからである。
第三に国家のあり方が変わり、帝国とネイションステート(国民国家)という色分けがなされるようになったのが戦後政治 だ。アメ リカは多文化国家となってナショナルな要素を希釈化してしまった。
第四に進歩史観が崩れ去り、左翼全体主義が人類の理想とされた時代は、ソ連の崩壊で轟音たてて崩壊した。にもかかわら ず民主党 の思想的立脚点は進歩史観である。
第五に保護主義からブロック経済へと進んできた貿易体制は、世界の国境を取り除くというグローバリズムが全盛を極めた ことに よって拡大してきた。EUの結束、WTO。
ところが、EU破綻の兆候が英国離脱(BREXIT)、世界が期待していたWTO(世界貿易機構)も中国の傍若無人な貿 易マナー 破りによって機能不全に陥り、急激に衰退し、保護貿易主義的な経済ナショナリズムが台頭した。それがこの四分の三世紀の経済的歩 みである。この問題の詳細は、四月頃を予定している渡邊氏と評者との共著で、くわしく語るつもりなので、このコラムでは 以上の概 要に留める。
さて本書は民主党の現代史、というより直近史であるからにはクリントン末期からブッシュ、オバマ政権と移り変わり、過 去を全否 定する形で登場するトランプによって、従来の米国の路線が転覆した。その経緯を渡邊氏は綴る。
結局、ブッシュ・ジュニア政権も、共和党の看板を掲げながらも、じつは政策は民主党と変わりがなかった。つまりクリン トン、 ブッシュ・ジュニア、オバマの三代政権を支配したのはネオコンだという史観に渡邊氏は立脚している。
▲ネオコン思想が三代政権の基底にあった
渡邊惣樹氏の「ネオコン観」と言えば、広範な文脈で捉えられており、評者が、嘗て『ネオコンの標的』(二見書房)で、 定義した 狭義のネオコン解釈ではなく、どちらかといえば、馬淵睦夫大使や藤井厳喜氏のいう「ディープ・ステーツ」に近い。
ディープステーツを敵視するのがトランプ大統領だ。
狭義のネオコンは「元トロッキスト、転向組、ユダヤ人が多い」という特色があって、アービン・クリスタル親子やロバー ト・ケーガ ン(その夫人がウクライナ民主化で暗躍したヌーランド)、リチャード・パールらを指し、保守本流にいたチェイニーや、ジョン・ボ ルトンは含めなかった。渡邊氏は、後者もネオコンに含める。つまり本書に於けるネオコンはディープ・ステーツと同義だ。
大統領選挙において不可欠の三要素はEMMといわれ、「Eは選挙民の熱狂、ひとつ目のMは資金、次のMは選挙民への適 確なメッ セージである」。
トランプが立候補表明するまでの米国の言論空間といえば、「報道の自由」「表現の自由」は希薄だった。
なぜならメディアの主流が左翼であり、保守の主張を黙殺するか、激烈に批判した。自分以外の主張を受け付けない、排撃す るのが民 主党リベラル派と、それを擁護するリベラルメディアの特質であり、かれらがトランプを『反知性』とレッテル張りしたが、じつは民 主党こそが『反知性』である、と渡邊氏は批判する。
民主党がおかしくなったのは、基本的にJFK時代から唱えられ、ニクソンが法制化し、レーガン時代から実施が顕著と なった「ア ファーマティブ・アクション」(少数派と女性への配慮。たとえば大手企業は雇用に黒人、ヒスパニックの雇用割合を義務づけられ た)だ。
つぎに「ポリティカル・コレクトネス」(通称「ポリコレ」)という制約で、差別用語などが禁句となった。「言葉狩り」と 言い換え ても良いだろう。
次第次第に言論空間は極めつきに狭くなり、表現者は臆病になり、左翼からの攻撃に敏感となったために心理も萎縮し、むし ろ自由な 表現が制約され、ついには人前でトランプ支持を言うことさえ憚られた(いまはトランプ支持を自由気ままに表現できる状況にもどり つつあるが。。。)
メディアの横暴は容赦なく保守に襲いかかり、痛烈な罵声が浴びせられた(日本のメディアが酷評する対象も似ている)。
こうした窮屈な言論状況をぶち破る必要があった。ぶち壊したのはツィッターというSNS時代の新兵器。ユーチューブ、主 張を唱え るHPや、ネットでのテレビ局の開局だった。だからウォールストリートジャーナルのような保守のメディアまでトランプを批判した が、少数意見はミニコミとミニ・テレビ局とツィッターが代弁し、それが瞬く間に言論空間を席巻した。
CNNの視聴者は75万人しかいなくなった。逆にフォックスニュースは250万人。これを日本に当てはめると桜チャン ネル、林 原チャンネル、言論テレビ等のミニ放送局が、NHKを視聴率で凌いだということである。
クリントン時代から推進されてインターネット革命は、オバマ政権でSNSによる言論空間に革命が起きていた。民主党は、 この間、 穏健派、保守派、中間派がおおきく後退し、左派に乗っ取られていた。しかも左派を操ったのが、共和党に陣取っていたネオコンであ り、その一派がオバマ政権に雪崩れ込んだのだ。
▲民主党は惨敗し、分裂する可能性が高まった
渡邊氏は次のように書く。
「民主党は、ターゲットとした弱者層に『失われた』権利を回復しなくてはならないと訴えた。弱者であることを意識させ ることは 難しくない。殆どのケースで、外見だけで弱者に所属していると自認できた。所属するグループ(黒人、移民、少数民族、女性など) を見渡せば、容易にわかった。この思想とも言えない権力を掴むための主張(戦術)が、アイデンティティ・リベラリズム (IL)で ある」。
弱者が強者に変貌すると、他人に強要するのが極左の特質である。
民主党は自分で自分の行動、主張に制約をかけて、とどのつまりは身動きが取れず、過激な左翼や社会主義者が党の中軸を 揺らした ばかりか、主導権を握るまでになった。
YES WE CAN と呪文のように唱えてヒラリーを退けてオバマが当選したとき、米国内の黒人やヒスパニックの歓 呼の声が 鳴り響いた。
ところがオバマ政権下の黒人の失業率(9・5%)はブッシュ時代のそれ(7・7%)より酷くなり、こんな筈ではなかった という不 満が拡がっていた。
民主党の支持層が離れだした。
現時点で言えば、例えば黒人のトランプ支持が30%近くとなり、ヒスパニックは50%に近い。絶対の、鉄壁の民主党支持 が民主党 の候補者や訴えに愛想を尽かし、2020年にはトランプに票を投じることになると予想される。
結局、「オバマは、外国企業のロビイストだった人物に推されて大統領に上り詰めた政治家だった。当選すると、ウィリア ム(悪名 高きロビィスト)を大統領首席補佐官に抜擢した。オバマ政権では、外国企業に奉仕することを生業にしてきたロビイストが幅をきか せていた。だからこそ、ヒラリーの利益誘導的街区緒にも鈍感だった」
「(オバマの)政治の本質は(弱者ではなく)強者に寄り添ったものだった。メディアは相変わらず『弱者代表』のオバマ には甘い 報道を続けていたが、実態は伴っていなかった」(134p)。
ヒラリーが自宅にサーバを移し、機密に属する通信を自分のパソコンから発進し、アラブの春を操り、リビアで大失敗をや らかして 失脚したが、メディアは頬被りを続けた。国務省を外交と利権(政治献金、寄付)とリンクさせて「ヒラリー商会」に化かし、政治資 金の受け皿に慈善事業とかの財団を設立し、政策を売り歩いて世界をロビィ工作のために行脚した。それがクリントン・ヒラ リー外交 だったのだ。
こうみてくると、日本のメディアが伝えているトランプは、真実とは異なる、異形に歪められた印象をもたらし、そこにく わえて左 派ジャーナリズムの誤謬にみちた報道によってアメリカの読み方を間違えているのである。
著者は2020年の大統領選挙で、トランプの圧勝を予想している。
それにしても、良くここまで劣化したものです。つまりは、奇跡のトランプさん当選も必然だったのかもしれません。
もし、ヒラリーを選んでいたら今頃はChinaの天下になっていたかもしれません。アメリカは、危機一髪でトランプさんを選んだのです。
願わくば、そのトランプさんが日和ることなくChinaを叩き潰してくれますように。今のところは、間違い無いとは思いますが、こればっかりは何が起きるかわからないでしょう。










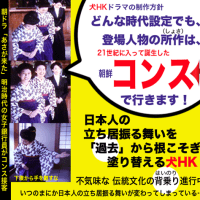
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます