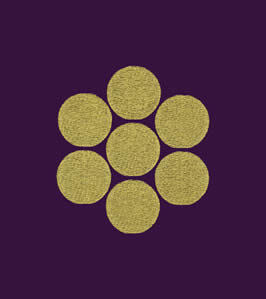◇リンカーン(2012年 アメリカ 150分)
原題 Lincoln
staff 原作/ドリス・カーンズ・グッドウィン『リンカン』
監督/スティーヴン・スピルバーグ 脚本/トニー・クシュナー
製作/スティーヴン・スピルバーグ キャスリーン・ケネディ
撮影/ヤヌス・カミンスキー 美術/リック・カーター
音楽/ジョン・ウィリアムズ 衣裳デザイン/ジョアンナ・ジョンストン
cast ダニエル・デイ=ルイス サリー・フィールド トミー・リー・ジョーンズ
◇1865年12月6日、修正第13条、憲法に追加
南北戦争の全貌であるとか、
奴隷解放宣言であるとか、
ともかく派手な場面を期待すると、とんだ肩透かしを食らうことになる。
ていうか、実際にぼくがそうだった。
なんの情報も仕入れずに観に行くと、たまにこういうことがある。
「え、超大作なのに、なんで、こんなに地味な映画なの?」
というのが正直な感想で、観ている間中、
「南北戦争の最後の四か月っていうけど、世界史やってないし」
とか、
「まさか、下院の議員をひとりひとり自陣営に鞍替えさせてるだけの話?」
とか、
「そもそも奇蹟の28日間とかって知らないし、そんなに有名な挿話なわけ?」
とかいった疑問が心の中で渦巻いてた。
で、映画を観たあとで、スピルバーグたちのインタビューを観た。
すると、そういう批判が出るのを承知の上で、
スピルバーグは用意周到なインタビューを用意してた。
だけど、
「観客の反応がわかってるんだったら、なんでまた…」
とはおもったものの、ちょっとしてから、おもいなおした。
「なるほど」
スピルバーグが描きたかったのは、家族の再生の物語だったんだ~って。
つまり、こういうことだ。
南北戦争という75万人もの戦死者を出した内乱に直面することで、
それまで夫唱婦随の仲だったはずのリンカーン夫妻は、
ことに妻の精神的な脆さが仇になり、いまにも最後の絆が切れそうになっていて、
息子は息子で、自分だけが守られているという特別扱いに、
尊敬していた父親への失望と近親憎悪が生まれ、
父子の絆もまた最悪の危機に陥っている。
けれど、大統領である自分は、ときに面白くもない冗談を口にしながら、
なんとしても奴隷解放を明文化させるべく憲法修正をしなければならず、
また、それが成るや、すぐさま悲惨な戦争を終わりに導かねばならない。
この順序が逆であってはならないというのが持論で、
そのために、リンカーンは懐柔策を採用し、
議員の一本釣りという、したくもない根回しをしている。
そうしたリンカーンとその家族、そして知人にのみ焦点を絞って演出した、と。
それはそれでかまわないし、観る側にしても、
「ああ、リンカーンってこういう人だったんだ~」
みたいな感想はいえるし、
なにより、一代記を箇条書きのようにして描かれても退屈なだけだし、
そんなものは資料で読めばいい。
役者が演ずる以上、人生のあるひとコマを切り取った方がいい。
人生が凝縮されたようなある時期を描くことで、
その前後の状況は見えてくるし、なにより人間味がよくわかる。
あとは、人生のどの瞬間を切り取るかって話になってくるんだけど、
黒人差別と黒人との友情について語りたいとおもうなら、
当初の草案だったフレデリック・ダグラスとの友情話にするべきだったろう。
けど、スピルバーグは、家族の話に終始した。
だって、
実際のところ、憲法が修正されようと、戦争が北軍の勝利に終わろうと、
奴隷すべてが一夜にして解放され、自由と仕事を手に入れられるわけでもないし、
フレデリック・ダグラスはそうした状況をまのあたりにして悶えたみたいだし、
そういうところからすると、
家族の再生の話だけを映像化した方が、ドラマとしての完成度は高い。
リンカーンの人生に関するいろいろな場面を描いたり、
南北戦争を映像によって再現しようとしたら、
それはたぶん絵本のようになって、うすっぺらなドラマだけが残ったろう。
なにもかも承知の上で、スピルバーグは戦争末期の28日間を選んだ。
それで、いいのだ。