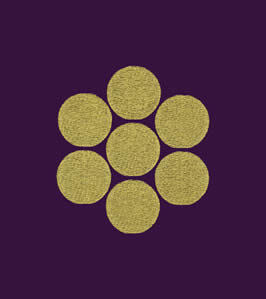◎見知らぬ乗客(1951年 アメリカ 101分)
原題 Strangers on a Train
staff 原作/パトリシア・ハイスミス
監督/アルフレッド・ヒッチコック 脚本/ウィットフィールド・クック
脚色/レイモンド・チャンドラー ツェンツィ・オルモンド
撮影/ロバート・バークス 美術/テッド・ハワース
音楽監督/レイ・ハインドーフ 音楽/ディミトリ・ティオムキン
cast ファーリー・グレンジャー ルース・ローマン ロバート・ウォーカー ローラ・エリオット
◎結末は2種類ある
というのも、DVDを観ればわかるんだけど、
この作品にはアメリカ版とイギリス版があって、
話の流れもクライマックスもほぼ同じなんだけど、
最後のオチをつけるかどうかって感じで、
英米の国民性を考慮したのかどうかはわからないけど、
ともかく、
見知らぬ乗客にふたたび声をかけられるかどうかっていうだけの違いだ。
観る人によって好みのわかれるところだろうけど、
そもそも、ヒッチコックはどうしたかったんだろう?
ただ、このあらすじは上手に構成されている。
主人公のテニス選手が交換殺人を持ちかけられるあたりは、
(なんだ、単純な話だな)
とおもってしまいがちなんだけど、
別れたいとおもっていた妻が殺される段になって、
どんどんと恐怖が増してくる。
交換殺人の片方は済んだんだから、おまえも早くやれと、
まったくするつもりもない犯罪に引き込まれそうになるんだから。
そこで交換殺人を持ちかけた相手に殺意が芽生えるのは当然なんだけど、
これはけっこう普遍的な人間関係だ。
仲良くなり、一緒に仕事をしかけ、ふとしたきっかけで仲違し、殺意を持つようになる。
通常、これは男と女の関係でよくある話だけど、この映画は男と男の話だ。
主人公ふたりに、ゲイの気があるんじゃないかとはよくいわれる話だけど、
なるほど、そういうことも考えられるかもね。
ネクタイやライターの扱いを観てると「お、そうかな」とおもえてくる。
してみると、ヒロインはどちらなんだろう?
それはともかく、クライマックスのメリーゴーランドは凄い迫力だ。
スクリーンプロセスも使われてるけど、
遊園地のじーさんがメリーゴーランドをとめるために、
回転する真下を這っていくところは、まじで固唾を飲む。
話の中身にではなく、
「あ~、これ、まじでやってんじゃん。ちょっとでも腰や背中に触れたらまずいで」
という、ヒッチコック組への心配なんだけど、それくらい、まじだった。
昔はCGが使えない分、役者は体を張ってるから、迫力は段違いだ。
あと、
メガネにライターが映るのはちょっと噴き出すけど、
殺人の光景が映り込むのは、この時代の先端だったかもしれないね。
冒頭の鉄道と並んで見事なカットでした。