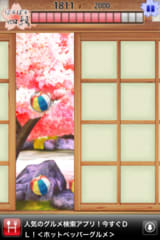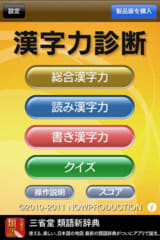「東日本大震災を機に、関東大震災後の帝都復興に稀代のリーダーシップを発揮した後藤新平が再び注目され始めた。なぜ後藤のような卓越した政治家が出現し、多彩な人材を総動員して迅速に復旧・復興に対処できたのか…。」(表紙カバー裏より抜粋)
東日本大震災への復旧・復興に、歴史から学ぶことが大切だ。関東大震災と東日本大震災を、そのまま比較することはできないが、非常時の対応は通常時には想像もつかないもので参考にすべき点は多々あるはずだ。
政治家、行政、被災地の住民が、過去から学び取り、教訓を生かして自分たちの街の未来を作ることが大事だと思う。
「後藤は内務大臣、帝都復興院総裁としてわずか四か月で復興の基本ビジョン、具体的な復興計画の策定、官僚・技術者の人材結集、復興のための特別法律の制定、復興予算の帝国議会可決、復興事業の実施方法(区画整理)など、あらゆる重要な事項について、レールを敷くことを成し遂げた…。」
誰もが知りたい問いかけ(表紙カバー)に対し、情熱の都市計画学者 越澤 明(こしざわ あきら)氏が、膨大な文献調査とヒアリングを通して、緻密な調査に基づき、後藤新平の実像に迫った。
内務大臣だった後藤による帝都復興計画の原案は、議会によって2度にわたり縮小・予算削減されたため、「大風呂敷」だった批判されるが、越澤は幻であった帝都復興計画の原案を探し出し、削減される前の原案は帝都復興には不可欠だったと高く評価している。
「マッカーサー道路は本当は後藤新平道路だった」 例えばマッカーサー道路と呼ばれる環状2号線。1946年に戦災復興計画として都市計画決定され、現在ようやく工事中の虎の門から汐留を結ぶ幹線道路。1923年10月の後藤の帝都復興計画原案には描かれており、その後削減されたことを明らかにしている。
1923年9月の関東大震災からわずか1か月後に帝都復興計画を作ることができたのは、大風呂敷と誤解されるような大雑把な計画だったからではなく、1920年12月から23年4月まで後藤が東京市長として在任中、緻密な調査に基づき立案した東京市政要綱が帝都復興計画に活かされたからだ、と明快に説明している。
「昭和天皇の無念」 1983年に昭和天皇は「後藤新平の復興計画がもし実行されていたら、東京の戦災は軽かったのではないか、後藤新平の計画が実行されないことを非常に残念に思っています。」と発言された。
水沢出身の医師としてのスタート。「板垣死すとも自由は死せず」で有名な板垣退助が岐阜で刺された際、治療したのが後藤だったという意外なエピソード。台湾で蔓延していたアヘン問題解決のために提案した画期的な意見書。台湾における産業振興とインフラ整備、満州における鉄道と都市整備、都市計画法の制定と普及のための全国行脚…などなど。
図や写真が多く、エピソードも豊富で読みやすい。一読をお勧めします。
<ちくま新書933 2011年11月10日発行。900円>