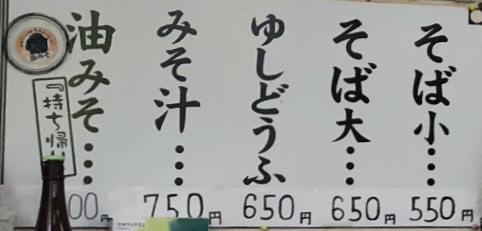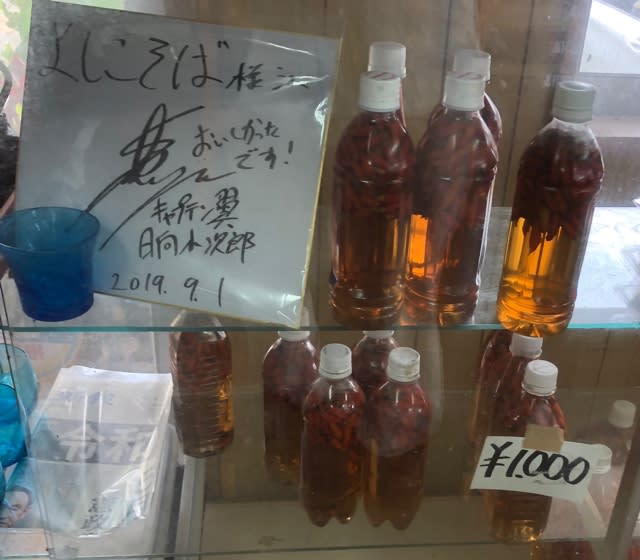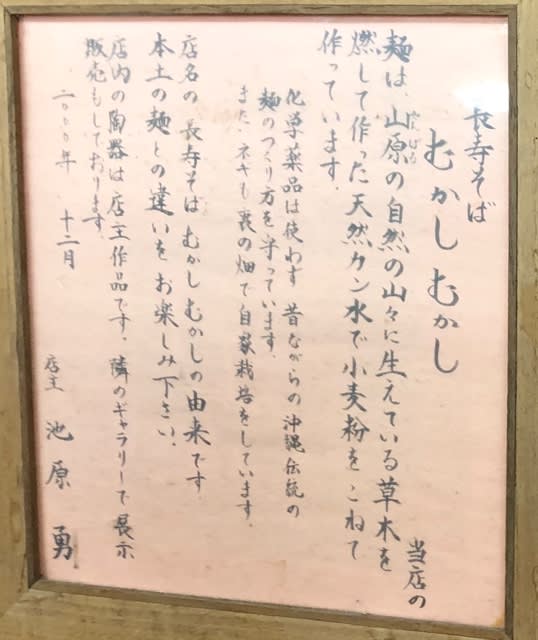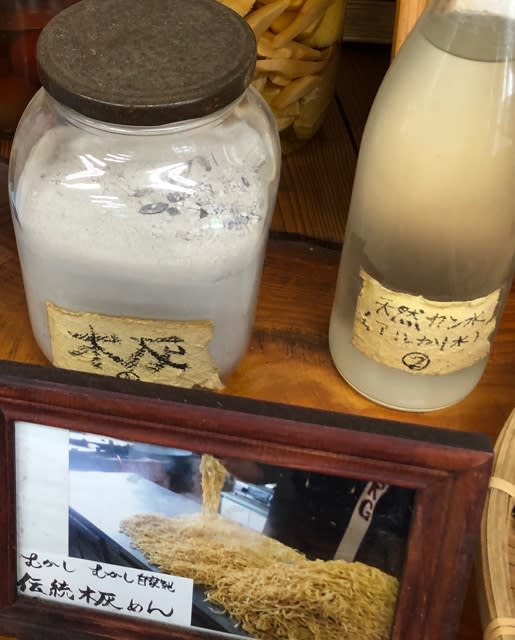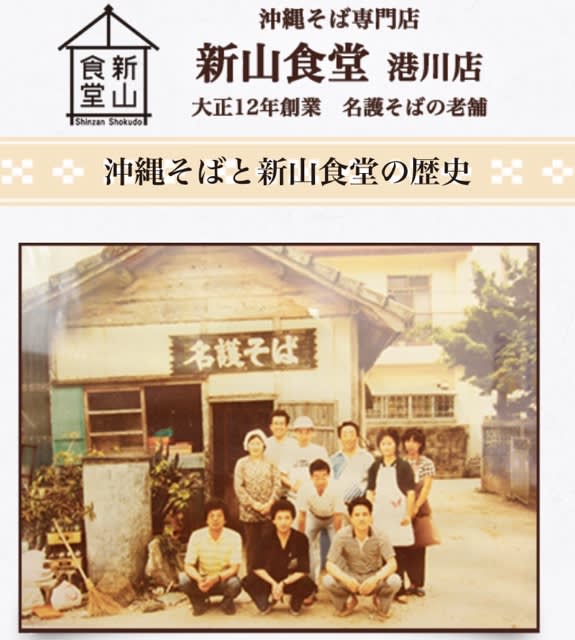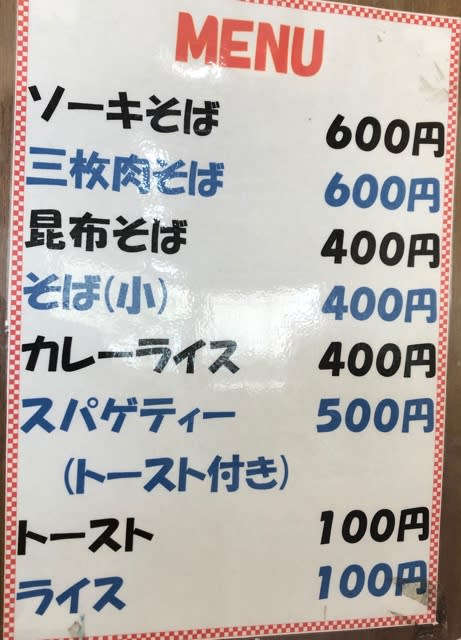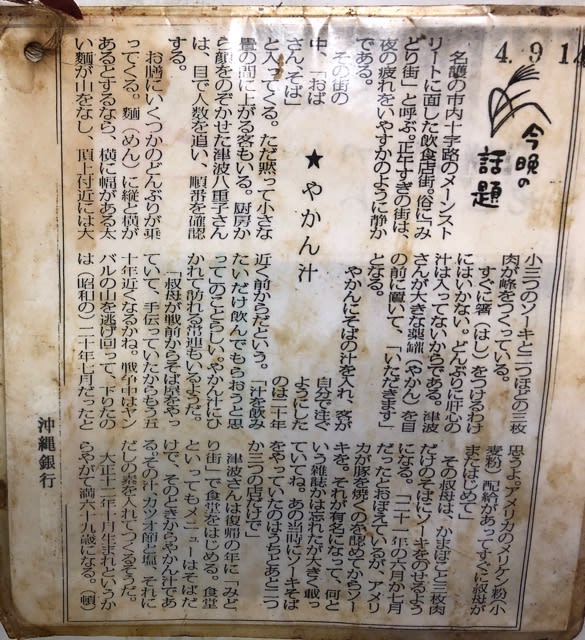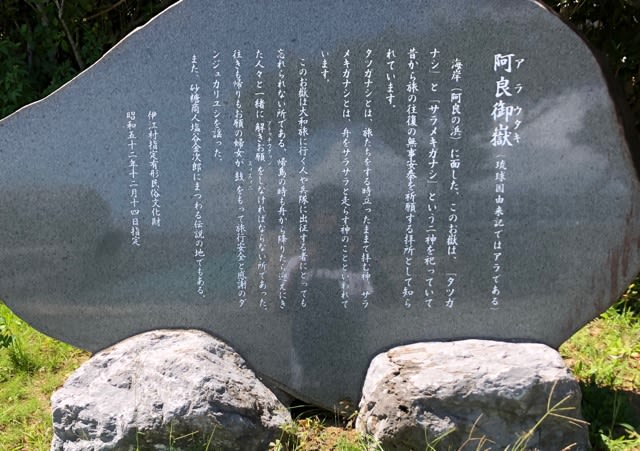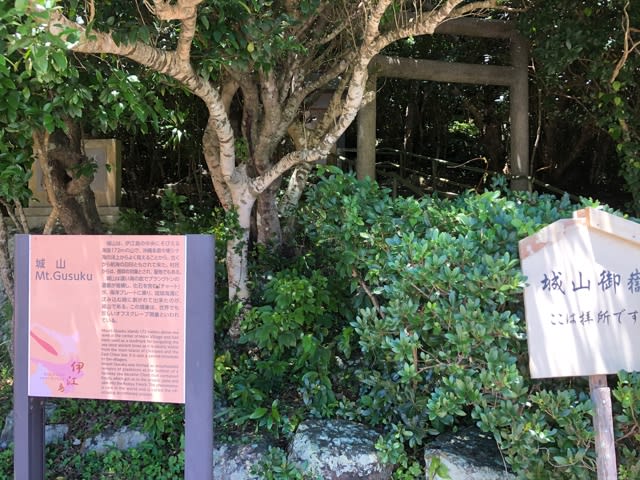名護から伊豆味街道を走行し始めてすぐの、山の中に「むかしむかし」があります。

天然の木灰(もっかい)そばとあります。
これは、期待できますね!

山羊(やぎ)そばに、山羊カルパッチョ。持ち帰り用の山羊汁980円がある。
山羊料理店が、山羊汁(山羊肉を煮込み、脂を取りながら味を整えた肉とスープ)の肉を、そばに乗せて「山羊そば」を出すのはわかる。
だけど、山羊汁は手間と時間がかかるので、沖縄そば屋さんが山羊そばを出すのは少ない。
三枚肉そば大650円を注文しました。
店内は、ワイルドな手づくり感溢れています。木材はスギではなくモクマオウ。
ワイルドだけど、スギちゃんじゃない。

2000年、店主の池原さんが山を切り開いて店を作る際、切り倒したモクマオウを、テーブルやイスに再利用したそうです。
加えて、店主制作の焼物が有ります。お碗も手づくりで販売もしてます。

ということは、もちろんそばも同様ですね。
お店のコンセプトが書いてありました。
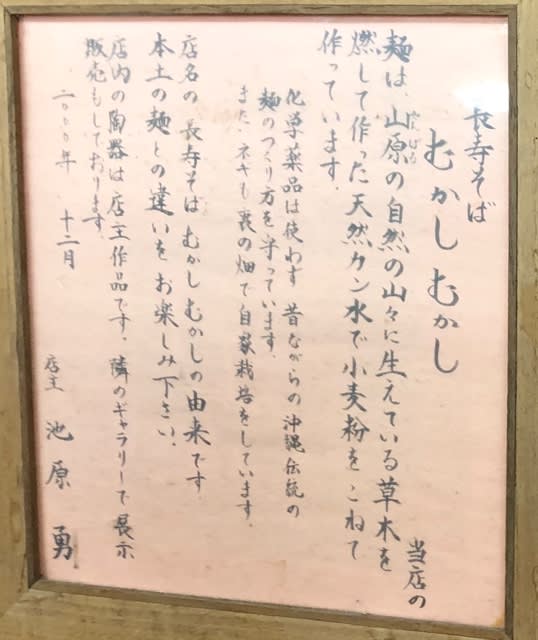
昔の沖縄県民のそばの作り方を、再現した店の名が「むかしむかし」。
木材からプロパンガスへと昭和30年代のエネルギー革命で、木材供給や木灰がなくなった。
「木灰で小麦粉を固める」沖縄そばさんの多くが、閉店していった。
店主は、建物を再建し、お茶碗や麺も手づくりで、むかしながらの自給自足を目指し、お客様に伝えようとしているのでしょうか。

木灰と天然カンスイです。
初めて見ました。
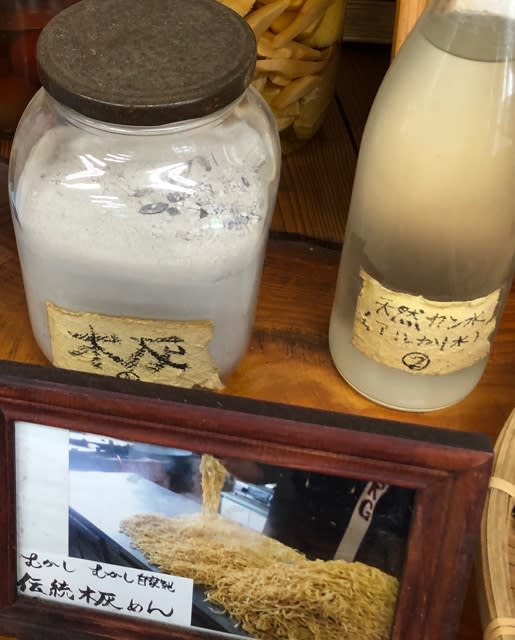
感心しているうちに、そばが出てきました。

スープ
沖縄そばの歴史で、醤油から塩に変わる過程があったと聞きますが、少し醤油味があるかな。
近くの「よしこそば」とスープが似ているから、むかしはこういう味が主流だったのかと思う。
肉
三枚肉がしっかり食べれます。美味しいです。
麺
腰があります。このコシの強さは「首里そば」を連想します。沖縄そばは、麺をよく噛んで味わう、スープとの組み合わせ。
そこに肉がある。いいね。
サービスで美味しいコーヒーをいただきました。
スプーンが、ワイルドです。

ホールスタッフは、
娘さん。
「山羊があるんですね」と軽く質問する。
「沖縄では食べるための家畜なんですよ。洗礼を受けるのが小学校一年生になった時。メエちゃんが突然いなくなり、後で意味がわかる。」と、娘さん。
沖縄の家では、子供が小学校に入学すると、自宅でお祝い会を開催し、お祝いに来る人々にご馳走でもてなす慣習がある。
お祝い会には、山羊汁や山羊刺身が欠かせない。

太い幹を削って作った大きなイス。
新聞ラックも、丸太をくりぬいたかな。
一刀彫りというのか、クギを使わず豪華。
これは芭蕉布かな。肌触りが涼しいです。
芭蕉布が沖縄で普及した理由を科学的に解明。糸芭蕉を「木灰」で煮ることで、通気性がよく熱や汗を外に逃す繊維を作り出していると、OIST
沖縄科学技術大学院大学の研究発表がありました。
芭蕉布の素晴らしさを、製造方法を科学的に説明した面白い内容でした。
沖縄の木材が生み出した食べ物、焼物、衣服の文化が理解出来るお店でありました。