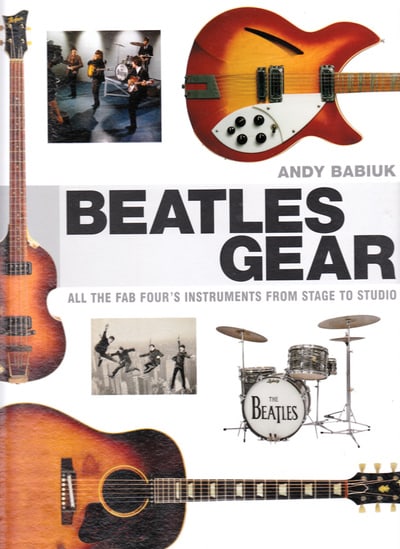富岡製糸場には、世界遺産に指定されて以来、行きたいと思っていた。
もちろんその歴史的価値に興味があったのだが、横浜と縁の深い製糸場という意味での興味もあった。
GW明けでどうかと思ったが、適当な人出で、何より、天気が最高。
開場の9時に合わせて着くように行ったのだが、効率よく楽しむことができた。
家からDoor to Door で、ちょうど2時間。
この時間に行けば、駐車場も大丈夫。

ガイドツアーに200円で参加することができる。
1時間弱で、富岡製糸場のことを知るのには、うってつけだった。
入口の中央には、明治5年の碑が。
明治5年の建物が、残っている事自体すごいことだ。
東置繭所と呼ばれ、フランスの技術の粋を集めた建物だ。
レンガはフランス積みと言って、縦横、ジグザグに積んである。
木骨煉瓦造りと言われる工法だ。
日本にまだなかった技術ばかりだった。
1階が、事務所、作業所、2階が乾燥した繭の貯蔵所とした使用された。
国宝に指定されている。

長さ104.4m。

女工館。フランス人の女性教師の住居として建設された。

ここが操糸所。
繭から生糸を取る作業が行われた。
工場の、心臓部と言える。

長さが140mもある。
国宝に指定されている。1987年まで実際に片倉工業が操業していた。
この製糸場は、官営→三井→原→片倉と引き継がれていった。
片倉工業は、操業停止後も、年間8000万円かけ、この製糸場を維持していたという。
すばらしいことだ。

柱がないのは、このトラス構造による。
これも、フランスからの最新技術だった。
窓ガラスは、全てフランスからの輸入だった。
日本ではまだ作れなかったのだ。

この機械は、昭和40年代以降に使用されたもので、ニッサン製。
まだ動くという。
当初は、もちろん手作業の女工さんが、ずらっと並んで作業をしていた。

指導者とした雇われたブリュナの家。
重文に指定されている豪邸だ。
破格の条件で、政府に雇われていた。

寄宿舎。
立ち入りはできない。

東置繭所内での座繰り実演。
生糸は、髪の毛の半分ぐらいの太さだが、元々の蚕糸を10本程度よったものだそうだ。

西置繭所は、改修中だが、ヘルメット借り賃200円で、中を見学できる。
ちょうど瓦が全部はずされたところだった。

修理現場から、製糸場を見下ろす。
煙突も戦前のもの。

鉄水溜。重文。
日本でも明治8年製で、国内最古のもの。
海外から輸入して、横須賀で、製作したという。
生糸の製造には、きれいな水が必要だった。

東置繭所の避雷針。
デザインが、チャーミング。
雷の多い地域ということで、この避雷針のおかげで、雷にあわずに済んだのかもしれない。
見学時間約2時間で、満喫。

名物のおっきりこみうどん。