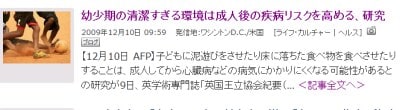座り方一つでも文化があります。外国から見ると正座はどう見えるのでしょうか?
---------- 【ここから引用】 ----------
【仏国ブログ】フランス人から見た日本の「正座」 2009/12/21(月) 11:05
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1221&f=national_1221_005.shtml
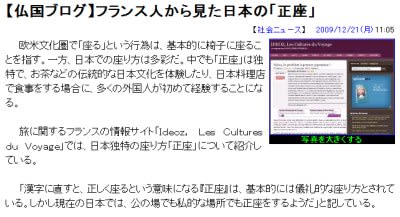
欧米文化圏で「座る」という行為は、基本的に椅子に座ることを指す。一方、日本での座り方は多彩だ。中でも「正座」は独特で、お茶などの伝統的な日本文化を体験したり、日本料理店で食事をする場合に、多くの外国人が初めて経験することになる。
旅に関するフランスの情報サイト「Ideoz, Les Cultures du Voyage」では、日本独特の座り方「正座」について紹介している。
「漢字に直すと、正しく座るという意味になる『正座』は、基本的には儀礼的な座り方とされている。しかし現在の日本では、公の場でも私的な場所でも正座をするようだ」と記している。
また、正座の歴史については「江戸時代の公式な場で初めて導入されたという。動乱と混乱に満ちた戦国時代が終わったことを民衆に示すためにも、上品で礼儀正しい形の座り方である正座が推奨されたようだ」とつづっている。
多くのフランス人は、正座を楽な座り方ではないと考えている。「徳川幕府も『正座』を快適な座り方ではないと考えていたのではないか。なぜなら、(正座に慣れていると思われる)日本人でさえも、足がしびれたりするからだ。もしかすると、『正座』を公式の場で用いることで、急襲を避けようとする意図があったのかもしれない」と意見を述べている。(編集担当:山下千名美・山口幸治)
---------- 【引用ここまで】 ----------
胡座(あぐら)の状態から片足を立てた座り方を立て膝と言います。
戦国時代の武将などでは胡座や立て膝が普通の座り方だったみたいですね。胡座はすぐに相手に斬りかかれない座り方だったのに対し、立て膝は武具を着装した際の合理的な座り方で、武者座りともいわれたんだとか。
現代生活はほとんど正座をする機会がなくなりました。法事などで正座をせざるを得ない時に足がしびれないような工夫も覚えておきたいですね。
---------- 【ここから引用】 ----------
【仏国ブログ】フランス人から見た日本の「正座」 2009/12/21(月) 11:05
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1221&f=national_1221_005.shtml
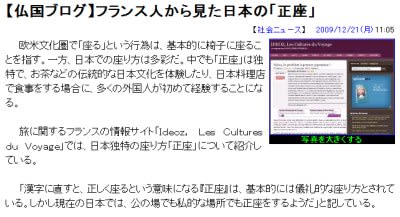
欧米文化圏で「座る」という行為は、基本的に椅子に座ることを指す。一方、日本での座り方は多彩だ。中でも「正座」は独特で、お茶などの伝統的な日本文化を体験したり、日本料理店で食事をする場合に、多くの外国人が初めて経験することになる。
旅に関するフランスの情報サイト「Ideoz, Les Cultures du Voyage」では、日本独特の座り方「正座」について紹介している。
「漢字に直すと、正しく座るという意味になる『正座』は、基本的には儀礼的な座り方とされている。しかし現在の日本では、公の場でも私的な場所でも正座をするようだ」と記している。
また、正座の歴史については「江戸時代の公式な場で初めて導入されたという。動乱と混乱に満ちた戦国時代が終わったことを民衆に示すためにも、上品で礼儀正しい形の座り方である正座が推奨されたようだ」とつづっている。
多くのフランス人は、正座を楽な座り方ではないと考えている。「徳川幕府も『正座』を快適な座り方ではないと考えていたのではないか。なぜなら、(正座に慣れていると思われる)日本人でさえも、足がしびれたりするからだ。もしかすると、『正座』を公式の場で用いることで、急襲を避けようとする意図があったのかもしれない」と意見を述べている。(編集担当:山下千名美・山口幸治)
---------- 【引用ここまで】 ----------
胡座(あぐら)の状態から片足を立てた座り方を立て膝と言います。
戦国時代の武将などでは胡座や立て膝が普通の座り方だったみたいですね。胡座はすぐに相手に斬りかかれない座り方だったのに対し、立て膝は武具を着装した際の合理的な座り方で、武者座りともいわれたんだとか。
現代生活はほとんど正座をする機会がなくなりました。法事などで正座をせざるを得ない時に足がしびれないような工夫も覚えておきたいですね。