依頼されていた原稿をやっと送ることができました。
「生涯学習でお好きな風に書いていただいて結構です」と言われて、それではと「生涯学習のまちづくりの現場から」なんてタイトルで、掛川での思い出や榛村元市長の言行録などから感じたインスピレーションをまとめました。
依頼は約7000字程度ということだったのですが、私の原稿の書き方は、まず粗筋で、テーマはあちこちに飛びながら、一つが800字程度のテーマの塊をいくつも書いてゆきます。
今回は15個ぐらい書いて、全部で1万2000字くらいのボリュームを作ってから、前後の脈絡やまとめ方、全体の盛り上がりなどを考えつつ削っては足す作業で7000字まで絞り込みました。
こういう原稿って、読み返してみると気に入らないところが何度も出てくるので、「締切で終わらせる」と決めてかからないと、いつまでもぐずぐずしてしまいます。
文書のリライトはブログでもなんでも次の発表の時までに改善しておけばよいくらいのテキトーなところがあった方がよろしいようで。
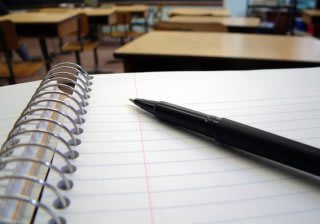
※ ※ ※ ※ ※
二宮尊徳先生は、大きなことをしようと思ったらまず小さなことをコツコツと続けることだ、として「積小為大(せきしょういだい)が大切だ」と言いました。
小田原藩の財政改革をしたときは、米を炊く釜についた焦げをこそげ落として、「これで薪がいくらか少なくて済むだろう」と告げました。
焦げをとることひとつをおろそかにせず、小さなことを馬鹿にせず積み上げるからこそ大きな事ができるのです。
原稿を書こうと思ったら、まずは知っていることを少しずつでも書いてみて、塊をいくつも作ってそれを組み合わせてゆくと比較的構成をまとめやすくなります。
あまり全体構成に悩まずに、まずは文字数を予定の二倍くらい書いてから削れば良いのです。
もっとも、確かに文章を削るのは新しく書くよりずっと簡単ですが、時数合わせとはいえ書いたものを消すのはもったいない気がして勇気が必要。
バラや樹木を剪定するようなつもりで大胆にやるのが良いですね。
校正が上がってきたら、全体を眺めて一行の文字数との関係で見た目が良いかどうかも考えます。
「…なのです。」なんて文章で最後の「す。」だけが文頭に来るようなら、文字を減らすか足すかして見栄えを整えます。
読んでみた時の音のリズム感にも注意するとなお良い文章に近づきますよ。
※ ※ ※ ※ ※
さて次は月末のシーニックバイウェイでの講演の準備です。
こちらは仲間内なのでお気楽に道東の未来のために必要なことを語ろうかと思いますよ。
「生涯学習でお好きな風に書いていただいて結構です」と言われて、それではと「生涯学習のまちづくりの現場から」なんてタイトルで、掛川での思い出や榛村元市長の言行録などから感じたインスピレーションをまとめました。
依頼は約7000字程度ということだったのですが、私の原稿の書き方は、まず粗筋で、テーマはあちこちに飛びながら、一つが800字程度のテーマの塊をいくつも書いてゆきます。
今回は15個ぐらい書いて、全部で1万2000字くらいのボリュームを作ってから、前後の脈絡やまとめ方、全体の盛り上がりなどを考えつつ削っては足す作業で7000字まで絞り込みました。
こういう原稿って、読み返してみると気に入らないところが何度も出てくるので、「締切で終わらせる」と決めてかからないと、いつまでもぐずぐずしてしまいます。
文書のリライトはブログでもなんでも次の発表の時までに改善しておけばよいくらいのテキトーなところがあった方がよろしいようで。
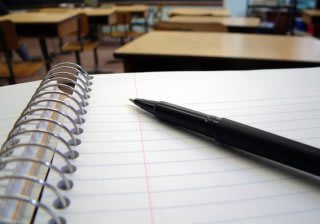
※ ※ ※ ※ ※
二宮尊徳先生は、大きなことをしようと思ったらまず小さなことをコツコツと続けることだ、として「積小為大(せきしょういだい)が大切だ」と言いました。
小田原藩の財政改革をしたときは、米を炊く釜についた焦げをこそげ落として、「これで薪がいくらか少なくて済むだろう」と告げました。
焦げをとることひとつをおろそかにせず、小さなことを馬鹿にせず積み上げるからこそ大きな事ができるのです。
原稿を書こうと思ったら、まずは知っていることを少しずつでも書いてみて、塊をいくつも作ってそれを組み合わせてゆくと比較的構成をまとめやすくなります。
あまり全体構成に悩まずに、まずは文字数を予定の二倍くらい書いてから削れば良いのです。
もっとも、確かに文章を削るのは新しく書くよりずっと簡単ですが、時数合わせとはいえ書いたものを消すのはもったいない気がして勇気が必要。
バラや樹木を剪定するようなつもりで大胆にやるのが良いですね。
校正が上がってきたら、全体を眺めて一行の文字数との関係で見た目が良いかどうかも考えます。
「…なのです。」なんて文章で最後の「す。」だけが文頭に来るようなら、文字を減らすか足すかして見栄えを整えます。
読んでみた時の音のリズム感にも注意するとなお良い文章に近づきますよ。
※ ※ ※ ※ ※
さて次は月末のシーニックバイウェイでの講演の準備です。
こちらは仲間内なのでお気楽に道東の未来のために必要なことを語ろうかと思いますよ。

































