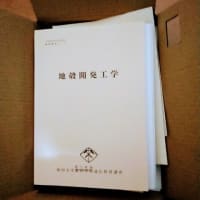| 起業3年目までの教科書 はじめてのキャッシュエンジン経営 |
| クリエーター情報なし | |
| 文響社 |
・大竹慎太郎
著者は、最初サイバーエージェントに入社し、いくつかの会社を経て現在はトライフォートの代表を務めている人だ。本書は、著者の経営方法についてまとめたものである。
本書の肝は、「キャッシュエンジン経営」ということだ。要するに事業のベースとして金の成る木を持っておいて、そこから得られるキャッシュを使って新しい分野にチャレンジしていくというのである。新しい分野では当たり外れがある。成功すればリターンは大きい代わりに失敗する確率も決して低くはない。キャッシュエンジンを持っていれば、たとえ失敗しても会社に与えるダメージを抑えられるというものだ。
確かに、金のなる木を持っていれば日銭は入る。しかしそれだけでは夢はない。新たな分野に投資してチャレンジすることが大切なのだ。日銭を稼げる事業を持つということには賛成なのだが、幾つか気になる部分がある。列挙してコメントしていこう。
採用で、「うちの社員はやる気がない」と嘆く会社の代表者について、
<採用の時点で「やる気のありそうな人」を採ろうとしていないのだ。>(p76)
これは、採用する側の見る目にも関わってくると思う。見る目のない人間が「やる気のありそうな人」を採用すると、体育会系の組織になってしまい、パワハラの温床に・・・。そんな会社、私は嫌だな(笑)。
<高学歴の人材は確かに暗記型の勉強に慣れ親しんでいる>(p115)
これは著者の偏見に過ぎない。高学歴で暗記の嫌いな人はいくらでもいる。私なども世間の標準から見れば高学歴だとみなされると思うが、昔から暗記は苦手だ。学生時代に、自分の周りにも暗記力がすごいと思った人はいなかった。理系の人間は結構暗記が苦手だと思う。そもそも理系では暗記力しかない人間は周りから評価されない。
<その上司(評者注:サイバーエージェントの新人マネージャー時代の上司)はビジネス書やセミナーに影響されやすい人で、何かをインプットすると、すぐに言動ががらりと変わる人だった。>(pp155-156)
著者の場合は、これがいい方に行ったようだが、これってダメ上司の典型やん。私も会社勤めをしていた頃に経験があるが、本社の企画部門あたりがこれをやると、やたらとくだらないことを全社に押し付ける。その被害は甚大だろう。当然何の効果もないので、初めは威勢がいいが、そのうち尻すぼみになって消えてしまう。人に影響を受けやすい人間には、「あんた、その頭はなんのために付いているのか。」と小一時間問詰めたくなってくる。
こんな記述もある。社員の中にビジョンを浸透させることについてだ。
<トライフォートの場合の答は、「朝礼で唱和させろ」でも「高価な額縁に入れて飾れ」でも「たまに各社員がいえるかどうかの抜き打ちチェックを行え」でもなかった。そういった頭ごなしの命令形のスタイルで、人に何らかの考え方が受け入れられることは難しい。>(p104)
この考えかたには賛成だ。とにかく上の方から何かが押し付けられてくると、意味がよく分からない現場の方ではそんな対応をしがちだろう。納得感がなければ、そしてどんなにいいビジョンでも、神棚に飾ったり、意味も分からず唱えるお経のようになってしまいかねない。
また経営学の教科書によく出てくるPDCAサイクルについて、次のように言っている。
<だから業務は、「PDCAではなくCPDAの順番で回せ!」が正しい回答なのである。>(p392)
それはPを頭の中でウンウン考えて的外れなものとするより色々な人の知恵を借りた方がいいということのようだ。しかし、これは、Pをどう定義するかの問題だろう。そもそもPがないのにどうチェックするんだとツッコミたくなるし、まともなところなら、色々と調査したうえでPを立てるはずだ。
本書全体を通して、著者が最初に就職したサイバーエージェントの藤田晋氏に心酔しているように思える。それではどうして転職や独立をしたのか。おそらく最初の目標が起業するということだったのだろうが、そのあたりをもっと知りたいところだ。特にトライフォートを起業して1年で多くの社員が退職したことが辛い体験(p397)だったのならなおさらだ。人が辞めるのは辛いが自分は辞めてもいいというのは説明不足だと感じてしまう。
しかし、キャッシュエンジン経営の例として「電通」を挙げている(p58)のはかなり気になる。あれだけ世間で騒がれた会社だ。キャッシュエンジン経営をするには社員の多大な犠牲が必要なのかとつい思ってしまう。トライフォートの労働条件(賃金、勤務時間、休暇など)をちゃんと最初に示したうえでないと、どうも眉に唾をつけて話を聞くようになってしまうのだ。
本書を読んだ感想としては総論は賛成なのだが、各論を見ると気になる点が色々あるというところか。
☆☆☆