9時45分、起床。
「緊急事態宣言」が出そうである。

取り箸派VS直箸派というのは結婚によって生じる家族における異文化対立の1つだが、それがコロナ禍によって顕在化し、新聞の人生相談欄に登場した。思うにコロナ禍は、新たな家族問題を生み出すとういうよりも、すでに存在している問題を顕在化させ増幅させる働きがある。その一方で、もしかしたら、コロナ禍によって潜在化ないし低減する問題もあるのかもしれない(ただしそれは人生相談欄からはわからない)。
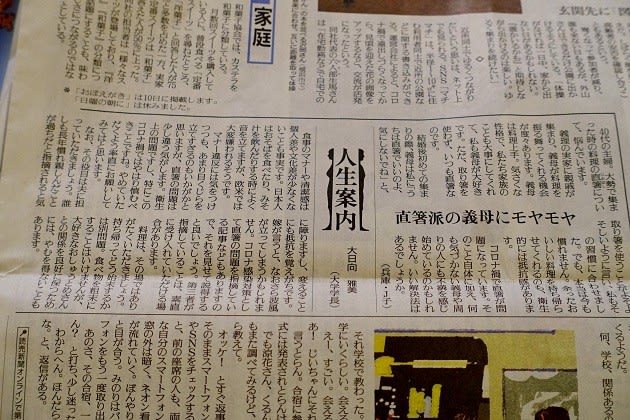
朝食は軽くトーストを一枚食べただけで、昼に川越からやってきた妹夫婦と昼食をとる。お節料理+出前で取った「濱清」の鮨。いつもであれば鮨は大きな桶で一緒盛りにするところだが、今年は個別で。

デザートはアイスクリーム。私は抹茶をチョイス。

妹夫婦は3時半頃に帰って行った。家の前で記念撮影。彼らも私たち夫婦も全員60代。健康第一で過ごしましょう。

年賀状の返信を近所のポストに投函しがてら、二人を途中まで見送る。

それから1時間ほどして、息子も名古屋に帰って行った。見送りがてら駅まで歩く。

息子を見送ってから、東急プラザの屋上に上ってみる。

日没の時刻だ。

幸せの観覧車に乗る。

西の空が茜色に染まっている。

そのあと「テラス・ドルチェ」に寄ってみたが、三が日は5時閉店ということで、いまから入ることはできなかった。

帰宅して、夕食の時間まで放送原稿を書く。

年末から過剰摂取の状態が続いているので、今夜は雑煮(餅は2つ)とサラダですませる。お節の残りも摘まんだが、写真は省略。

NHKオンデマンに加入して(月990円)、年末に見逃した『7年ごとの記録 35歳になりました』を観る。7歳(1992年)、14歳(1999年)、21歳(2006年)、28歳(2013年)と同じ子どもたちを追跡インタビューしてきたドキュメンタリーで、今回は35歳(2020年)版である。
もの足りない内容だった。ずっと観てきた私には、前回の28歳のときからの7年間のことがわたってそれはよかったのだが、1時間13分という尺(一人平均8分)は彼らの「現在」を知るには十分だとしても、彼らの「これまでの人生(5時点)」を辿るには全然不足である。少なくとも2倍の尺が必要である(番組としては21歳のときのように、前半・後半の二部構成にする)。
たとえば最初に登場した優美さん(豊田市出身)の場合、21歳のときの記録がまったく紹介されていなかった。そのため14歳のときの「将来は出版社に勤めたい」との語りの後に28歳のときの東京の出版社で働く彼女の映像が紹介されて、夢をすんなり実現したかのような印象を与えてしまっていたが、21歳のときの彼女は就活で苦労していて、ようやく地元の会社の社員食堂の管理栄養士になったのである。しかし、編集者になる夢を捨てられず、働きながら週末に東京に行って転職活動を続け、1年後に家族の反対を押し切って出版社に転職をしたのである。また、28歳のときの記録では地元の友人たちはみな結婚・出産を経験したのに自分は独身のまま東京で働いていて「このままでいいのだろうか」という不安を語っていたが、それも今回は省略されていたので、結婚をして二児の母となり育休中の現在(35歳)の彼女の穏やかな語りの意味も今回の番組だけを観た視聴者には十分に伝わってはいないだろう。
7歳の時の出演は本人の意志ではなかったろう。ただ無邪気にテレビカメラの前に立ったのである。なので途中で番組を降りた人もいたし、途中から復帰した人もいた。そのあたりのこと、つまり7年ごとに公共の電波で自分の人生が多くの人に見られるということについての感想も聞いてみたかった。尾上松也は28歳のときの出演以降、テレビの仕事が増えたと語っていたが、芸能人ではない他の人たちにとってどのような影響があったのかを知りたい。

放送原稿を書いてから、風呂に入り、『山下達郎のサンデー・ソングブック』をradikoで聴きながら、今日の日記とブログ。

2時15分、就寝。















