
カンガルーケアに警笛????
カンガルーケアは何のためにあるのか!!!!
産後すぐの刷り込みや頑張って自分の力でこの世に生まれたことを誉めてあげることでもある。(医師・助産師が赤ちゃんの生まれる力を無視して取り上げるところもある)
無知な医者は健常な赤ちゃんを保育器に入れる。
カンガルーケアは、体温調節(保温)、呼吸刺激(未熟児の無呼吸を刺激し、予防する)や母子の愛着形成などにより、そのの効果が見直されています。
先進国でも未熟児医療に積極的に取り入れられるようになっています。
誕生直後、約1時間の新生児は驚くべき能力を持っています。
生まれた赤ちゃんを母親の胸からお腹におくと、しばらくして目を開け、左右をうかがい、次いで首を振り、お腹をけ上がり、おっぱいにたどりつき、 乳首にむしゃぶりつきます。
出産時の早期接触(カンガルーケア)は、 母と子の絆づくりの面からも、母乳栄養・母乳育児の面からも現在世界の多くの出産施設で取り入れられています。
産後すぐに、母子分離し保育器へ入れる事の方が赤ちゃんの為になる…とも受け取れるような報道の仕方…。大いに問題があります。
2時間後に抱きしめる、ここに意味はあるのか保育器の中で赤ちゃんに糖水を座らせて飲ませているのには驚いた。
この産婦人科は「母乳哺育は低血糖」でも物議を醸した。
母子にとって産後の2時間は、とてもとても大切なハネムーンの時です。
赤ちゃんの心を無視した保育器への隔離には反対です。
アプガースコアが低いときにはカンガルーケアを行ってはいけません。
カンガルーケアに公的なガイドラインが必要という人がいますが必要ない。
赤ちゃんの容態や安全を見ながら行うのが当然だからである。
赤ちゃんを見ることが出来ない医師や助産師、看護師は行うべきではない。
形だけのカンガルーケアはするべからず。
ちょっとした異変も見逃さず、アプガースコアが高いときに行うべきである。
アプガースコアAppearance(皮膚色)、Pulse(心拍数)、Grimace(刺激に反応)、Activity (筋緊張)、Respiration(呼吸)のそれぞれの頭文字をとって、アプガースコア(APGAR score) です。
出生した赤ちゃんの元気度を採点するものです。
何故行うのか意味もわからずカンガルーケアを行うことは赦せない。?カンガルーケアは客を呼ぶブランドではない。
マスコミはもっともっときちんと取材をすべし!!!!
表面や一部の医師の言動だけで鵜呑みにするな。
カンガルーケアーが問題なのでなく、その状態でママと赤ちゃんを二人っきりで放置することが、最もとがめられる問題であることに焦点をあてて報道してほしいものです。
赤ちゃんが重篤な状態になっているケースは、母子を放置したことによることが大きいのではないだろうか。
みなさん、報道を鵜呑みにしないでください。
カンガルーケアは、素晴らしいのです。
(赤ちゃんの状態がいいとき)


















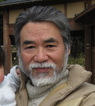






カンガルーケアの体験出来て良かったですね。
2時間眠らせてくれた病院のスタッフも素晴らしいですね。
あなたたちお二人の状態がいいから起こさなかったのでしょうね。
これからもお二人のお子さん共々、楽しんで共育してください。
調べものがあり何となく検索していたら、このページがあり拝見させて頂きました。
私は2児の母です。
お姉ちゃんの時の産院はカンガルーケアを取り入れていないので、どうしてもカンガルーケアをしたいと言う強い希望があり、弟の時は実施している病院(総合病院)を選びました。
その結果、ちっちゃな息子と心地の良い幸せな時間を過ごせて感動しました。
あのぬくもりは未だ忘れていません。
思い返してみると、授乳させてからしばらくすると誰も居なくなり息子と二人きり。
ウトウトしてきてしまい眠ってしまった私、授乳しながら2時間寝てしまいました。
目を覚ました時も息子と二人きり。
途中様子を見に来てくれていたのかもしれませんが、ニュースを聞いて思わずゾッとしました。
幸い息子は元気でいてくれましたが、他人事じゃない気がしました。
まっ、睡魔に負けてしまった私もどうなのですかね。
カンガルーケアのおかげ!?かどうかはわかりませんが…とても元気で(現在1歳2M)、ほとんど手のかからない可愛い息子でいてくれています。
あの大いなる幸せを感じさせてくれるカンガルーケアを選択して、私はとても良かったと思っています。
「命を二度もらった」素晴らしい言葉ですね。
お母さんに救ってもらったのですね。
その思いを抱きながら分娩介助、産褥支援をされているのですね。
あらためて、乳幼児期のこどもの命の危うさに気づかせていただきました。
ありがとうございました。
妊娠期の命の教育やお産、産後のケアについてももっともっとたくさんの時間をかけて学んでいただくことが重要ですね。
産後の子育ても見据えて。
爺のブログを見ていただいている皆さんもこれを契機にいろいろ考えていただけると、一石を投じたことに意味が出てくると思います。
ありがとうございます。
ガイドラインを作った先生たちの講演を先日聞いた助産師です。
その中で、「『正常新生児』という言葉はガイドラインで使っていない。
正期産か、アプガースコアはどうか、これまでに分かっている病気は無いか、とみることはできるが、
うまれてからしばらくして重症化する疾患がある。それは出生直後のカンガルーケアの時期には分からないため。」
「カンガルーケアは、いい側面がコクランレビューにも報告されているため、自分の施設では続けている」
私も、「生まれたばかりの新生児の危うさ」を多くの人々に知ってもらうのは重要だと思っています。
決して母親だけではなく一緒に家族もいて、医療者もリスクアセスメントをしながら、なるべくたくさんの愛情ある目で一緒に観察することができると、悲しい結果を減らせると思う。
どんなことを見ながら、幸せな時間を過ごすのか。
それを妊娠中からみんなが知っていて一緒に赤ちゃんを守る、
・・・母親やお産に立ち会った家族はお産で疲れきってボロボロだったり、医療者は作業や記録もしながらだったり・・・みんな不十分なのです。
それだけではなく、乳幼児突然死症候群のことも一般の人たちに知ってもらうといいな、と思っています。
それほど乳幼児期の子どもたちは、危ういということを。
リスクとしてハッキリとしている因子もあるし、分かっていない因子もあるけれど、
親としてはきちんと知って、きちんとリスク排除をしたい。
私自身、乳児期に真っ青になっているのを母親が見つけ適切に対応してくれたということを聞かされていて、他人事ではない気持ちなのです。私は母に二度いのちを頂きました。
話がずれてすみません。
「カンガルーケアをしている最中くらい、我が子の様子を観察し、命を守ってやれないような女性はカンガルーケアなど希望すべきではない」その通りだと思います。
「我が子の命を守るのは母である」これもその通りです。医者のせいにすべきではありません。
ただ、全ての医療従事者にあてはまるものではないのも事実です。
自宅分娩では、産後の処理の間も助産婦は複数で介助しますので、母子の容態に注意をはらいながらおこなっていました。
爺のこれまで自宅分娩や有床診療所での分娩では、
赤ちゃんとお母さんに気遣いをしているように思います。
突然死は、どのようなお産でもおこることは理解しています。
カンガルーケアの知識が欠落している産科医や医療従事者がいるのは事実です。
ただ赤ちゃんをお腹の上にのせればいいと思っています。
その意味では、ガイドラインは必要なのですね。
ガイドラインには「健康な正期産児には、ご家族に対する十分な事前説明と、機械を用いたモニタリングおよび新生児蘇生に熟練した医療者による観察など安全性の確保(今後さらなる研究、基準の策定が必要です。)をした上で、出生後できるだけ早期にできるだけ長く(出生後30 分以内から、出生後少なくとも最初の2 時間、または最初の授乳が終わるまで、カンガルーケアを続ける支援をすることが望まれます。)、ご家族(特に母親)とカンガルーケアをすることが薦められる。」とあります。
いつも貴重な情報ありがとうございます。
母親が我が子の状態を常に観察することが重要である。
我が子の命を守るのは「親」です。
情報のソースは某テレビ番組でしょうか。赤ちゃんまでテレビに出ていたようですね。
カンガルーケアが新生児医療に有用なのは議論の余地はありません。ただ、ひげ爺さまも混同しているように、
「医療の対象でない、正常のお産と健常な新生児」
にとってカンガルーケアは必要か、とうことです。これには答えはないはずです。
それと、カンガルーケアのガイドラインは残念ながらもう作られています。
http://square.umin.ac.jp/kmcgl/kasou02.html
新生児を扱っていると、残念ながら突然死してしまう赤ちゃんに出会うこともあります。
産婦人科医院で死ぬとそれは産婦人科医の管理責任となり
自宅分娩や吉村医院で死ぬとそれは運命、悪い遺伝子を持った赤ちゃんであったということになります。
カンガルーケアは客寄せサービスではない。母子愛着形成にとって重要な儀式である。
それなら、カンガルーケアをしている最中くらい、わが子の様子を観察し、命を守ってやれないような女性はカンガルーケアなど希望するべきではない。
わが子の命は、母が守る。なんでもかんでも医者のせいにしないでほしいですね。お産は病気じゃないんだから。
自宅出産や助産院分娩では、当然出産後は母子は二人っきりで放置されます。
助産院分娩では突然死がおこらない、のではなく、表に出てこないだけだということはご理解いただけると思います。