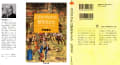昨日は横浜駅で1000円の理容室で髪の毛をカットしてもらった。左右と後ろは3ミリのバリカンで、前と天辺は9ミリのバリカンで、短くしてもらった。見た目は五分刈りと同じ。98%は白髪なので、このように短くするとほとんど髪の毛があるようには見えないのが悲しいといえば悲しい。
このようにしてほしい、と伝えたところ店の人から「本当に刈ってしまっていいのですか?元には戻りませんよ。刈ってから元のように戻せとおっしゃっても無理ですよ」と云われて思わず苦笑い。「毎年の夏バージョンですからご心配なく」と伝えた。
先に「元に戻りませんよ」と言ってから「元のように戻せと言われても‥」と続いたので、余計に私は傷ついて、半ばはムッとした。逆ならまだ柔らかい指摘なのだが‥。そのために「なかなか生えてきませんよ」というのが強調されたように聞こえた。確かに前と天辺は伸びる速度は遅い。左右と後ろは元気が良く、太いのだが、それ以外は細いし弱々しい。そのうち毛穴も閉じてしまいそうである。しかしあからさまに指摘されると普段気にしていなくとも、あえて指摘されたくはない。養毛剤を使用するほどの色気はとうになくなっている。
まぁ店員悪気はなかったようなので、笑ってごまかした。
このように短く刈り込んでしまうのはもう10年以上しているはずだ。一番初めに別の店員に言われたのは「夏だからといって短く刈りこむとかえって暑いですよ」ということだった。確かに直接陽があたり、汗が皮膚を伝ってすぐに顔にたれてくる。髪の毛が陽をさえぎらず、汗も溜めることはない。しかし風が吹いた時の気持ちの良さには代えられない。
定年退職後からは野球帽をかぶるようにしている。頭頂部が一番髪の毛がうすいので直に日があたり、帽子をかぶらなかったら山ですっかり日焼けしてしまった。日焼けして分厚く剥けた皮膚が枕を汚して、妻に怒られた。枕と布団に黒く剥けた皮膚が散乱していた。人前に出られなくて野球帽を被ることにした。それが帽子をかぶり始めたきっかけである。それまで帽子はほとんど被ったことはない。すぐにどこかに置いてきてしまう。
半世紀以上の習慣でようやく眼鏡と時計と財布、四半世紀の習慣で携帯電話と定期・財布だけは忘れないようになった。だが、60歳を過ぎて新たに身につけるものを置き忘れないようにできるとは思いもしなかった。
確かに今でも野球帽はときどき置き忘れてしまう。組合の事務室やその傍の飲み屋ならばすぐにそれは出てくるが、それ以外の居酒屋などではまず戻ってこない。だから安い野球帽しか手に入れない。小さめだが100円ショップで購入したものも愛用している。
このようにしてほしい、と伝えたところ店の人から「本当に刈ってしまっていいのですか?元には戻りませんよ。刈ってから元のように戻せとおっしゃっても無理ですよ」と云われて思わず苦笑い。「毎年の夏バージョンですからご心配なく」と伝えた。
先に「元に戻りませんよ」と言ってから「元のように戻せと言われても‥」と続いたので、余計に私は傷ついて、半ばはムッとした。逆ならまだ柔らかい指摘なのだが‥。そのために「なかなか生えてきませんよ」というのが強調されたように聞こえた。確かに前と天辺は伸びる速度は遅い。左右と後ろは元気が良く、太いのだが、それ以外は細いし弱々しい。そのうち毛穴も閉じてしまいそうである。しかしあからさまに指摘されると普段気にしていなくとも、あえて指摘されたくはない。養毛剤を使用するほどの色気はとうになくなっている。
まぁ店員悪気はなかったようなので、笑ってごまかした。
このように短く刈り込んでしまうのはもう10年以上しているはずだ。一番初めに別の店員に言われたのは「夏だからといって短く刈りこむとかえって暑いですよ」ということだった。確かに直接陽があたり、汗が皮膚を伝ってすぐに顔にたれてくる。髪の毛が陽をさえぎらず、汗も溜めることはない。しかし風が吹いた時の気持ちの良さには代えられない。
定年退職後からは野球帽をかぶるようにしている。頭頂部が一番髪の毛がうすいので直に日があたり、帽子をかぶらなかったら山ですっかり日焼けしてしまった。日焼けして分厚く剥けた皮膚が枕を汚して、妻に怒られた。枕と布団に黒く剥けた皮膚が散乱していた。人前に出られなくて野球帽を被ることにした。それが帽子をかぶり始めたきっかけである。それまで帽子はほとんど被ったことはない。すぐにどこかに置いてきてしまう。
半世紀以上の習慣でようやく眼鏡と時計と財布、四半世紀の習慣で携帯電話と定期・財布だけは忘れないようになった。だが、60歳を過ぎて新たに身につけるものを置き忘れないようにできるとは思いもしなかった。
確かに今でも野球帽はときどき置き忘れてしまう。組合の事務室やその傍の飲み屋ならばすぐにそれは出てくるが、それ以外の居酒屋などではまず戻ってこない。だから安い野球帽しか手に入れない。小さめだが100円ショップで購入したものも愛用している。