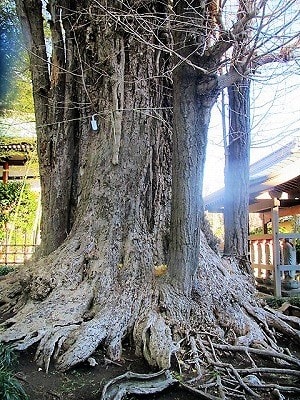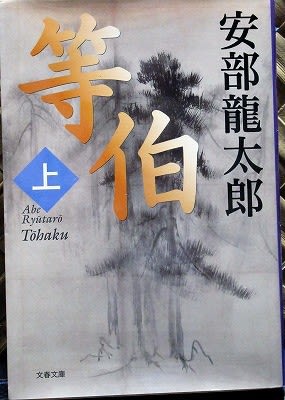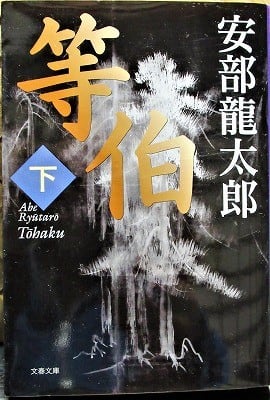日本史や世界史でわからないことがあったとき、アマゾンで中古の副読本を購入して参考にしたらじつに便利。
日本史の老舗「山川出版社」の図録は、歴史年表・人物の紹介・文化の流れ・産業・宗教など、カラフルな写真・図版が満載なのが魅力。(360頁)

とりわけ世界史は、世界地図・各国の歴史変遷・日本と世界のつながりなど、断片的で曖昧だったオイラの知識をストンとつなげてくれる(337頁)。しかも、中古なので数百円で入手できる。発行が古いと1円で買えるものさえある。
これを眺めてみるだけでも、自分はいかに「無知」であるかを思い知らせてくれる。一気に髪の毛が邪魔だった高校生時代に戻った瞬間を味わえる優れたアイテムだ。高校生時代には邪魔だった教科書だったが、その知識の宝庫のありがたみが半生記後の今になりやっとわかったわけだ。