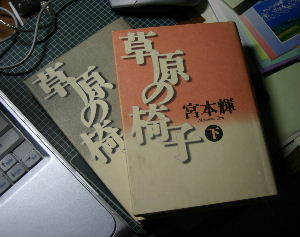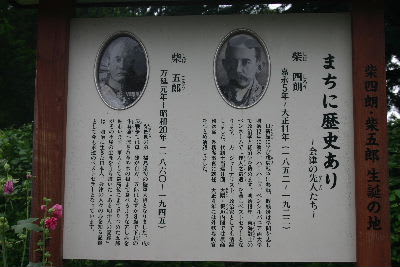《センリョウの葉上のキボシカミキり》
桑の葉上に、今年もまたキボシカミキリを発見した。なんだかとても嬉しくなった。
季節はいつも同じように移ろい、また季節の虫に巡り会えたのだ。良く来たなと呼びかけた。
でも、去年の夏出会った君は、今日の君ではないよね。去年のは君のお父さんか?
思えば、チョウも、トンボも、草花も、間違いなく初めて巡った季節に命をもらい、精一杯に生きて死んでいく。庭の小さな生き物の夏は、たいてい一度きりの夏なのだ。
ふと、何度も季節の移ろいを見つめ、精一杯の生き様を見つめることができる自分の幸せを思わずにはいられなかった。
それにしても、この庭はなんと無限の命にあふれていることか。
桑の葉上に、今年もまたキボシカミキリを発見した。なんだかとても嬉しくなった。
季節はいつも同じように移ろい、また季節の虫に巡り会えたのだ。良く来たなと呼びかけた。
でも、去年の夏出会った君は、今日の君ではないよね。去年のは君のお父さんか?
思えば、チョウも、トンボも、草花も、間違いなく初めて巡った季節に命をもらい、精一杯に生きて死んでいく。庭の小さな生き物の夏は、たいてい一度きりの夏なのだ。
ふと、何度も季節の移ろいを見つめ、精一杯の生き様を見つめることができる自分の幸せを思わずにはいられなかった。
それにしても、この庭はなんと無限の命にあふれていることか。












 ><
>< ><
>< ><
>< ><
><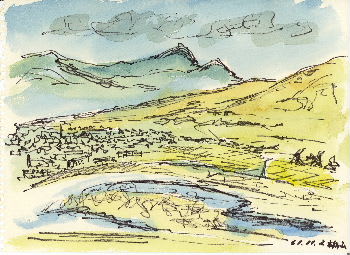 ><
>< ><
>< ><
><


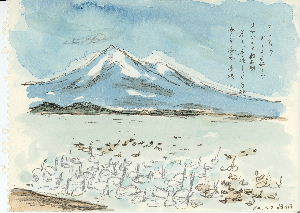 ><
>< ><
>< ><
><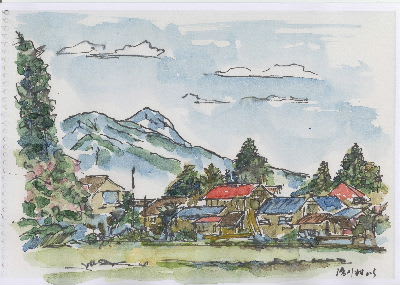 ><
><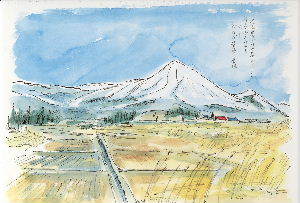 ><
>< ><
><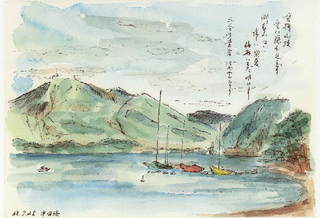 ><
><