都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
歳をとると、何らかの薬を服用していることは多くなります。今日はそんな薬の語源と字源について考えます。
実はいろいろな説がありますが、島根県の出雲大社にある古文書によると「奇(く)すしき力を発揮することから、くすりというようになった」と伝えられています。
|
くす・し【奇し】 形シク ①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集[18]「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語[帚木]「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」 ②奇特である。神妙である。枕草子[292]「物忌み―・しう」 広辞苑第六版より引用 |
この「奇すしき」とは、古い言葉で「並みより優れている、突き出た、不思議な、神秘的な」という意味で、そこから「くすり」という言葉が生まれたといわれています。
|
くすり【薬】 (一説に「くすし(奇)」と同源か) ①病気や傷を治療・予防するために服用または塗布・注射するもの。水薬・散薬・丸薬・膏薬・煎薬などの種類がある。万葉集[5]「雲に飛ぶ―はむともまた変若おちめやも」 ②広く化学的作用をもつ物質。釉薬うわぐすり・火薬・農薬など。 ③心身に滋養・利益を与えるもの。比喩的にも用いる。「毒にも―にもならない」「失敗が彼の―になればよいが」 ④ちょっとした賄賂わいろ。鼻薬はなぐすり。「―をかがせる」 ⑤ごく少量のたとえ。「―ほども無い」 広辞苑第六版より引用 |
この話し言葉の「くすり」に、大陸から伝わった漢字の「薬(やく)」をあてています。
当時の薬は草木等を使った漢方医学だったため、「草木によって体の調子がよくなる、楽になる」という意味を持つ「薬」(草かんむりに楽)を使ったという説があります。

藥(薬) =艸 + 樂
手鈴を振って病魔をはらったので癒す意。
病気を癒す草で、くすりの意。
樂(楽) 図↓
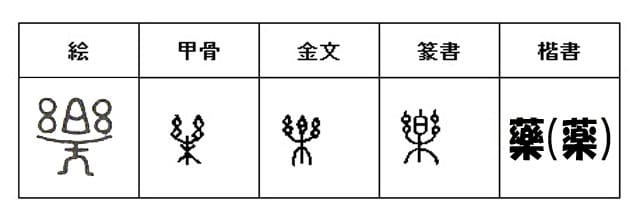
ヤママユが木の上に二つの繭を作った姿。
白川説では、柄のある手鈴の形。手鈴で奏でる音楽。
音楽をたのしむことから、たのしいの意。
「薬」という文字を使った言葉で面白いものを2つ紹介したいと思います。
どちらも「くすり」が関係しているので、「薬」の文字が使われています。
【薬玉(くすだま)】
お祝いなどで使われる「くすだま」は、中国の漢の時代に邪気を祓うものとして用いられたのが始まりで、
麝香(じゃこう)、沈香(じんこう)、丁子(ちょうじ)などの薬を入れていました。
|
くす‐だま【薬玉】 5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。夏 広辞苑第六版より引用 |

【薬缶(やかん)】
「やかん」は、もともと薬を煎じるために作られたものでした。
江戸時代になり、お茶を飲む習慣が広まると、お湯を沸かす道具として使われるようになりました。
|
や‐かん【薬缶】‥クワン (ヤッカンの約。もと薬を煎じるのに用いたのでいう) 銅・アルマイトなどで鉄瓶の形に造った容器。湯沸し。茶瓶。去来抄「うづくまる―の下の寒さかな」(丈艸) 広辞苑第六版より引用 |
薬(くすり)は、逆から読むと「リスク」となります。薬には副作用というリスクもありますので正しく使いましょう。


















