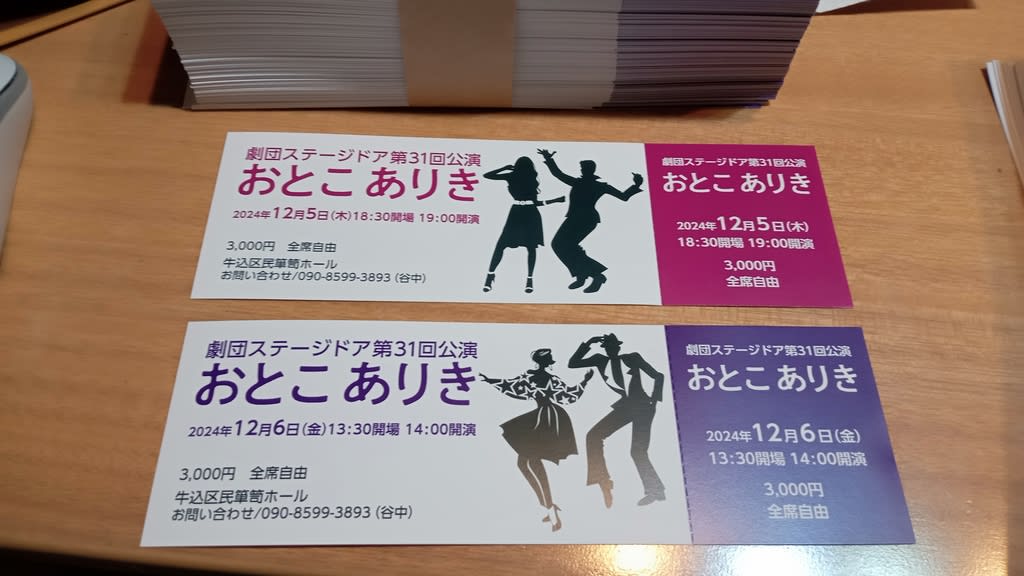今日は座長と室さんとの3人で、今年度の劇団公演の打ち合わせ。
いわゆる運営ミーティングで、ここ数年毎年行っているものです。
いつも通り、2時に新宿のルノアールに集合。
今日は、座長から次回公演のあらすじと、配役の説明がメインの話題。
昨年は僕が主役で、朴訥な男の生き様を描いた芝居だった。

お陰様で、去年の公演はことのほか評判が良かったです。
好評だった要因の一つは、脚本の変化にあったと思いますね。
今までの話は、主役が誰なのか?はっきりとしなかった。
そんな訳で、場面によって誰の話なのかが判らなくなるような芝居だった。
去年は主役の僕一人が出ずっぱりで、ハッキリしていたため、
どの場面でも話がボヤけずお客様にも判り易かったという。
もう一つは、シニア劇団らしい芝居の内容。
舞台上でのエネルギーは圧巻だっという感想を多々頂いています。

さらにシニア世代らしい題材で死や認知症、

連れ合いに先立たれた男の心情など・・・。
来場者の殆どがシニア世代なので、そういった話にお客様も共感する部分が多かったという。
この二つが、昨年の公演がお客様に好評だった要因だと思う。
さて、今年の芝居の話は老姉妹の話。
去年が男性の話だったので、今回は女性の話にしようという主旨。
配役もほぼ決まって、舞台セットの事も含めて芝居の流れをどうするか?
そんな事を含めて舞台を想定して、色々と意見を出し合って脚本の土台を作る。
実際に脚本を作るのは座長なんですけどね。
ここ数年は、こういった話し合いを経て台本を作って居る。
去年は、台本が出来上がった後に、大どんでん返しで主役を交代し
台本を書き直したりという事もあったので、これで決定という訳では無いです。
こういった事前打ち合わせで、いつも意見が食い違っていたのが僕と室さん。
ところが、去年からその様子が変わって来て、意見が一致する事が多くなった。
今日の打ち合わせでも去年に続いて、室さんとほぼ意見が合った。
そして、公演をいつにするかの話。
こればかりは、会場を確保しない事にはどうにもならない。
会場確保の担当は僕なので、ちょっと大変です(笑)
いよいよ、公演に向けて再始動・・・と言ったところですね。