あーあ、仕事再開。
今日は2週間ぶりに仕事に行きました。
お土産があったのと、帰りに自宅へ寄るつもりなので車で通勤。
今日は10時前に到着した。
僕のいない間、指示してあった仕事をきちんとやってくれていた。
電気回路の修理を依頼されていて、その受け入れ検査をやるように言い、
僕がやるときに作った、チェックシートに各部の電圧を記入したり、
入出力チェックをやって、不具合があった場合のチェック方法も教えてあった。
その作業も、僕が教えた以上の事をきちんとやってくれていた。
もう僕が居なくても仕事が出来るなって、ちょっと安心したし、嬉しかった。
僕が居ない間に、手配していた板金一式が出来上がっていて、こちらも問題なし。
来週からいよいよ実験的な装置の電気回路のチェックが出来る。
今回の電気回路はペルチェ素子
を使って、大きなタンクの中に入る溶剤の冷却を試みる。
適正な電圧がいまだに掴みきれていないので、ちょっと大変。
ペルチェ素子は2種類の金属の接合部に電流を流すと、
片方の金属からもう片方へ熱が移動するというペルティエ効果を利用した板状の半導体素子。
直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が起こる代物。
車などに乗せる小型冷温庫、医療用冷却装置などに使用されている。
ただ、この素子は欠点もあって簡単に使えず、前の会社でも使いあぐんでいた。
その欠点は、移動させる熱以上に素子自体の放熱量が大きいため、
冷却メカニズムとしては電力効率が悪いという点、
吸熱側で吸収した熱と、消費電力分の熱が放熱側で発熱するため、
ペルティエ素子自体の冷却が大変というところ。
冷却の手段として広く普及しない理由でもある。
また、エアコンのような断熱圧縮を利用したヒートポンプの熱交換とは異なり
「熱移動」であるため、排熱側の十分な冷却を行わないまま負荷をかけ続けると、
吸熱側の冷却効率が落ちるばかりでなく素子自体が破損・焼損することがあるうえに、
印加電圧が大きくなると発熱量が増えて冷却効率が悪くなるという厄介者。
しかし、あえて今回はそのペルチェ素子での冷却にチャレンジしてみた。
だから、まだ上手く行くかどうかは未知数。
たった3㎜の厚さの素子だから、吸熱面と発熱面の断熱も必要になる。
今回は強制空冷(ファンでアルミ製のフィンを冷やす方法)を使って
何所まで冷却できるのか?その実験を来週やる事にした。
考えてみれば、前の会社でもこんなチャレンジの連続だったなぁ・・・・
帰りに自宅へ寄ったら、契約書にサインして返送するよう封書が来ていた。
半年更新なので、10月から来年の4月までの契約書。
けれど、この仕事が上手く行ったら、一区切りつけるつもりです。


















































































































































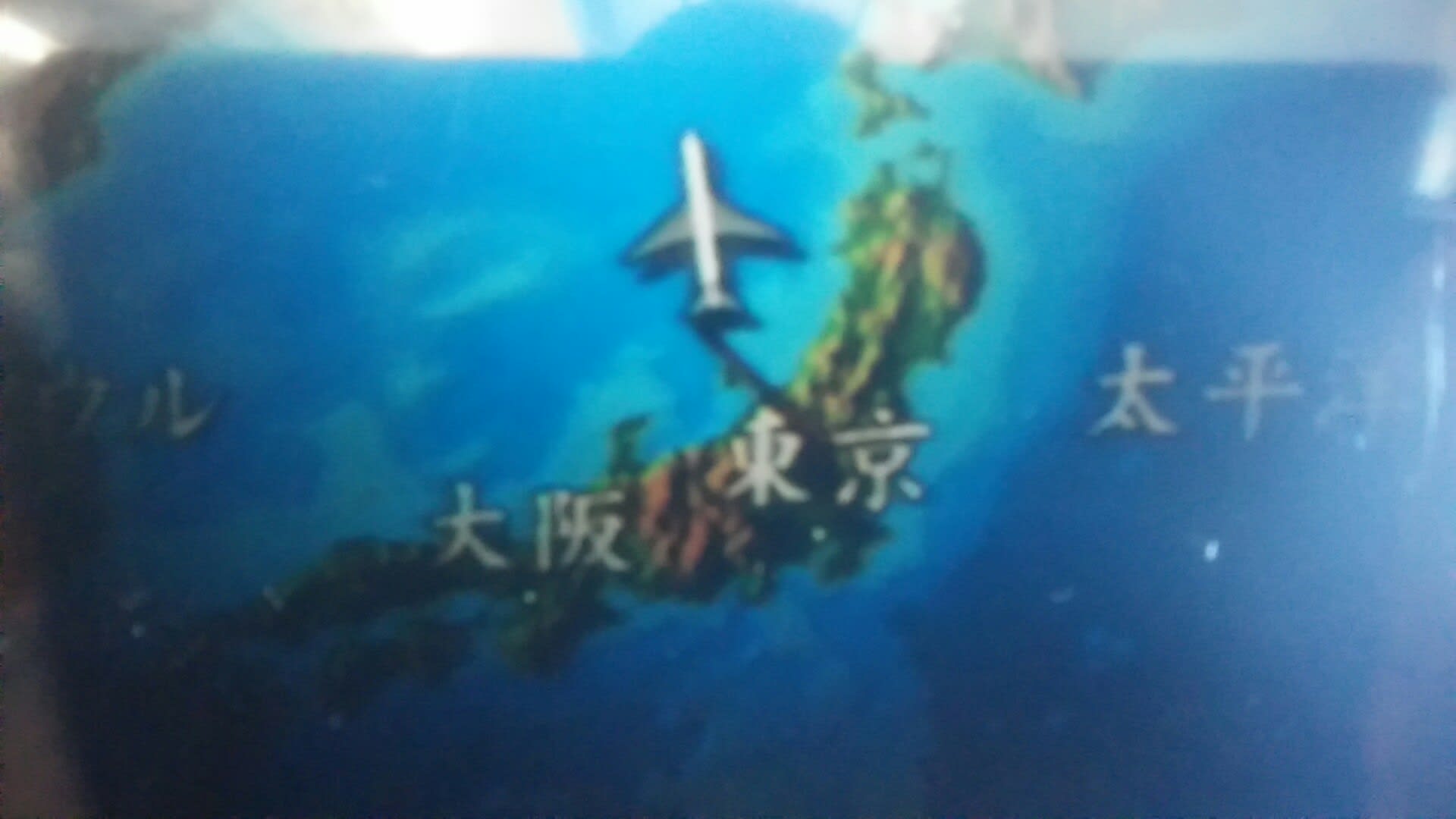












 慌てずに居れば、ホテル代の出費は無かったのかも•••
慌てずに居れば、ホテル代の出費は無かったのかも•••







