今日は車検の見積もりをしてもらいに、ディーラーまで行って来ました。
最近は、仕事とサッカーに行く時以外は使わないため、
半年で3000㎞しか乗っていないので、車の必要性も薄くなって来た。
もう18年乗っているこの車は、僕の自家用車の歴史の中で唯一、
新車ではないクルマです。
その前に新車で購入したCUBEを、最初の定期点検に出した際に、
ディーラーのミスで、納車時に立体駐車場の駐車位置を間違えて、
リフトが下りた際に天井が潰れてしまった事故があって、
さらに元々入っていた新車特約を入れ忘れるというミスが重なったために
保険も利かなかったため、代替車として走行距離がほぼ同じ程度の
試乗車を探させて、手を打ったという代物。
それだけに、この車になってから車自体に愛着が無くなった。
今回の見積額は車検整備代32万円、諸経費5万7千円で、トータル40万円弱。
車のロアリンクアームとショックアブソーバーが劣化していて交換を要するとの所見。
ロアアームとは、車の足回りを構成する骨組みのひとつで、
ブレーキやハブが組み付いているナックルや、サスペンションなどが接続される部品。

ロアアーム自体はメンバーと呼ばれるフレーム部分に取り付けられて、
路面からの衝撃をサスペンションへ伝えると同時に、
加減速時の前後方向の力やコーナリング中の左右方向の力を受け止める、
足回りの部品の中でも、特に強度が要求される重要部品です。
経年劣化によってロアアームブッシュにひび割れや亀裂が生じると交換が必要となる。
ブッシュにひび割れが発生するとロアアームがしっかりと保持されなくなるため、
車が勝手に曲がっていく
ステアリングが震える
ゴツゴツとした振動や異音が聞こえる
などの症状があらわれます。
最近、運転時にゴツゴツとした振動音が気になっていたので納得です。
という訳で、この内容ならこれくらいの値段になっても仕方がない。
さらに7年使って居るタイヤも細かいひび割れが見えているので、
これを新品に交換するとさらに9万円程度なので、車検時に50万円近くかかる。
この価格で新車と、今流行りのリースとを比較して出費を考えてみました。
新車は軽自動車を考えているので新車を購入すると180~220万程度。
リースの場合、5年契約で月に4万円弱なので、年額48万円程度。
2年で100万円弱、5年で約250万円ほどになります。
車検を頼むと、年額4万円の自動車税を払っても2年で60万円。
さらに2年後の車検で30万円かかっても、4年で100万円程度で済みます。
さらに2年後の車検で30万円かかっても、4年で100万円程度で済みます。
そう考えてみれば結論として、しっかりとした整備を行って車検を取った方が安い。
新車に興味はないし、古い車を乗り続けて恥ずかしい事もない。
お気に入りの横開きのリアハッチは、今や採用しているメーカーが無い。
新車に興味はないし、古い車を乗り続けて恥ずかしい事もない。
お気に入りの横開きのリアハッチは、今や採用しているメーカーが無い。
去年ボンネットを新品に交換したし、バッテリーも交換したばかり。
車検を取って、今後は少し手入れをしてやろうかなと思っています。






















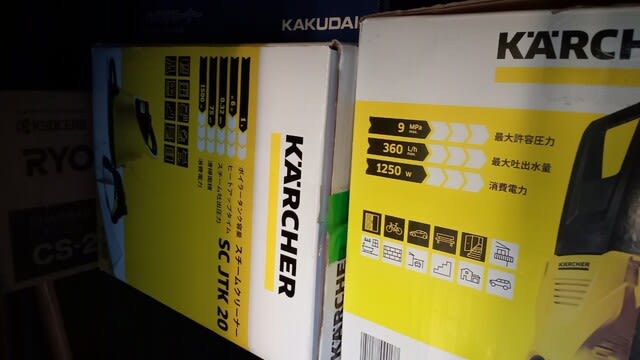





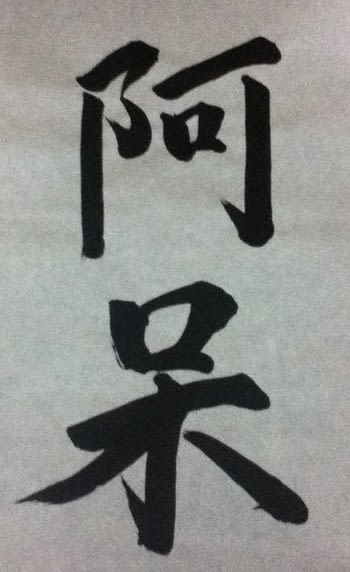





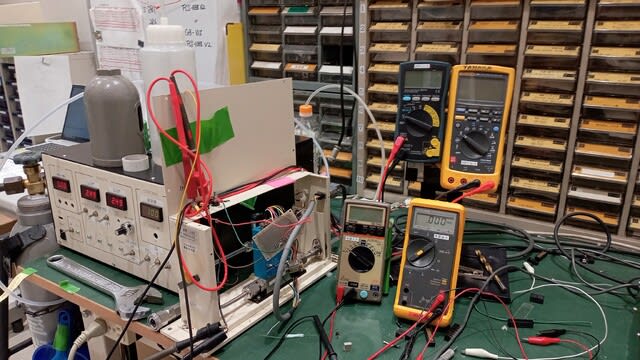




















 イメージ画像
イメージ画像


 鉄道弘済会(現kiosk)創業100年記念
鉄道弘済会(現kiosk)創業100年記念




