





 目指したのはここ、石塀小路
目指したのはここ、石塀小路
 | |||||||||
| 石塀小路から八坂の塔へ | |||||||||
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
表通りのような喧騒からは全くの別世界の小路を歩くと、好きな古都がここにあるように思う。
突き当たりに思わず目を見張った、庚申堂の境内の華やかな色彩が嬉しくて、お参りしてくる。
「欲が沢山ある」私はお猿さんを見るだけにした。
ここは初めてだったので、いつかまた「一つの欲」を我慢して、切なる願いをかなえてもらう時には訪れようかと・・・







 目指したのはここ、石塀小路
目指したのはここ、石塀小路
 | |||||||||
| 石塀小路から八坂の塔へ | |||||||||
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |



| ||||||||||||||||||






| ||||||||||||||||||||||||






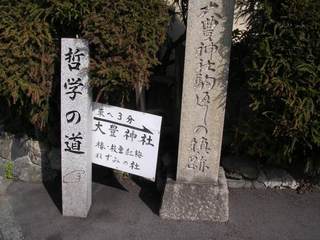



| ||||||||||||||||||

 千住~草加
千住~草加
 | |||||||||
| 明治・大正の元老山県有朋の別荘 無鄰庵 | |||||||||
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |



 日本橋~千住(今日から日光街道)
日本橋~千住(今日から日光街道)