
このお料理が並ぶ前、何よりのご馳走となったのは、開放的な座敷を通り抜ける風の涼しさである。久しぶりに会ったことでもあり、次々と話題が尽きない。

「先ずは冷たい梅ジュースを・・・」

遠くの山は金剛山。北から南に吹きぬける風が、軒の風鈴の短冊を遊ばせて、心地よい音色が絶えず部屋のバックグランドミュージックのように流れる。
同じ五條なのにここは全くクーラーの要らない自然の風の贅沢な世界である。




お母さんスタッフによる手作り料理は、地元の旬の野菜をふんだんに使っているので、お料理がテーブルに載るごとに、お料理の名前や、食材、調味料など丁寧に説明してくれるのに、肯きながら頂く。
自家農園の食材は勿論、調味料も自家製で、それらが食材とマッチしてどのお料理も美味しくて、これが心和むお料理と言えるものだ。

揚げ物も、お決まりの食材の使用などでなく、山菜も交えたような本当に旬の野菜なのが何より、野菜の味が生きてきているようで美味しい。このような感じの揚げ物を味わった記憶が、春浅い黒姫高原のホテルの夕食の、揚げ物の味を思い出す。

鮎の姿焼きのさっぱりした美味しさも久しぶりだった。

デザートその1で、次には席を変えて、お抹茶とゼリーを頂く。その写真はうっかりして撮り忘れてしまった。



お抹茶を頂いた部屋から見える内倉で、昔の農機具がこのレストランの、インテリアとして、この家の歴史をも語っているようだ。アットホーム的な温かさを感じるのは、こうした配慮からかもしれない。

この地湯塩の春夏秋冬を描いている大作の屏風だ。そばに行って読まなかったので内容は把握しなかったが、作家は知っている人であることをオーナーの話で分かった。広い座敷にマッチしているいい屏風だ。
ここでお食事の時間よりも長い時間を、オーナーとの話し合いで過ごした。何しろ涼しい座敷なので居心地がよく時間の経つのも忘れて、友人とともにとてもいい時間を過ごすことができた。案内してくれて全てお世話になったEさんには感謝・感謝である。
「今度は季節を変えてまた来たいね。」 そんな約束が実現するのは、梅の花の咲くころだろうか。

山を下る途中、車を停めてくれたところから谷を隔てた向こう側が、賀名生梅林の全景の見えるところだった。
今年の春 梅の季節にあの山を梅を楽しみながら、ぐるっと一回りして、かなりの時間をかけて歩いたものだった。今は緑の山だけれど、梅の季節は白と淡いピンクの朧な美しさに包まれていたのを、今は幻のように思う。




































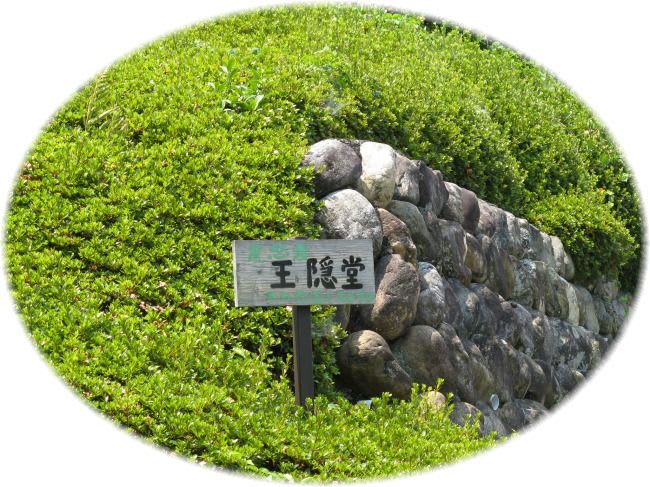








 9156
9156











