先日、日本海へカニを食べに行きました。
その民宿の箸袋がこれです
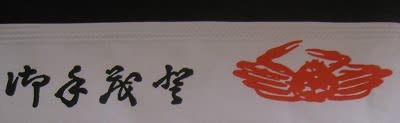
これが「御手茂登」で、「おてもと」と読むのは知っていました。
さて、民宿のタオルがこれです

「おてふき」だろうとは思いましたが、「御手富き」の「き」がわかりません。
やっと先日、「き」が「貴」であるとわかりました。「御手富貴」です。すっきりしました。
次は、三人で出掛けた京都の東福寺の塔頭光明院の掛け軸です。

三人とも「家和百事」まではわかりましたが、最後の一字がわかりません。
「朱」ではないし、「求」ではないし…。
やっと先日、「成」であることがわかりました。「家和百事成」です。なるほどね。すっきりしました。
次は字ではありませんが、私の理解を超えているのがこの絵です。
東福寺の東司(とうす)の中に掲げられていた絵なのですが、これは何をしている絵でしょう。
※ちなみに東司とは、トイレのことです。
東司で何をしているのでしょう。壺の中身は何でしょう。この湯気は何でしょう。


東司

東司の中を覗き込む人たち

中の様子

----------------------------------------------
最近知り得たこと…
法堂を「はっとう」と読むのを、先日京都の相国寺で知りました。
相国寺の法堂の天井には鳴き龍(直径10mくらいの天井板)が描かれていました。
東福寺の法堂の天井にも龍(約150畳の天井板)が描かれていました。
東司を「とうす」と読むのは、先日永平寺で学びましたので、東福寺のパンフレットの「東司」は正しく読めました。
出掛けると、刺激があって、一つ一つ知識が増えます。




















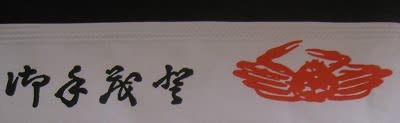





















 吽形の右足の親指のなんと力強いこと!!
吽形の右足の親指のなんと力強いこと!!






