潮干狩りを見学した後、室津へ向かいました。
http://www.kanko-mitsu-hyogo.jp/より引用
室津は港町として1300年の歴史があります。奈良時代に行基法師により5つの港が整備されました。そのうちの1つが「室(室津)」です。
室津は江戸時代に一番の栄華を迎えます。参勤交代で西国からの大名のほとんどが船で室津に到着し、ここから陸路江戸へ向かいました。 室津は海と陸の接点、宿場町として栄えたのです。
室津は、狭い道沿いにたくさんの家がぎっしりと建っていました。


魚を干しています

何が干してあるのでしょう?


★室津民俗館

もと豪商「魚屋」で、23の部屋、168枚の畳があります
八朔の雛祭り

室津では、3月3日ではなく、旧暦の8月1日に雛祭りをするそうです。
★室津海駅館
もと豪商「嶋屋」


2階の大きな畳の部屋で、潮の匂いを感じながらゆっくりと休憩しました。
海駅館では、朝鮮通信使饗応料理と参勤交代の御上御献立が食べられるようです。
次回は、朝鮮通信使饗応料理(3,000円)か御上御献立(1,500円)を食べてみたいものです。
★室津港

港には漁船がたくさん繋留されていました。
ちょうど漁から戻ってきた船があって、じっと見ていると、たくさんのカレイや小さな魚がおろされました。
★賀茂神社
大きな社殿です

紋章は二葉葵
賀茂神社の例祭小五月祭りも見学してみたいものです。
http://www.kanko-mitsu-hyogo.jp/page_fes/fes_1.htmlより引用
小五月祭り(室津)賀茂神社の例祭として春に開催されます。
同じ例祭の「夏越祭り」が男の祭りであるのに対して、「小五月祭り」は女の祭りです。
この祭りは平安後期に室津の長者の娘が、賀茂神社へ棹の歌を奉納したのがきっかけです。
今でも女の子はきれいな衣装を着て棹の歌を奉納します。「棹の歌」は兵庫県重要無形民俗文化財です。
★浄運寺
山門に鐘がありました

http://www.muro-shimaya.jp/より引用
奈良時代の高僧、行基は摂津と播磨の両国のなかで海上交通の良港として五つの港を定めたと言われます。いわゆる摂播五泊です。
東より、河尻(尼崎)、大輪田(兵庫)、魚住(明石) 、韓(的形)、室津の五泊です。
室津海駅館は、江戸末期から明治中頃まで「嶋屋」という屋号で廻船業で富をなした
豪商の建物です。
現存する建物は嶋屋の主、三木半四郎が18世紀中頃に建てたもので、佐藤氏が所有
していました。
1994年に御津町が買い上げ、2年間の修復工事を終え、 1997年に町立「室津海駅
館」として開館しました。
主屋は、町の指定文化財で、軒の低い切妻平入りの2階建てで、間口に格子をはめて
室津の町屋の特色を示しています。
海駅館は2階がほぼ完全な形で残っています。
「やかたぶねの間」 とよばれる表の間の曲がり状になった天井、前面窓にかかる腰掛
け縁と格子、豪奢な床や出書院を備えるお座敷など、一見の価値があります。
豪商の家としてはもう一軒「魚屋」(現、室津民俗館)があります。
魚屋の部屋数は23、箱階段や隠し階段、貴人専用の「御成門」など興味深い。
室津海駅館の展示は、江戸時代に海の宿駅として栄えた室津を知ってもらうために、廻船、参勤交代、江戸参付、朝鮮通信使の4つのテーマにしぼっています。
そのなかでひときわ目を引くのが朝鮮通信使饗応料理と参勤交代の御上御献立の復元模 型です。開館以来、来館者のなかには「実際に食べてみたい」という要望もあり、海 駅館でもなんとか、これらの料理を希望者に提供できないものか、と考えてきました。
幸いにもこのたび地元料理店の協力で実現のはこびとなりました。
(中略)
朝鮮通信使饗応料理 3,000円
御上御献立 1,500円
双方の料理とも海駅館で食べることができます。 博物館の展示は見るだけでなく、ふれる展示など 新しい試みがみられます。
食べる展示というのが今回の試みです。 ひとつの体験学習です。
皆様も、江戸時代の面影を残す海駅館で、ぜひ一 度大名・国賓気分を味わって
みてください。但し、料理は10月1日より予約できます。
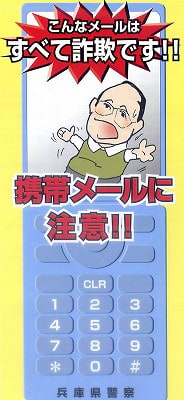


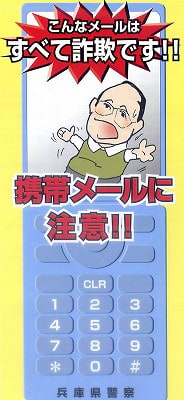




























 6個540円でした
6個540円でした










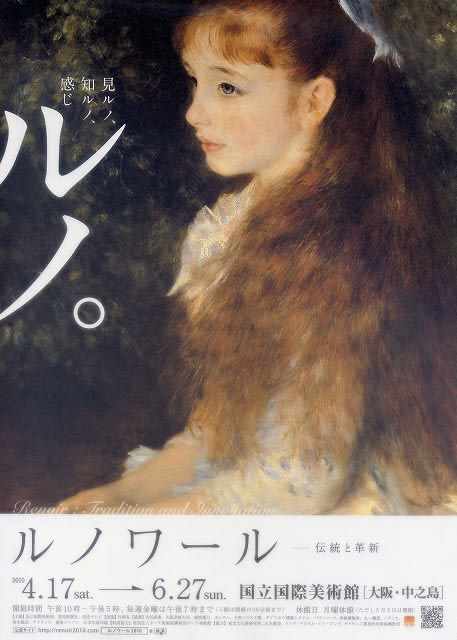



 (下記のHPより)
(下記のHPより) (下記のHPより)
(下記のHPより) (絵葉書より)
(絵葉書より) (絵葉書より)
(絵葉書より) (絵葉書より)
(絵葉書より) 







 もと豪商「魚屋」で、23の部屋、168枚の畳があります
もと豪商「魚屋」で、23の部屋、168枚の畳があります 



 紋章は二葉葵
紋章は二葉葵





 3つの小島、唐荷島
3つの小島、唐荷島 14時頃が干潮のようです
14時頃が干潮のようです

 遠くに小豆島が見えました
遠くに小豆島が見えました




















