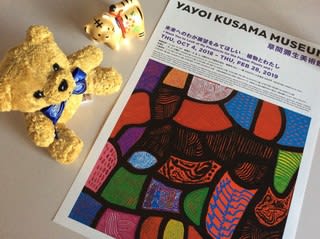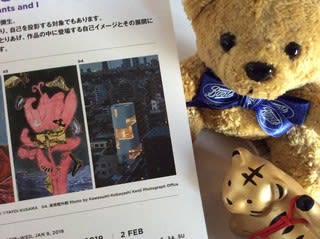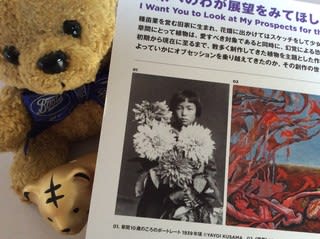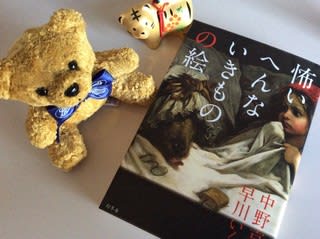「こんにちわッ、テディちゃでス!
……ふァ? すいかァ??」
「がるる!ぐるるがぅるるるる?」(←訳:虎です!ニセ物じゃないんだ?)
こんにちは、ネーさです。
スーパーマーケットの果物売場に並んでいたのは
……スイカ。
えっ? 西瓜が2月に?!?
2月に真っ赤な夏の果実が??
我が目を疑いながらの本日の読書タイムは、
さあ、こちらの新書を、どうぞ~♪

―― 姫君たちの明治維新 ――
著者は岩尾光代(いわお・みつよ)さん、2018年9月に発行されました。
それは150年ほど昔のこと、
サムライ制度が瓦解した日本に於いて、
“ひと”はどう変わったか――
著者・岩尾さんは、
新たな時代=明治に生き、暮らした女性たちの視点から、
《維新》という変革期を見詰め直します。
「えェ~とォ、けいおうゥ、なのでスゥ!」
「ぐるるるるがるる~!」(←訳:慶応4年の春だよ~!)
慶応4年。
西暦では、1968年。
当時は旧暦だったので、
現代の暦では季節は少しずれると、
岩尾さんは御本の第一章で書いておられますが、
3月13日には薩摩の西郷隆盛さんと
幕府代表の勝海舟さんが会談、
4月11日には幕府討伐軍が江戸城に入り、
ひとつの時代が終焉を迎えました。
その衝撃、その驚きたるや、いかばかりだったことか。
「もうゥ、びッくりィどころじゃないでス!」
「がるるるるぐぅるるるー!」(←訳:スイカの比じゃないよー!)
城は多くが焼失し、
領地も無くなってしまった……
一般市民もお殿さまたちも等しく混乱に陥った変革は、
お城の奥に暮らしていた姫君たちにも
変容を促します。
「おもてぶたいィにィ~」
「ぐるがるるるる!」(←訳:出てゆかないと!)
好むと好まざるとにかかわらず、
明治政府が推し進める西洋式社会に
お姫さまたちも合流せねばなりません。
岩尾さんは、
徳川家、
有栖川宮家、
前田家、
鍋島家
といった名家の女性たちが
どのような維新前・後を送ったか、
詳しく検証してゆきます。
「ううむゥ! いろいろォなのでスゥ~…」
「がるるぐるる~…」(←訳:幸福も不幸も~…)
維新前と比較して、
維新後の上流階級の女性たちの違いは、といえば、
“海外との結びつき”
でしょうか。
夫君が政治家であるなら、
大使や大臣のパートナーたる姫君たちは、
欧州へ、米国へ、同行するのが必然。
そして、海外に居住する姫君たちのもとへ、
友人知人が、親族が、行くこともある。
とりわけ、パリは姫君たちに大人気?
「いつだッてェ、じょせいィはァ~」
「ぐるるるるがるる!」(←訳:おフランス大好き!)
日本を離れた遠い異国で、
姫君たちは何を見たのか。
そして、身分は姫君であっても、
恵まれた生活を送ることが許されず、
日本に留まったまま、
苦難に苛まれる女性も、
また存在した――
御本の終章『戦火のかげで 落城の妻たち』は
溜め息なくしては読めません……。
「これがァ、れきしィ……!」
「がっるるぐるる……」(←訳:ずっしり来ます……)
維新の華々しい功績と、
もう一方の、現実。
歴史好きな活字マニアさんにおすすめの新書作品、
ぜひ、一読してみてくださいね♪
……ふァ? すいかァ??」
「がるる!ぐるるがぅるるるる?」(←訳:虎です!ニセ物じゃないんだ?)
こんにちは、ネーさです。
スーパーマーケットの果物売場に並んでいたのは
……スイカ。
えっ? 西瓜が2月に?!?
2月に真っ赤な夏の果実が??
我が目を疑いながらの本日の読書タイムは、
さあ、こちらの新書を、どうぞ~♪

―― 姫君たちの明治維新 ――
著者は岩尾光代(いわお・みつよ)さん、2018年9月に発行されました。
それは150年ほど昔のこと、
サムライ制度が瓦解した日本に於いて、
“ひと”はどう変わったか――
著者・岩尾さんは、
新たな時代=明治に生き、暮らした女性たちの視点から、
《維新》という変革期を見詰め直します。
「えェ~とォ、けいおうゥ、なのでスゥ!」
「ぐるるるるがるる~!」(←訳:慶応4年の春だよ~!)
慶応4年。
西暦では、1968年。
当時は旧暦だったので、
現代の暦では季節は少しずれると、
岩尾さんは御本の第一章で書いておられますが、
3月13日には薩摩の西郷隆盛さんと
幕府代表の勝海舟さんが会談、
4月11日には幕府討伐軍が江戸城に入り、
ひとつの時代が終焉を迎えました。
その衝撃、その驚きたるや、いかばかりだったことか。
「もうゥ、びッくりィどころじゃないでス!」
「がるるるるぐぅるるるー!」(←訳:スイカの比じゃないよー!)
城は多くが焼失し、
領地も無くなってしまった……
一般市民もお殿さまたちも等しく混乱に陥った変革は、
お城の奥に暮らしていた姫君たちにも
変容を促します。
「おもてぶたいィにィ~」
「ぐるがるるるる!」(←訳:出てゆかないと!)
好むと好まざるとにかかわらず、
明治政府が推し進める西洋式社会に
お姫さまたちも合流せねばなりません。
岩尾さんは、
徳川家、
有栖川宮家、
前田家、
鍋島家
といった名家の女性たちが
どのような維新前・後を送ったか、
詳しく検証してゆきます。
「ううむゥ! いろいろォなのでスゥ~…」
「がるるぐるる~…」(←訳:幸福も不幸も~…)
維新前と比較して、
維新後の上流階級の女性たちの違いは、といえば、
“海外との結びつき”
でしょうか。
夫君が政治家であるなら、
大使や大臣のパートナーたる姫君たちは、
欧州へ、米国へ、同行するのが必然。
そして、海外に居住する姫君たちのもとへ、
友人知人が、親族が、行くこともある。
とりわけ、パリは姫君たちに大人気?
「いつだッてェ、じょせいィはァ~」
「ぐるるるるがるる!」(←訳:おフランス大好き!)
日本を離れた遠い異国で、
姫君たちは何を見たのか。
そして、身分は姫君であっても、
恵まれた生活を送ることが許されず、
日本に留まったまま、
苦難に苛まれる女性も、
また存在した――
御本の終章『戦火のかげで 落城の妻たち』は
溜め息なくしては読めません……。
「これがァ、れきしィ……!」
「がっるるぐるる……」(←訳:ずっしり来ます……)
維新の華々しい功績と、
もう一方の、現実。
歴史好きな活字マニアさんにおすすめの新書作品、
ぜひ、一読してみてくださいね♪