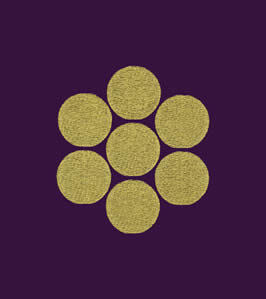◇リアリズムの宿(2004年 日本)
なるほど、リアリズムかもしれない。
なまなましい映像と台詞回しは、なにやら迫真性すら感じる。
ただまあ、いつの時代なのかちょっとぼんやりした感じがするのは、
つげ義春の「旅」物が発表されたのが、昭和40年代だからだろう。
もちろん、冒頭、携帯電話が一般に普及してるわけだから、
昭和なわけはないんだけどね。
もっとも、
まだ大学生臭の抜け切らない脚本家と映画監督の青臭い会話は、
昭和50~60年代の大学生の自主製作映画的な世界観があって、
ぼくとしてはえもいわれぬ好感を抱いた。
ただ、
性格付けも、ふたりの間をただよう微妙な距離感は、
要するに間の取り方が見えてこない居心地の悪さというやつで、
なるほど、リアルだな~とは感じたものの、
山間の宿で金を巻き上げられるくだりや、
あまりにも薄汚くかつ切な過ぎる生活臭たっぷりの民宿のくだりになってくると、
どうにも生理的なリアルさはあるものの、設定にリアルを感じなくなり、
つげ義春という作家の思考が色濃く感じられてくる。
それはそれでいいんだけども、
つげ義春の持っているリアルでありながら決してリアルでない世界は、
こうして実際の人間の演じるドキュメンタリー調の映像作品になってみると、
妙にすんなり受け入れられちゃうような気もするからふしぎだ。
それが、山下敦弘の演出力や、向井康介の脚本力かもしれないし、
長塚圭史と山本浩司の妙にリアルな演技によるものなのかもしれない。
すげーなこれはと感じたのは、
尾野真千子の登場するカットで、
おもいきり引いた逆光気味の砂丘の波打ち際で、
パンティ一枚の彼女が手前からフレームインしてくるんだけど、
半裸という衝撃的な出会いが打ち消されてしまうくらい、
砂と波と光の凄まじさが伝わってきてた。
尾野真千子が謎の女であればあるほど、
彼女を中心にしてふたりの自主製作映画人の過去や現実が見えてきて、
それはたとえば、
童貞であったり同棲してたのが別れたとかいう事実だったりするんだけど、
問題の謎の女については謎のまま突然現れ、やがて突然蒸発する。
次の登場が、
これまた現地の女子高生という突飛な結末に飛ばされるわけだけど、
こういう衝撃的な出会いと別れと再会とがリアリズムであるといえば、いえる。
いや、事実は奇なりであるとおもえば、そういえるかもしれない。
もちろん、タイトルにあるのは「宿」であって「旅」ではないので、
もうなんだか眼をそむけて鼻をつまみ、爪先だけで物に触りたくなるような、
生理的嫌悪感がたまらずに迫ってくる森田屋だけがリアルであればいいわけで、
映画全体に現実臭があるのかないのかということについては、
ぼくらはそれぞれが味わえばいいだけの話なんだけどね。