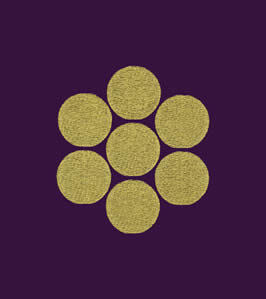☆ハンナ・アーレント(2012年 ドイツ、ルクセンブルグ、フランス 114分)
原題 Hannah Arendt
staff 監督/マルガレーテ・フォン・トロッタ
脚本/マルガレーテ・フォン・トロッタ、パメラ・カッツ
撮影/カロリーヌ・シャンプティエ 美術/フォルカー・シェイファ
衣装/フラウケ・フィルル 音楽/アンドレ・マーゲンターラー
cast バルバラ・スコヴァ アクセル・ミルベルク ミヒャエル・デーゲン ユリア・イェンチ
☆1960年5月11日、アドルフ・アイヒマン拘束
映画の中で問題になっているのは、
イスラエルにおけるアイヒマンの裁判を膨張したハンナが、
1963年に雑誌『ニューヨーカー』に連載した論文で、
『イエルサレムのアイヒマン・悪の陳腐さについての報告』という裁判記録だ。
ユダヤ人でシオニズムにも造詣の深いはずのハンナが、
アイヒマンは徹底して陳腐な取るに足らない小役人にすぎないと主張し、
さらに、
国際法上における「平和に対する罪」には明確な定義はなく、
ソ連のカチンの森の事件や、
アメリカの広島・長崎への原爆投下が裁かれないのはおかしいと主張したことで、
こういうあたりを日本人のぼくが観てると、
なんら、ハンナの主張はおかしくないようにおもうんだけど、
やっぱり、ユダヤ人ことにシオニストたちからすれば大変なことで、
当時、いかに物議をかもしだしたかがよくわかる。
まあ、映画の中でも触れられてるんだけど、
ハンナは、マールブルク大学に在学していたとき、
教えを受けていたマルティン・ハイデッガーと不倫関係にあったみたいで、
自身でも「初めての情事」とかいってるみたいなものだから、
シオニストたちからすれば、こう勘繰りたくなったんだろう。
ナチスに関係していた人物との関係がその主張に繋がっているのか、と。
人の心はよくわからないし、
忘れ難い関係をもった異性を忘れるはずはないんだけど、
この勘ぐりはおおやけのもとでするべきではないし、苦し紛れにすら見える。
ハンナの主張はあくまでも客観的でありながら、たしかに主観的でもあり、
これはこれでひとつのアイヒマンに対する意見として受け止めればいいはずなのに、
なかなかそうはいかないのが人種や宗教、さらには民族浄化のからんだ問題だ。
こうした小難しい問題を前面に掲げながらも、
ユダヤ人として生きてきた女性が自身の見解を勇気をもって主張することの強さ、
というものについて、この映画は硬質に描いてる。
ハンナの日常は、朝が重要だったようで、
煙草と珈琲を大量に摂取しながら瞑想にふけるのが日課だったようで、
これについても映画は冒頭とラストできちんと取り上げてる。
入念な調査と準備のもとに撮影されたことがよくわかるし、
人物造形については、まじ、脱帽に値するんじゃないかと。