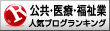4人姉妹がいてその下の男の子、小さいときからてんかんがあって両親も心配し末っ子で男の子ということもあり家族全員からかわいがられて成長した男性は就労の経験もなく酒を飲んでいる毎日をすごし、姉妹はすべて結婚をして家を出た。そのうち父親が亡くなり母親は老健で療養中、生活能力のないその男性はてんかん、腎臓機能低下、高血圧と複数の疾病をもち第2号被保険者の要介護認定3。
入院環境になじまず入院をいやがってむりやり退院、で介護支援。
服薬管理・水分摂取ができないというよりしない、自分で判断をしない、生活能力がない、気力、体力が続かずという状態でのケアプランを実施、内容は限度額上限まで使ってサービスを組み込み何とか生活を維持するがポータブルトイレまでにたどり着けず夜間の便失禁もたびたび、という状態を1ヶ月継続、何とかヘルパーで生活を安定させ、3ヶ月目には10以上も飲んでいた薬を医師が薬を減らした結果、本人の身体が回復、あいかわらず生活能力はないが失禁はなし、話は聞ける、意見を述べるようになった。
これは当社の所長が担当した事例ですが、この経過を話すのが目的ではなく、こうした成果を獲得した原因はなにかが重要です。
ケアマネジャーはこの成果で満足しているがこうした成果を獲得した要因が分かれなければケアマネジメントの確立につながらない。
改善の直接の原因は薬剤の減少だろうが処方箋を書いているのは1人の医師だけで当然重複のリスクは承知、その上で10以上の服薬が少なくするという処方箋になった原因が重要で、なぜ服薬が変化したのか、それが生活の安定から本人の心身の安定につながり、薬に頼らないまでに回復したのかどうかの確認ができなければならない。
この話は単に成功事例という自慢話で終わらせることなく、原因追及があって始めてケアマネジメントが完成するということを認識しなければならない。
入院環境になじまず入院をいやがってむりやり退院、で介護支援。
服薬管理・水分摂取ができないというよりしない、自分で判断をしない、生活能力がない、気力、体力が続かずという状態でのケアプランを実施、内容は限度額上限まで使ってサービスを組み込み何とか生活を維持するがポータブルトイレまでにたどり着けず夜間の便失禁もたびたび、という状態を1ヶ月継続、何とかヘルパーで生活を安定させ、3ヶ月目には10以上も飲んでいた薬を医師が薬を減らした結果、本人の身体が回復、あいかわらず生活能力はないが失禁はなし、話は聞ける、意見を述べるようになった。
これは当社の所長が担当した事例ですが、この経過を話すのが目的ではなく、こうした成果を獲得した原因はなにかが重要です。
ケアマネジャーはこの成果で満足しているがこうした成果を獲得した要因が分かれなければケアマネジメントの確立につながらない。
改善の直接の原因は薬剤の減少だろうが処方箋を書いているのは1人の医師だけで当然重複のリスクは承知、その上で10以上の服薬が少なくするという処方箋になった原因が重要で、なぜ服薬が変化したのか、それが生活の安定から本人の心身の安定につながり、薬に頼らないまでに回復したのかどうかの確認ができなければならない。
この話は単に成功事例という自慢話で終わらせることなく、原因追及があって始めてケアマネジメントが完成するということを認識しなければならない。