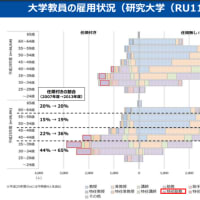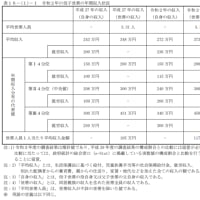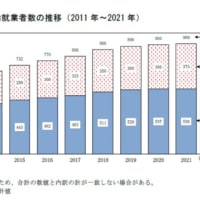このところ毎日のように、報道されている中国産食品の問題。
今日は、学校給食に予定されていた「きくらげ」から、農薬が検出されている。
スーパーに行くと、日本の食材が様々な国からやってきていることが良く分かる。
鮮魚などに関して言えば、近海モノを探すのが難しいときもある。
これでも、私が住んでいる名古屋は海産物の産地が近いだけではなく、畜産も盛んな地域で、当然のことながら野菜なども比較的地元産が手に入りやすい地域なのだ。
それでも、スーパーに行くといわゆる「地物」はあまりお目にかかれない。
特に、大型スーパーで「地物」は少ないような気がする時がある。
それを補っているのが、海外からの輸入食材だ。
その筆頭が、中国だ。
確かに、中国産と地元産の食材は、相当の値段差がある。
食材によって、その差は1.5倍~2倍以上はあるだろう。
その中で、今話題というか問題になっているのは「うなぎ」だ。
中国産うなぎから、禁止されている薬剤が検出された上に、中国産蒲焼の稚魚・ヨーロッパうなぎ稚魚の減少に伴い、規制されることになったからだ。
これで一番の打撃を受けるのは、コンビニなどで販売されている「お弁当」だろう。
その対策に今から頭を痛めている、コンビニチェーンもあるかも知れない。
そこで、目を向けたいのは「静岡(浜名湖)産」以外の、国内産うなぎだ。
イオングループなどは、鹿児島産うなぎを販売しているし、実際「日本養鰻漁業協同組合」の統計によると、生産量では鹿児島・愛知・宮崎などが目に付く。
昨今の「食のブランド化」で、食に対するこだわりを持つ人が多くなってきているが、反面日本の食卓は、万国旗のような状態だということを考えれば、「ブランド」よりも優先させるモノがあるのではないだろうか?
確かに中国産に比べれば、鹿児島産うなぎなどは割高感があるかも知れない。
だが「静岡(浜名湖)産」うなぎに比べれば、割安感がもてるのではないだろうか?
そして、今私たちが考えなくてはいけないのは、「自給率40%」という寂しい日本の農水行政なのでは?
今日は、学校給食に予定されていた「きくらげ」から、農薬が検出されている。
スーパーに行くと、日本の食材が様々な国からやってきていることが良く分かる。
鮮魚などに関して言えば、近海モノを探すのが難しいときもある。
これでも、私が住んでいる名古屋は海産物の産地が近いだけではなく、畜産も盛んな地域で、当然のことながら野菜なども比較的地元産が手に入りやすい地域なのだ。
それでも、スーパーに行くといわゆる「地物」はあまりお目にかかれない。
特に、大型スーパーで「地物」は少ないような気がする時がある。
それを補っているのが、海外からの輸入食材だ。
その筆頭が、中国だ。
確かに、中国産と地元産の食材は、相当の値段差がある。
食材によって、その差は1.5倍~2倍以上はあるだろう。
その中で、今話題というか問題になっているのは「うなぎ」だ。
中国産うなぎから、禁止されている薬剤が検出された上に、中国産蒲焼の稚魚・ヨーロッパうなぎ稚魚の減少に伴い、規制されることになったからだ。
これで一番の打撃を受けるのは、コンビニなどで販売されている「お弁当」だろう。
その対策に今から頭を痛めている、コンビニチェーンもあるかも知れない。
そこで、目を向けたいのは「静岡(浜名湖)産」以外の、国内産うなぎだ。
イオングループなどは、鹿児島産うなぎを販売しているし、実際「日本養鰻漁業協同組合」の統計によると、生産量では鹿児島・愛知・宮崎などが目に付く。
昨今の「食のブランド化」で、食に対するこだわりを持つ人が多くなってきているが、反面日本の食卓は、万国旗のような状態だということを考えれば、「ブランド」よりも優先させるモノがあるのではないだろうか?
確かに中国産に比べれば、鹿児島産うなぎなどは割高感があるかも知れない。
だが「静岡(浜名湖)産」うなぎに比べれば、割安感がもてるのではないだろうか?
そして、今私たちが考えなくてはいけないのは、「自給率40%」という寂しい日本の農水行政なのでは?