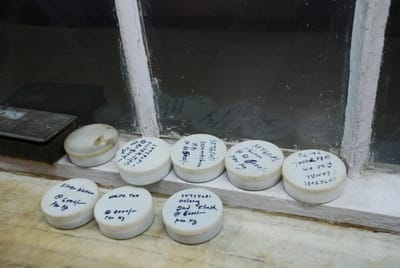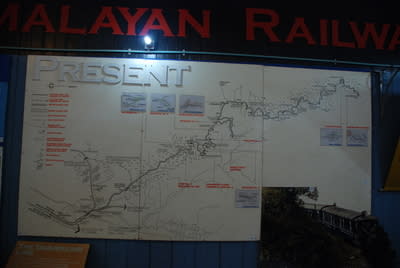紅茶工場の次は、ヒマラヤ動物園に行ってみた。
インドには、200以上の動物園があるが、この動物園が一番人気があるという。我田引水のような気もするが、確かにユニークな動物園だった。

一番ユニークなのは、動物園の中に、ヒマラヤ登山学院 (Himalayan Moutaineering Institute "HMI" ) があることだ。
この学校は、登山家を育てるための学校で、技術の程度によって、さまざまなコースがある。

この学校の初代校長は、Tenzing Norgay さん。ヒラリー卿とともに、1953年5月29日に、エベレスト登山に成功した。このモニュメントによると、1986年に亡くなるまで、当学院のアドバイザーを務めたとのこと。

登山学院内にあるエベレスト博物館の前には、テンジンさんのお墓がある。
博物館は、登山家の紹介、世界の有名な山の紹介、登山の際に使われた装備など、素人にもわかりやすいような展示になっている。植村さんの紹介もあった。女性で初のエベレスト登山を果たした田部井淳子さんのサイン入り写真も展示されていた。

話を動物園に戻そう。この地域特有の動物を、飼育・公開している。これは、雪豹だったと思うが、美しい。ロシアで捕獲されたものというが、インドではもう絶滅したのか。

これは、普通の豹。まだ、ダージリン近辺でも見られるという。

これは、雲豹(ウンピョウ)。美しい。これも絶滅危惧種か?

たぶんベンガル虎。これも確か絶滅危惧種。ベンガル州で見るベンガル虎。感慨深い。

これは、チベット狼。これもたいへん珍しいらしい。

これは、ヒマラヤで見られる熊。骨付き肉の餌付けでご満悦。カラオケのマイクを離さないオヤジみたいだ。
やや雨模様で、ゆっくり見る雰囲気ではなかったが、現地で見る現地の動物達ということで、面白かった。特に、絶滅危惧種に対しては、格別の配慮が必要だ。トキみたいにしたくない。