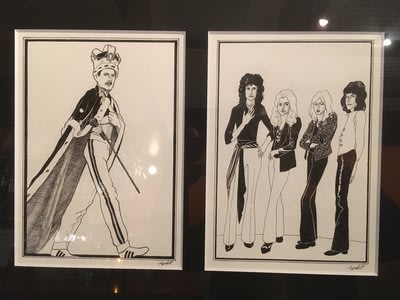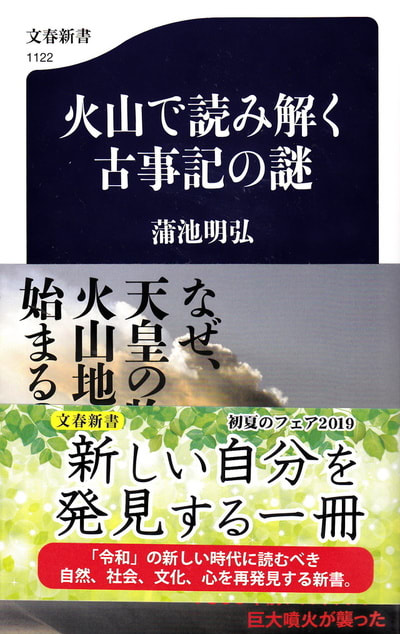ビートルズの歴史を語る時に、避けられないのが、レコーディング技術の進歩である。
もちろんその後、デジタル化の波が押し寄せるのだが、アナログの時代でも、大きな進歩があり、特に、ビートルズが活躍していた時代、大きな進展があった。
それを、各スタジオが競っていたのである。
もちろんEMIスタジオもその最先端を目指していたのだが、必ずしも、常に一番だったわけでなない。
本書は、46スタジオの歴史を読み解き、その時の音楽シーン、各スタジオの特色を浮き彫りにする。
導入されている機器のみならず、それをどう使って斬新な音を作り出すか。
当時のミュージシャンたちが競いあった。
そして、各スタジオがそれに答えようとした。
残されている音源から、リミックスをする技術は、格段に進歩したが、そもそもの音源がどのように作られたかは、記録が残されている訳でもなく、推測によるしかない。
それを、実現しようとしたのが本書であり、本のタイトルが示すように、それだけの力作だ。
もちろんアビーロードスタジオが一番なのだが、最近よく知られてきたように、他のスタジオも新規のシステム導入により、アビーロードスタジオを凌駕するハードを有するスタジオも出てきていた。
その辺を、ING感覚で、浮き彫りにしてくれる。
スタジオは、科学実験室か?