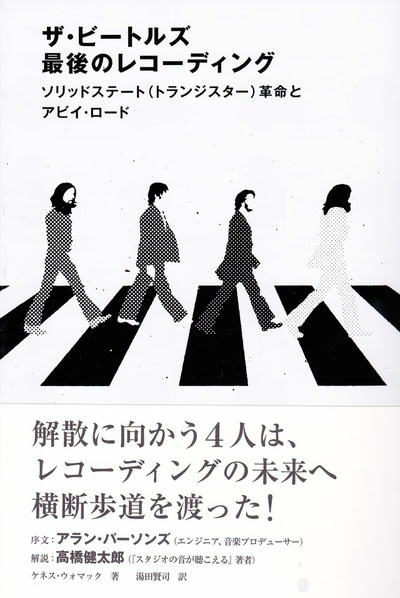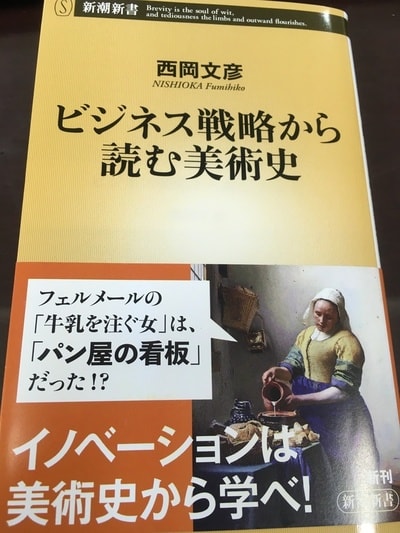本書は、本屋で見つけた。
古代史講義シリーズの第4弾。
その他のちくま新書もかなり読んで来たが、正攻法で面白い。
本書もしっかりした内容だった。
意外だったのは、古代史といいつつ源氏、平氏、奥州藤原氏など、半分中世の氏族も対象にしている。
読んでみると、これらの武士の世界の氏族も、天皇家、貴族から、発祥していることが、わかる。
例えば、奥州藤原氏の実質始祖の清衡も、京の都で、ノウハウを身につけて、奥州に都を開いた。
平氏の平も、平安京の平から来ている。
その他、あまり触れられることのない橘氏、佐伯氏、紀氏なども取り上げられていて、面白い。
最近わかって来たことも取り上げられている。
例えば、論語や千字文が、漢字の勉強の題材になっていたことは知られていたが、漢字を伝えたと言われる王仁が歌った(と伝わる)難波津の詩も、漢字の練習に使われていたことが、わかって来た。
この話は、渡来系氏族である東漢氏、西文氏の章で出てくる。
各章の書き手が、それぞれの専門家であり、コンパクトながら、ディープな内容になっている。
古代史に興味のある方に、広くお勧め出来る。
次作は、どの切り口で来るか?