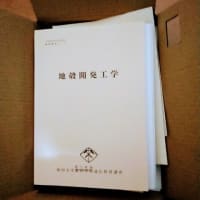| 地震と噴火の日本史 (岩波新書 新赤版 (798)) |
| クリエーター情報なし | |
| 岩波書店 |
ついこの間、御嶽山の噴火が大惨事を引き起こしたが、我が国には、いたるところに火山が存在する。少し前に、富士山が世界遺産となったが、あれが活火山だということをご存じだろうか。昔学校では、富士山は休火山だと習った。しかし、現在では、休火山とか死火山とかいう区分はなくなっており、活火山かどうかという分類があるだけだ。富士山についても、竹取物語が書かれた時代には、その記述から噴煙を上げていたことが分かるし、近くでは、1707年に、宝永大噴火を起こしている。富士だけではない。御嶽山、浅間山、有珠山など日本は火山噴火の歴史には事欠かない。
そしてもうひとつ地震。阪神大震災や東日本大震災を例にとるまでもなく、日本は地震の多い国だ。日本書紀にも地震の記録が載っている。416年(允恭天皇5)のことだ、当時は地震のことを「なゐふる」と呼んだらしい。ただしどの程度の規模だったのかは分からず、最初の巨大地震の記録は684(天武天皇13)だという。
これらの歴史に残る地震と噴火の記録をトピック的に紹介したのが、本書「地震と噴火の日本史」(伊藤和明:岩波新書)である。
我が国に地震や噴火の多い理由は明らかである。ユーラシアプレートや北米プレートの境界付近に位置しているため、太平洋プレートやフィリピン海プレートがその下に潜りこむ際に、地殻にひずみが貯まっていき、それが地震や噴火を引き起こしているのだ。
地震や噴火が恐ろしいのは、それ自体の破壊力もさることながら、これによって発生する津波や土石流、火砕流といった続いて起こる現象も甚大な被害をもたらすからである。本書には、そのような事例が多く収められている。
しかし、いたずらに地震や津波を恐れていてもしかたがない。この日本で、私たちは生きていかなければならないのだから。大切なのは過去に学ぶことだ。そして、まさかの時に被害を少しでも減らすために備えることだ。しかい、時代とともに災害の記憶は風化していき、忘れ去られてしまう。津波よけのために作られた堤防の海側にも住宅が広がっているような例もあるというから、過去に学ぶと言うのは、人間にとってはなかなか難しいことなのだろうか。
著者は理学系の人だからか、本書では、具体的にどのような方策をとったらよいかということには、殆ど触れられていない。これも理解できないことはない。過去に学び、それをどう生かすかは、政治と工学の問題ということなのだろうから。
☆☆☆☆
※本記事は、姉妹ブログと同時掲載です。