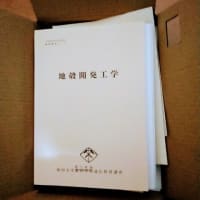| ぼくの翻訳人生 (中公新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 中央公論新社 |
・工藤幸雄
本書はかなり昔に買ったものだ。これまでずっと本棚の肥しになっていたのだが、やっと読むことができた。調べてみると、著者は2008年既に鬼籍に入られているが、買ったのはおそらくそれより前だったと思う。本書は著者の自分記ともいえる内容だろう。
著者は、4浪して旧制一高に入った苦労人だ。当時は旧制高校に入るのが一番難しく、それを突破すれば大体が帝大に進学できたという話はよく聞く。東大の仏文科を卒業しているのだが、なぜか翻訳書はポーランド語からのものがほとんどである。もちろん今の東大よりは段違いに難しい。
本書には、著者が大先輩の川口篤さんから聞いたという景気のいい話が紹介されている。
<「学生時代に対して苦労もなしに訳した岩波文庫の一冊の印税で、すぐさま家が買えて、いまもその家に住んでいるのだから。あれは、アンドレ・ジッドの『狭き門』でね」(pⅱ)>
ここでポイントは二つ。一つは学生時代ということ。昔は大学生は本当にエリートだった。今のような学士様ハイパーインフレ時代ではない。学士様の価値は、今では考えられないくらいに高かったのだ。
例えば琵琶湖疎水の設計も、田辺朔郎の工部大学校(今の東大)の卒業論文だった。今よりずっと大学生というのはエリートだった時代だ。だから学生が翻訳をやっても少しもおかしくないのである。今はせいぜい下訳に使われるくらいのものか。もうひとつは家が一軒買えるくらいの印税が一つの翻訳作品から入ったということ。現在のような出版不況の時代ではありえないだろう。大学生が本を読まないと嘆かれるような時代ではないのだ。
著者の受験時代は戦時中で、野球なんかで横文字が日本語に言い換えられたことは有名だ。しかし反骨心旺盛な著者は、電車の中で敵性言語と言われていた英語の原書を読んでいたらしい。別に乗客からなじられることはなかったというが、おそらく軍部と一般の人との思いに乖離があったのだろうか。もしかすると、他の人は英語もドイツ語も区別できなかったのかもしれない。何しろ横文字を理解できただけでかなりのエリートだった時代である。
著者はあまり早いうちから外国語を学ぶことには賛成ではないようだ。次のような一文がある。実は小学校の英語教育は1886年(明治19)に廃止されるまで行われていたらしい。それから一世紀以上たって小学校でまた英語を教えるようになるのだから、いったい我が国の教育行政はどうなんだろうと思ってしまう。
<「ちいちいぱっぱ」がしっかり身につかない幼児に、どの外国語を押し付けても無駄である。>(p88)
また、著者は私と同じように、単なる外国語を「語学」というのは嫌いのようである。次のように言っている。
<語学ー正直な話、この「語学」という言い方が好きになれない。語学者を目指すことなく、外国語習得などは手段のひとつと考える筆者にとって、外国語の勉強がどうしても「学」とは思えないからだ。>(p91)
なんだかとても親近感の湧く主張が多く、ポーランド語にそれほど関心がなくとも色々と参考になるようなことが多いのではないのかと思う。
☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。