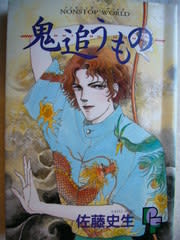「鬼追うもの」 小学館 PFコミックス 1995年7月20日 初版
つるさんにお借りしています。
収録作および初出
「鬼追うもの」 プチフラワー 1994年7月号
「神遣い (かみやらい)PART 1」 プチフラワー 1995年1月号
「神遣い (かみやらい)PART 2」 プチフラワー 1995年3月号
「神遣い (かみやらい)PART 3」 プチフラワー 1995年5月号
舞台は 大崩壊 が起きて旧世界が崩壊してしまった地球。人の住んでいる宇宙ステーションもあるらしいので、未来の話でしょう。
邪気を締め出した 「聖域」 であるはずの ヒモロギ府 に鬼が出没し、府外の都市ギルドから鬼追いの特殊技能者である 朱楽 (あけら) が呼ばれた。朱楽 は府のぐるりを囲む 羅城 (らじょう) の警備隊の隊長である 篁(たかむら) に出会い…
とあらすじを試みようとしたが、いつものように 史生さん の作った世界を説明するだけで相当文字数がかかる上、いくら説明してもなーんか違った話になりそうなので、 この世界のしくみとストーリー を説明するのはやめたやめた~。
史生さん の本の中では比較的新しくてまだ手に入りそうだし。(セブンアンドワイでは、入荷次第メールでお知らせになってる)
それじゃ作品の紹介にならないじゃん、と自分でも思うが、史生さん の宗教観が以前から気になっていたので、そこら辺を少し。
というのも、この作品には古代日本人の神に対する宗教観と言ったものが表されているような。
一応コミックス一冊がすべて続いている連作になっていますが、「鬼追うもの」 は平安時代の信仰世界が基盤になっているようです。。鬼を追い払う「追儺 ついな」の儀式である鏑矢を放ったり、桃の木で作った弓や杖を持ち、祈祷をしていたりするので、そうじゃないかな~と。
これは実は別名を 「鬼やらい」 と言って、見事に次の3作に題名が繋がっているのです。3作の題名は 「神遣い」 ですが、神と鬼とは古代日本では同じものなんですよ。これは後で話しましょう。
作者も表紙見返しに
鬼を追いかけたら、平安時代に行き着いてしまった云々・・・
と書いているが、いえそれどころか、史生さん の興味は 記紀 (古事記・日本書紀) まで行ってるでしょ !
「神遣い」 3作はもっと前の大和朝廷以前の古代日本の信仰世界が基盤になっているように思えます。前者はこの世界の中でも特に文化的進歩的 (とされている) 首都の中でのお話、後者3作はいわゆる田舎の蛮地で起こる話、という区別もあるのかも知れません。
全部はよく分からないんですが、地名・人名などの名前のひとつひとつが古事記や日本書紀から出されているようで、なにやらいわくありげです。朱楽 がおへそで飼っている 式神 のライコウのエサの土蜘蛛も記紀に出てきますよ。
どれだけの資料を読んでこれらを描きあげたものか もともと歴史がお好きなんでしょうが、好きで読むだけと、頭の中で再構築してこんなストーリーを作るのとは大違い、ですからね~
もともと歴史がお好きなんでしょうが、好きで読むだけと、頭の中で再構築してこんなストーリーを作るのとは大違い、ですからね~
古来、日本人は 八百万の神 やおよろずのかみ と言って、山や海の自然物、動植物全てにも神が宿ると考えて敬い祭ってきましたが、それはキリスト教のように 「我をお守りください」 という考えでなくて、 「我らに祟らないで下さい」 という考え方で、私はそういう意味じゃ西洋の神様と日本の土着の神様は全然違うもの、神様 というひとつの文字を使うのは意味が違うんじゃないかと思っているのです。
そこら辺はもう大学の偉い先生方がいろいろ書いてらっしゃるでしょうから、私ごときが言うことじゃないでしょうが、とにかくここでは、昔々、日本では神も鬼も人間にとっては祭っておいてお祈りして、どうか祟らないでね、という対象だったということが分かれば、「神遣い」 の題名の意味が分かると思うのです。
最後の方、一言主 (ヒトコトヌシ) と古主 (フルヌシ) が出てきましたね。ヒトコトヌシ というのは、古事記によると 一事主命 と書かれていて、太古より大和地方、葛城山に住んでいる神のこと。
第21代の天皇である雄略天皇が葛城山で狩りをした折、自分そっくりのヒトコトヌシに出会って先に名を名乗れと言われ、神とわかって一緒に楽しく狩りをした、というくだりがあります。
自分そっくりという逸話の通り、ヒトコトヌシはやまびこやこだまが神格化されたものであるといわれています。まだまだ神話の世界のお話ですね。
一方、「続日本紀」 には雄略天皇が無礼な葛城の神を土佐へ流刑にしたと記されており、高知市には移されたヒトコトヌシ神を祭る土佐神社が今もあるそうです。このことは雄略が即位に際し、大和の有力な土豪であった 葛城氏 を滅ぼした史実を伝えているのでしょう。
古事記・日本書紀その他古代や江戸時代のものまで、勝者の書いた歴史書の中にもちらちらと先住民のことが出ているし、真実が隠されているので深読みしている解説書を読むと、大変面白いのです。私の頭の中でもうごっちゃになっていて、出典がどれか分からなくなってますが。
大和地方、三輪山の土地神であるオオモノヌシの娘 (実は先住民の土豪の娘) と神武天皇の結婚譚とかはまさに土地のものと姻戚関係を結ばなければ支配が容易に出来なかっただろう、とか分かるわけです。
日本書紀には同じオオモノヌシとヤマトトトビモモソヒメのミコトとの結婚とちょっと恥ずかしい姫の死因の話 → 箸墓古墳の中の真ん中より少し下にあり が載ってますし。記紀って旧約聖書と同じで、物語としてもとても面白いんですよ。
あーー、この箸墓古墳は近畿における卑弥呼の墓と呼ばれていて・・・ どんどん横にそれるので、いい加減にしておきます。マンガと関係ない長い話を読んでいただけてありがとうございました。 m(_ _)m
つるさんにお借りしています。
収録作および初出
「鬼追うもの」 プチフラワー 1994年7月号
「神遣い (かみやらい)PART 1」 プチフラワー 1995年1月号
「神遣い (かみやらい)PART 2」 プチフラワー 1995年3月号
「神遣い (かみやらい)PART 3」 プチフラワー 1995年5月号
舞台は 大崩壊 が起きて旧世界が崩壊してしまった地球。人の住んでいる宇宙ステーションもあるらしいので、未来の話でしょう。
邪気を締め出した 「聖域」 であるはずの ヒモロギ府 に鬼が出没し、府外の都市ギルドから鬼追いの特殊技能者である 朱楽 (あけら) が呼ばれた。朱楽 は府のぐるりを囲む 羅城 (らじょう) の警備隊の隊長である 篁(たかむら) に出会い…
とあらすじを試みようとしたが、いつものように 史生さん の作った世界を説明するだけで相当文字数がかかる上、いくら説明してもなーんか違った話になりそうなので、 この世界のしくみとストーリー を説明するのはやめたやめた~。
史生さん の本の中では比較的新しくてまだ手に入りそうだし。(セブンアンドワイでは、入荷次第メールでお知らせになってる)
それじゃ作品の紹介にならないじゃん、と自分でも思うが、史生さん の宗教観が以前から気になっていたので、そこら辺を少し。
というのも、この作品には古代日本人の神に対する宗教観と言ったものが表されているような。
一応コミックス一冊がすべて続いている連作になっていますが、「鬼追うもの」 は平安時代の信仰世界が基盤になっているようです。。鬼を追い払う「追儺 ついな」の儀式である鏑矢を放ったり、桃の木で作った弓や杖を持ち、祈祷をしていたりするので、そうじゃないかな~と。
これは実は別名を 「鬼やらい」 と言って、見事に次の3作に題名が繋がっているのです。3作の題名は 「神遣い」 ですが、神と鬼とは古代日本では同じものなんですよ。これは後で話しましょう。
作者も表紙見返しに
鬼を追いかけたら、平安時代に行き着いてしまった云々・・・
と書いているが、いえそれどころか、史生さん の興味は 記紀 (古事記・日本書紀) まで行ってるでしょ !
「神遣い」 3作はもっと前の大和朝廷以前の古代日本の信仰世界が基盤になっているように思えます。前者はこの世界の中でも特に文化的進歩的 (とされている) 首都の中でのお話、後者3作はいわゆる田舎の蛮地で起こる話、という区別もあるのかも知れません。
全部はよく分からないんですが、地名・人名などの名前のひとつひとつが古事記や日本書紀から出されているようで、なにやらいわくありげです。朱楽 がおへそで飼っている 式神 のライコウのエサの土蜘蛛も記紀に出てきますよ。
どれだけの資料を読んでこれらを描きあげたものか
 もともと歴史がお好きなんでしょうが、好きで読むだけと、頭の中で再構築してこんなストーリーを作るのとは大違い、ですからね~
もともと歴史がお好きなんでしょうが、好きで読むだけと、頭の中で再構築してこんなストーリーを作るのとは大違い、ですからね~
古来、日本人は 八百万の神 やおよろずのかみ と言って、山や海の自然物、動植物全てにも神が宿ると考えて敬い祭ってきましたが、それはキリスト教のように 「我をお守りください」 という考えでなくて、 「我らに祟らないで下さい」 という考え方で、私はそういう意味じゃ西洋の神様と日本の土着の神様は全然違うもの、神様 というひとつの文字を使うのは意味が違うんじゃないかと思っているのです。
そこら辺はもう大学の偉い先生方がいろいろ書いてらっしゃるでしょうから、私ごときが言うことじゃないでしょうが、とにかくここでは、昔々、日本では神も鬼も人間にとっては祭っておいてお祈りして、どうか祟らないでね、という対象だったということが分かれば、「神遣い」 の題名の意味が分かると思うのです。
最後の方、一言主 (ヒトコトヌシ) と古主 (フルヌシ) が出てきましたね。ヒトコトヌシ というのは、古事記によると 一事主命 と書かれていて、太古より大和地方、葛城山に住んでいる神のこと。
第21代の天皇である雄略天皇が葛城山で狩りをした折、自分そっくりのヒトコトヌシに出会って先に名を名乗れと言われ、神とわかって一緒に楽しく狩りをした、というくだりがあります。
自分そっくりという逸話の通り、ヒトコトヌシはやまびこやこだまが神格化されたものであるといわれています。まだまだ神話の世界のお話ですね。
一方、「続日本紀」 には雄略天皇が無礼な葛城の神を土佐へ流刑にしたと記されており、高知市には移されたヒトコトヌシ神を祭る土佐神社が今もあるそうです。このことは雄略が即位に際し、大和の有力な土豪であった 葛城氏 を滅ぼした史実を伝えているのでしょう。
古事記・日本書紀その他古代や江戸時代のものまで、勝者の書いた歴史書の中にもちらちらと先住民のことが出ているし、真実が隠されているので深読みしている解説書を読むと、大変面白いのです。私の頭の中でもうごっちゃになっていて、出典がどれか分からなくなってますが。
大和地方、三輪山の土地神であるオオモノヌシの娘 (実は先住民の土豪の娘) と神武天皇の結婚譚とかはまさに土地のものと姻戚関係を結ばなければ支配が容易に出来なかっただろう、とか分かるわけです。
日本書紀には同じオオモノヌシとヤマトトトビモモソヒメのミコトとの結婚とちょっと恥ずかしい姫の死因の話 → 箸墓古墳の中の真ん中より少し下にあり が載ってますし。記紀って旧約聖書と同じで、物語としてもとても面白いんですよ。
あーー、この箸墓古墳は近畿における卑弥呼の墓と呼ばれていて・・・ どんどん横にそれるので、いい加減にしておきます。マンガと関係ない長い話を読んでいただけてありがとうございました。 m(_ _)m