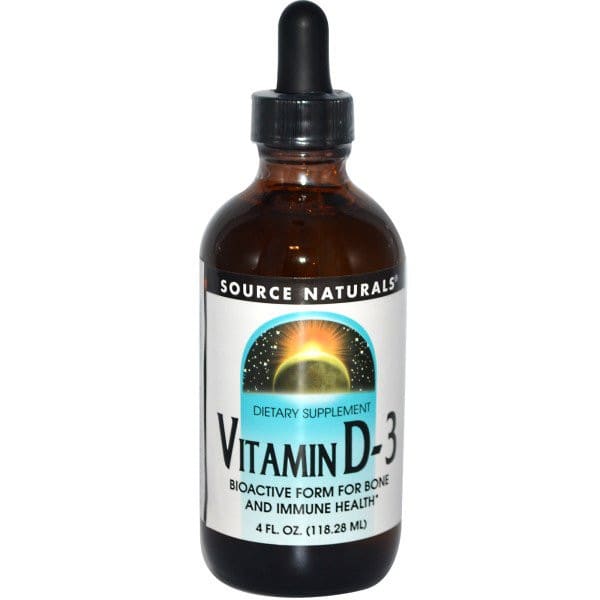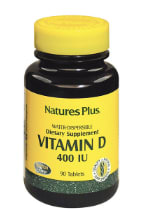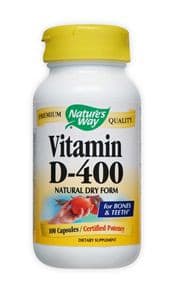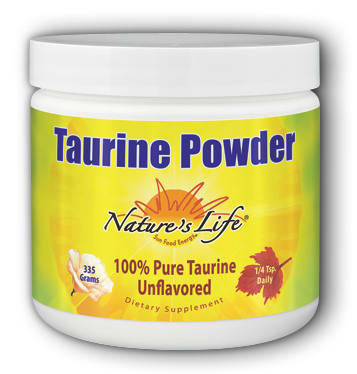★ Rhttps://ja.wikipedia.org/wiki/アポトーシス Wikipediaから
アポトーシス、アポプトーシス[1]
(apoptosis) とは、多細胞生物の体を構成する細胞の死に方の一種で、個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる、管理・調節された細胞の自殺すなわちプログラムされた細胞死(狭義にはその中の、カスパーゼに依存する型)のこと。ネクローシス(necrosis)の対義語として使われる事が多い。
Apoptosis の語源はギリシャ語の“απόπτωσις”, apoptosis アポプトーシス:「apo-(離れて)」と「ptosis(下降)」に由来し、「(枯れ葉などが木から)落ちる」という意味である。英語では[ˌæpəˈtoʊsəs,ˌæpəpˈtoʊsəs][2]と発音されるが、この語が最初に提唱された論文では2番目のpを黙字としている[3]。
特徴としては、順番に
細胞膜構造変化(細胞が丸くなる)
核が凝縮する
DNA 断片化(DNAが短い単位(ヌクレオソームに相当)に切断される)
細胞が小型の「アポトーシス小胞」とよぶ構造に分解する
といった変化を見せる。
多細胞生物の生体内では、癌化した細胞(そのほか内部に異常を起こした細胞)のほとんどは、アポトーシスによって取り除かれ続けており、これにより、ほとんどの腫瘍の成長は未然に防がれている。
また、生物の発生過程では、あらかじめ決まった時期に決まった場所で細胞死が起こり(プログラムされた細胞死)、これが生物の形態変化などの原動力として働いているが、この細胞死もアポトーシスの仕組みによって起こる。例えばオタマジャクシからカエルに変態する際に尻尾がなくなるのはアポトーシスによる[4]。線虫では発生において起こるアポトーシスがすべて記載されている。人の指の形成過程も、最初は指の間が埋まった状態で形成され、後にアポトーシスによって指の間の細胞が死滅することで完成する。さらに免疫系でも自己抗原に反応する細胞の除去など重要な役割を果たす。
シドニー・ブレナー、ロバート・ホロビッツ、ジョン・サルストンはこの業績により2002年のノーベル生理学・医学賞を受賞している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● 自閉症等は発症から3年以内が一種のターニングポイントですが、それはDR.大山恵昭の
研究によれば、脳障害が固定される=脳細胞の死滅が限界を超えるという事です。
アルツハイマー病でも同様に3年です。
● 進行した認知症の場合は、MRIやCT等で画像診断すれば、脳がスカスカになって多くの細胞が
死滅した後が分かります。この死滅現象は、炎症を伴いませんから、いわゆる普通の
障害による死滅とは異なります。ではどのような死滅かと云えば
● アポトーシスと云う炎症を伴わない死滅という事です。これは細胞の自殺を意味します。
普通のけがなどの場合は、傷ついた細胞や細胞成分を処理しようとして、
免疫細胞等がやって来て炎症が激しく起こります。赤くはれる現象です。
● しかしアポトーシスの場合は、細胞が瞬間的に細かく分断され・消滅して、炎症は起こりません。
これがある程度進行すれば、脳は完全に元に戻ることはあり得ないという事になります。
これがターニングという事なのでしょう。
● 細胞が内部からアスベスト等やヒューマンパピローマウイルス(HPV)に侵された場合は、
外からの免疫細胞は、ウイルスを感知できませんから、攻撃も出来ません。またHPVは免疫が
できにくい事は分かっています。段々と細胞が侵されると細胞は2つの方法を取ります。
1⃣ 1つ目は、アポトーシスを起こし、ウイルスもろとも自殺して、内部のウイルスも消滅させます。
2⃣ 2つ目は、細胞が狂って、止めどもない増殖を繰り返すことです。つまり、癌化です。
● これが細胞内にアスベストとHPV感染を起こして、2つの病態が起こりえる説明となります。
つまり、アポトーシスを起こしてアルツハイマーや自閉症になるか、癌になるかの2つに一つという事です。
● ある自治体の調査で、軽症の認知症は、その4割弱が自然軽快するという事が分かっています。
言い換えれば、上記3年以内に、何らかの生活上の変化が、
認知症を治したということになります。
● 従って、生活上の変化が何であるかが分かれば、認知症も防げるという事になります。
アポトーシス、アポプトーシス[1]
(apoptosis) とは、多細胞生物の体を構成する細胞の死に方の一種で、個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる、管理・調節された細胞の自殺すなわちプログラムされた細胞死(狭義にはその中の、カスパーゼに依存する型)のこと。ネクローシス(necrosis)の対義語として使われる事が多い。
Apoptosis の語源はギリシャ語の“απόπτωσις”, apoptosis アポプトーシス:「apo-(離れて)」と「ptosis(下降)」に由来し、「(枯れ葉などが木から)落ちる」という意味である。英語では[ˌæpəˈtoʊsəs,ˌæpəpˈtoʊsəs][2]と発音されるが、この語が最初に提唱された論文では2番目のpを黙字としている[3]。
特徴としては、順番に
細胞膜構造変化(細胞が丸くなる)
核が凝縮する
DNA 断片化(DNAが短い単位(ヌクレオソームに相当)に切断される)
細胞が小型の「アポトーシス小胞」とよぶ構造に分解する
といった変化を見せる。
多細胞生物の生体内では、癌化した細胞(そのほか内部に異常を起こした細胞)のほとんどは、アポトーシスによって取り除かれ続けており、これにより、ほとんどの腫瘍の成長は未然に防がれている。
また、生物の発生過程では、あらかじめ決まった時期に決まった場所で細胞死が起こり(プログラムされた細胞死)、これが生物の形態変化などの原動力として働いているが、この細胞死もアポトーシスの仕組みによって起こる。例えばオタマジャクシからカエルに変態する際に尻尾がなくなるのはアポトーシスによる[4]。線虫では発生において起こるアポトーシスがすべて記載されている。人の指の形成過程も、最初は指の間が埋まった状態で形成され、後にアポトーシスによって指の間の細胞が死滅することで完成する。さらに免疫系でも自己抗原に反応する細胞の除去など重要な役割を果たす。
シドニー・ブレナー、ロバート・ホロビッツ、ジョン・サルストンはこの業績により2002年のノーベル生理学・医学賞を受賞している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● 自閉症等は発症から3年以内が一種のターニングポイントですが、それはDR.大山恵昭の
研究によれば、脳障害が固定される=脳細胞の死滅が限界を超えるという事です。
アルツハイマー病でも同様に3年です。
● 進行した認知症の場合は、MRIやCT等で画像診断すれば、脳がスカスカになって多くの細胞が
死滅した後が分かります。この死滅現象は、炎症を伴いませんから、いわゆる普通の
障害による死滅とは異なります。ではどのような死滅かと云えば
● アポトーシスと云う炎症を伴わない死滅という事です。これは細胞の自殺を意味します。
普通のけがなどの場合は、傷ついた細胞や細胞成分を処理しようとして、
免疫細胞等がやって来て炎症が激しく起こります。赤くはれる現象です。
● しかしアポトーシスの場合は、細胞が瞬間的に細かく分断され・消滅して、炎症は起こりません。
これがある程度進行すれば、脳は完全に元に戻ることはあり得ないという事になります。
これがターニングという事なのでしょう。
● 細胞が内部からアスベスト等やヒューマンパピローマウイルス(HPV)に侵された場合は、
外からの免疫細胞は、ウイルスを感知できませんから、攻撃も出来ません。またHPVは免疫が
できにくい事は分かっています。段々と細胞が侵されると細胞は2つの方法を取ります。
1⃣ 1つ目は、アポトーシスを起こし、ウイルスもろとも自殺して、内部のウイルスも消滅させます。
2⃣ 2つ目は、細胞が狂って、止めどもない増殖を繰り返すことです。つまり、癌化です。
● これが細胞内にアスベストとHPV感染を起こして、2つの病態が起こりえる説明となります。
つまり、アポトーシスを起こしてアルツハイマーや自閉症になるか、癌になるかの2つに一つという事です。
● ある自治体の調査で、軽症の認知症は、その4割弱が自然軽快するという事が分かっています。
言い換えれば、上記3年以内に、何らかの生活上の変化が、
認知症を治したということになります。
● 従って、生活上の変化が何であるかが分かれば、認知症も防げるという事になります。