9時、起床。
パンとサラダと牛乳の朝食。

午前中に母の診察に付き合って池上の病院へ。
台風一過の晴れ間にフェーン現象が加わって梅雨明けを思わせるような真夏日である。



いったん自宅に戻り、昼過ぎに家を出て、大学へ。
駅前での立ち仕事はさぞかし大変だろう。


昼食をとるため神楽坂で途中下車して「SKIPA」に寄る。
もうじきお祭りがあるのだろう、商店街にはたくさんの提灯が取り付けられている。



のんちゃんだが、「梅ジュースがメニューに出ました」と教えてくれる。今年はよく梅が漬かったそうだ。とりあえず梅ソーダを注文。ああ、美味しい。暑い日にはこれに限る。

ソーダ水を飲み干した後のお楽しみがこれ。

スキッパ定食を注文。
「先生、ずいぶん陽に焼けてますね」と宙太さんが言う。うらやましそうである。私は陽に焼けやすい体質で、日中普通に外を歩いているだけで、海や山に行った人のように焼けるのである。宙太さんは昼間はずっと店内にいるので、陽に焼けない。のんちゃんは私と同じく陽に焼けやすい体質だが、とにかく暑いのが大の苦手だから、真っ黒になるということはない。

2時からUさんのゼミ論の個別相談。続いて、3時からSさんのゼミ論の個別相談。
これで4年生全員(19名)のゼミ論指導がひとわたり終わった。 就活と並行してのものだったから、それほど進んでいるわけではないが、夏休みに入る前に個別相談をしておくことに意味があるのである。個別相談は秋学期にも行うが、そのときは提出期限が迫っているから、テーマそのものの意味などについて考えている余裕はなくなっている。ゼミ論や卒業研究(文学部の学生ならば卒業論文)はその学生が4年間の大学生活を送ったことの知的証明である。どんなテーマと取り組んむのかといことがそもそも肝心なことである。「どうしてもこのテーマと取り組んでみたいのです」という思い入れが感じられるかどうかが、私から見た場合の、一番のポイントである。それらしいテーマなら五万とある。でも、なぜそうした五万とあるテーマの中からその1つを選んだのか。その理由を知りたいのである。そうした特別の思い入れがなくても、400字詰め原稿用紙換算で50枚の論文ならば、何冊か参考文献にあたれば、そこそこまとめることができるだろう。そう、ただまとめただけの論文だ。書き始める前から結論が見えてしまっているような論文だ。読まされるほうも面白くないし、書いている本人だって面白くないだろう。そんなもののために大学生活の最後の数か月を浪費するなんて馬鹿げている。


4時から私のゼミに興味があるという2年生と面談。ゼミ選考が行われる秋学期には留学に出ているので、その前での面談となったわけである。
面談の後、そのままゼミ見学をしてもらう。
今日は私の体調が十分ではないので、前半の2学年合同ゼミは短めに終わって、後半の学年別のゼミに早々に移行する。移行する前に、いつもより早めのスイーツタイム。今日のスイーツはさきほどゼミ論個別相談をしたUさんが用意してくれたチーズケーキ。

私は3年生のゼミに出たが、見学の学生がいたので、デュカッションを始める前に、その学生のために、今日とりあげるテキストの章の内容についてアウトラインを説明してくれるよう何人かの学生に求めたが、上手に説明ができない。実はこれは予想していたことだった。これまでのディスカッションを聴いていて、たしかに活発なディスカッションではあるのだが、部分的なテーマに議論が集中する傾向があり、はたしてみんなテキストの議論の全体の流れをちゃんと把握しているのかという疑問を覚えていた。読んだテキストの内容をそれを読んでいない人に説明できるためには、テキストの内容をきちんと理解し、自分のものにしていなければならない。たとえば「憂鬱」という漢字を読めても、書くことはできないというレベルでは「憂鬱」という漢字を自分のものにしているとはいえないのと同じようなものだ。受動的な理解と能動的な理解と言い換えてもよい。テキストを読んで、その内容を能動的に理解するためには、議論の流れをチャートにまとめながら読むなどの工夫が必要である。それをすることでその論文のポイントや問題点が見えてくるだろう。ディスカッションでとりあげるべきはそうしたところである。
ゼミを終え、今日の夕食は「ワセダ菜館」でとることにした。『孤独のグルメ』4の初回を観て、定食屋で食事がしたくなったということもあり、「夜トンボロ」だとスパゲティということになるが、今日はもう少ししっかりしたものを食べたい気分だったのだ。

かつ煮定食+ほうれん草のごま和えを注文。ここで食事をするときの定番なり。


食後のコーヒーは「カフェ・ゴト―」で。お腹一杯に食べたせいで、ウトウトしていたら、マスターに「お疲れのご様子ですね」と言われてしまった。
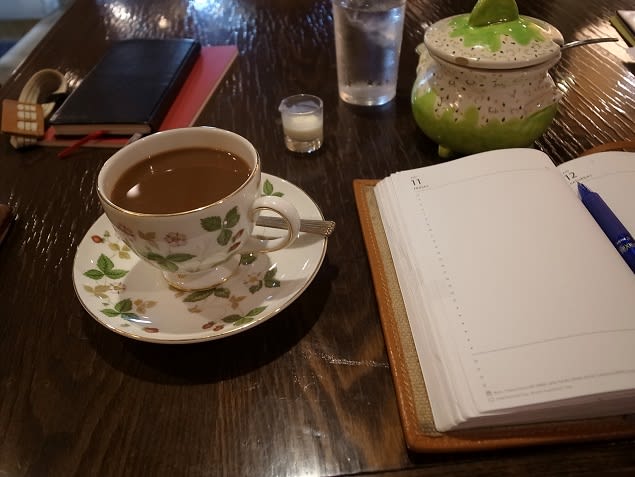
10時、帰宅。
録画してまだ観ていなかった『若者たち2014』の初回を観る。小学生の頃に観た『若者たち』(1966)と同じく両親を早くになくした5人きょうだいが激しくぶつかりあいながらも「家族」として生きていくという基本的な部分は同じなのだろう。リメイク版の特徴は、家族の外部の登場人物たちが重要なポジションを占めている点だ。その重要度に比例するようにそれを演じる俳優陣も豪華である。まるでオールスターゲームをみているようである。それぞれの関係性の中でエピソードがもりだくさんだ。すべての関係性を毎回同時進行で描いていくのだろうか。それとも回ごとに焦点をあてる関係性が入れ替わるのだろうか。脚本家の力量が問われるところだ。舞台劇のようなセリフ回しや、長男のキャラクターや、物語の舞台となる東京の下町の雰囲気のせいで、現代の物語というよりも、少しばかり昔の物語という感じがする。人と人とが激しくぶつかりあっていた時代の物語だ。こんなふうに(ときに)激しくぶつかりあってみたいという気持ちがこれを観る現代の若者たちにどれだけ残っているかが、このドラマの成否を握る一つの外的要因となるだろう。















