8時半、起床。
マフィン、ポテトサラダ、紅茶の朝食。

昼から大学へ。
これまで半分、工事車両の通行用になっていたスロープが、工事の終了に伴って全面開通した。幅広のスロープが戻ってきた。


スロープから中庭へ。

中庭も工事現場を囲っていた仕切りがなくなって、すっきりした。


春の訪れがそこそこに感じられる。

一文の社会学専修の卒業生(1997年卒)のSさんがやってきた。年末に会う約束だったのだが、私の母の体調不良で延期になっていたのである。

研究室で少し話をしてから食事に出る。

「五郎八」へ。私は天丼とせいろのセット、Sさんは揚げ餅そばを注文。


食後のコーヒーは「カフェゴト―」で。バナナタルトと洋梨のフランを注文して、ハーフ&ハーフにしてもらう。


Sさんはいま「産後クライシス」を克服するための夫婦参加型のワークショップ「OYAOYA?」を企画中で、今日はその話を聞かせてもらった。「産後クライシス」というのは、出産後に見舞われやすい夫婦関係の危機を表す言葉だが、危機の原因は、第一に、出産によって生じる生活の変化は妻の側にとても大きく夫の側に比較的小さいこと、第二に、その変化の不均衡に夫が鈍感であること(不均衡そのものに気付かないという場合もあれば、気付いていながらそれを当然のこととして見ている場合もある)。その結果、妻の夫に対する愛情は低下し、離婚に至るケースも出てくる。
(妻の)主産後、夫の生活構造には「子ども」という新しい要素が出現するが、それは夫の既存の生活構造を構造的に変化させるものではない。以前と同じように彼は職場と家庭の往復を続ける。もちろん育児の手伝いはするだろうが、それはあくまでも補助的な労働であって、彼の主要な労働はあいかわらず職場での労働である。一方、(出産前まで働いていた)妻にとっては、労働の場が職場から家庭に大きくシフトし、生活時間も子ども中心的なものに再編成される。最近、小さな子どものいる卒業生からこんな話を聞いた。「今日、自分がどんな食事をしたのか覚えていないんです」。育児の合間の隙間の時間に、立ったままで何かを食べているからだ。生活構造を住宅に喩えれば、夫側の変化は増築型であり、妻側の変化は改築型である。夫はこれまでと基本的に同じ住宅で暮らしているが、妻は新しい住宅(しかもそれは工事中であったりする)での暮らしが始まるのである。新しい暮らしを始めるのは大きなエネルギーが必要で、当然、ストレスも大きい。夫はそのことに気付かない。あるいは気付いていても、それを当然と考えている。妻は夫への不満や、育児の不安や、(将来の)職場復帰への不安を抱えながら、育児に専念しなければなら状況に置かれる。
そうした状況がたまたまのものではなく、出産後の女性が構造的に置かれやすい状況であるということを女性自身が知ることは、その状況を「自分がいけないんだ」「自分が間違っているんだ」と自責の念から女性を救うことになる。だからワークショップへの参加は女性が一人でしても意味はある。でも、夫婦で参加することにもっと大きな意味がある。「産後クライシス」は女性と新しい住宅の間で生じるのではなくて、新しい住宅の同居人である夫との間で生じるものであるからだ。夫に自分たちが新しい(しかも工事中の)住宅で暮らし始めているのだということをわかってもらう必要があるからだ。
このワークショップの成否は夫が一緒に参加するかどうかにかかっている。ちょっと皮肉な見方をすれば、夫婦で一緒にこのワークショップに参加する時点で、その夫婦はすでに「問題のある家庭」から一歩外に出ているともいえるだろう。「問題のあるレストラン」は「レストラン」という場所が公共的なものであるが故に「問題」にしやすいが、「家庭」という私生活の場は「問題」を「問題」として表面化させにくい重力を備えているのだ。メンバーひとりひとりが「問題」を胸の中に押しとどめならが「幸福な家庭」の物語を演じているのだ。
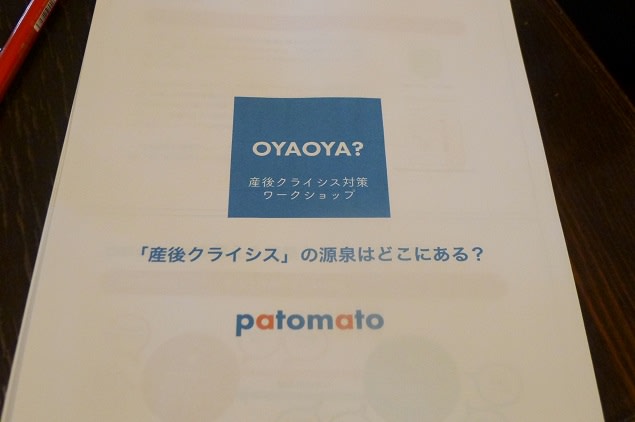
ワークショップの企画が具体化したら教えてください。

今日は帰宅はせず、上野発16時50分の東北本線(宇都宮行き)に乗って、宇都宮の1つ手前の雀宮へ行く。高校時代の友人Kに会うためである。Kはしばしばこのブログに登場する信州茅野の安楽亭の主人だが、彼は昨年定年を迎え、いまは嘱託として会社の工場のある雀宮に単身赴任しているのである。
東北本線(宇都宮線)にはけっこうたくさんの乗客がいたが、上野から1時間の久喜でどっと降りた。このあたりが通勤圏の外縁であることがわかる。18時半過ぎに雀宮の駅を降りると、改札にKが迎えに来てくれていた。駅前には立派な図書館があって、明るく光っていた。

車でKのアパートに向かう途中、スーパーに寄って、夕食のすき焼きの材料を買い込む。牛肉、焼き豆腐、ネギ、白滝、麩、エノキ茸、卵、そして割り下。〆て5千円ほどになった。

5千円の大半は牛肉(3200円)が占めている。100グラム1000円の肉である。

よい肉と「今半」の割り下(ストレートタイプ)があればすき焼きの出来は保証されたようなものである。

ひとつ問題なのは、Kのところには卓上用のコンロがないことである。なので卓上で調理をしながらすき焼きをつつくということができない。台所で調理を済ませてから、すき焼き鍋を卓上に運んで(鍋の余熱で)食べることになる。

牛肉とその他の食材(ネギ、焼き豆腐、麩、白滝、エノキ茸)は同時には調理できない。いや、できないわけではないが、それは「すき焼き」とは別のもの、「牛鍋」と呼ぶべきものになる。「すき焼き」は肉を焼いて食べるが、「牛鍋」は肉を煮て食べる。「牛鍋」も決して不味くはないが、よい肉は「すき焼き」で食べたい。
なので調理は三段階のステップを踏む。第一ステップでは半分の牛肉を焼いて食べる。割り下は使うが、決して肉を割り下に浸してはいけない。割り下で煮てはいけない。

割り下で焼いた肉は(その他の食材から出る水分の影響を受けないから)濃い味付けになるが、生卵をくぐらせて食べることでちょうどいい感じになる。
う、うまい!

第2ステップでは牛肉以外の食材を調理する。割り下はふんだに使い(これに第1ステップの肉汁が加味される)、食材を時間をかけて煮る。
もっと肉が食べたいという欲求を抑えて、ストイックにあれこれの食材を楽しむ。とくにネギが美味しい。

そして第3ステップでは残りの半分の牛肉を第1ステップと同じようにして調理する。
やっぱり、うまい!

デザートはスーパーで見つけて購入した金沢兼六園名物、末広堂の「うすかわまんじゅう」。

これが美味しかった。5個入りだが、私が3個、Kが2個、ペロリと食べた。

Kが知り合いから送ってもらったというボンタン。綺麗な色をしている。

食事の最後はこれでスッキリと〆る。

食後、Kのあれこれのコレクションを見せてもらった。
「コップのフチ子」シリーズ。こういうフィギアの存在そのものを初めて知った。

山の立体模型(アルミ製)。

これは南アルプスのナントカ岳のナントカ沢からの登頂ルート。

銃弾(火薬は詰まっていない)。

コーヒーを飲みながら語り合う。

風呂を浴びて、12時頃、就寝。















