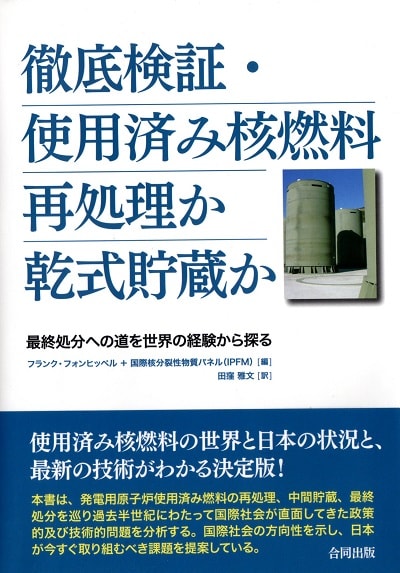寺尾忠能編『「後発性」のポリティクス 環境政策の形成過程』(アジア経済研究所、2015年)を読む。

中国の吉林省では、2005年、工場の事故によって河川に大量のベンゼン類が流出した。SARS対策を契機に、緊急性の高い事故・汚染等への対応が必要視されていたときであったこともあり、この事故への対応のまずさは、情報公開や指揮系統のあり方を問うことにもつながった。事件後、地方政府は、汚染現場にNGOやジャーナリストが入ることへに警戒しているという。情報公開のまずさに対する批判が、却って情報公開そのものを慎重にさせるという傾向は、日本にも共通するところがあるのかもしれない。
タイのチャオプラヤでは、2011年に大洪水が起きた。発生から長い時間が経ってもどの地域に水が来るのかはっきりせず、また、水が引くにも長い時間を要した。わたしもバンコクに行く用事をいつまで延期しなければならないのか見通しが立たず、やきもきさせられた記憶がある。これこそが、勾配が緩やかなチャオプラヤの特性である。そのとき、安定政権がインフラ投資できなかったからこのような事態になったのだという声をしばしば聞いたものだが、本論によれば、新旧の縦割り組織が事故対応を難しくしていたのだった。インラック政権は短期対応には高く評価すべき組織改革を行ったが、中長期の水資源管理対策についてはうまくいかぬまま、クーデターを迎えた。そして、組織はまた非効率な形へと戻ってしまった。
カンボジアの巨大なトンレサップ湖では、2012年、かつてフランスによって導入された区画漁業制度が撤廃された。このことは、政府主導の私有資源化(囲い込み)とは逆の、珍しい「脱領域化」である。実は、いまや漁業由来の歳入は非常に小さく、それを考えあわせれば、非常に多くの零細漁民を含めた人々に利益を再分配し、政治的な安定をはかるべきだという狙いが政府にあったのではないかという(カンボジア国民1,500万人のうち、トンレサップ湖に何らかの利害を持つ者の人口はなんと400万人)。しかし、その一方で、生態系や漁業資源の管理があやういものとなっている。実際に、目に見える形での悪影響は出ているのだろうか。
台湾では、水質保全の法制度が整備されてきたものの、それは必ずしも実効的なものではなかった。逆に不十分な法制度を作ってしまったことが、それを言い訳とする使い方を許してしまい、環境影響の観点からはマイナスともなった。日本では、浦安の「黒い水事件」(1958年)を受けて導入された「水質二法」が実際には甘く、むしろ公害追認法として機能し、その後の水俣病の被害拡大を招いてしまった。台湾でも同様に「緑色牡蠣事件」(1986年)が政治問題化し、関連法制度が整備された。しかし、日本と同様の失敗を繰り返してしまった側面があるのだという。
ドイツで1991年に導入された容器包装例は、容器包装廃棄物に関する拡大生産者責任(EPR)を法制化するモデルとなった。環境の時代を象徴するような政策であり、日本の容器包装リサイクル法にも大きな影響を与えている(わたしも1999年頃にOECDでのEPRの会議を黒子として手伝い、大変な勢いがあったことを記憶している)。なぜこれがドイツで導入されたのか。そこには、缶など「ワンウェイ容器」の台頭を脅威とするビールメーカーが多く立地する地域出身の政治家の存在があった。そして、政府と産業界とのせめぎあいにおいて、瓶など「リターナブル容器」の回収率が常に問題とされた。日本でも、リターナブル容器のほうが環境負荷が小さいとする論文が酢メーカーによって公表され、目立っていた記憶がある。
また、ドイツでは、埋め立てや焼却を従来通り公共部門が、そしてリサイクルを民間が行う「デュアル・システム」が導入された。おそらくリサイクルの事業性について明確なメッセージがないまま進んだのではないかと思ってしまう。日本では、容器包装リサイクル法の導入当時、ペットボトルのリサイクルに新規事業者が急激に参加し、原料としてのペットボトルの過不足やコストの乱高下を生んでしまった。果たしてドイツではどうだったのだろう。
大恐慌後、ニューディール期のアメリカでは、公共政策としての「保全」概念が拡張した。すなわち、水や森林の管理だけでなく、野外レクリエーションの機会創出、都市・農村間の格差解消までもが「保全」の範疇内なのだった。それに伴い、雨後の筍のように、数々の機関ができ、収拾がつかなくなった。これを受けて、連邦政府は「保全」という理念をもとに、権限争いをする省庁・機関をうまく統合し管理しようと試みた。そのひとつの答えがEPA(環境保護庁)なのだろう。著者は、「理念」の「制度化」のプロセスを検証しておくべきだとする。
本書は、寺尾忠能編『環境政策の形成過程』の続編的な本であり、同書と同様に、各国において環境政策がどのように導入され、多くの場合、それがどのように失敗したのかといった観点で掘り下げたものとなっている。齧った分野も関心のあった分野も取り上げられており、それぞれ興味深く読んだ。さらなる続編を期待したい。
●参照
寺尾忠能編『環境政策の形成過程』
佐藤仁『「持たざる国」の資源論』