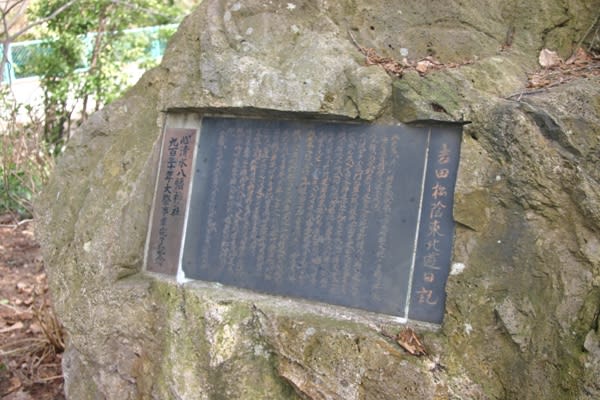先日、ラジオで、宗教学者 山折哲雄氏の講演「震災と日本人の心」を聞いた。 【拙ブログ 「斎藤茂吉、石川啄木、宮沢賢治」 2012-09-03 | 文芸】
いつも身近な「茂吉、啄木、賢治」の話だったので、耳をそばだてて聞いた。
さっそく本棚から、茂吉、啄木、賢治の本を持ち出して、ページをめくった。かつての心躍らせた青春の日々が甦ってきた。
あらためて豊かなこころに触れながら、講演の大震災との関わりを考えた。
震災、さらに原発事故に見舞われ、今切ない気持ちで過ごしている被災者を、そして人生を考えた。
そこで、どうしても賢治の思想を辿ってみたいと思った。
昨年末、ロジャー・パルバース氏のテレビテキスト「銀河鉄道の夜」を求めた。【100分de名著12月号。】
その表紙タイトルの脇には、《悲しみを、乗り越えよ》 《ほんとうの幸いとは》 とあった。 【拙ブログ 「賢治をもう一度見つめてみたい」 2011-11-30 | 文芸】
まずは、賢治の「銀河鉄道の夜」を読み直した。 あらためて人間の生き方について考えさせられた。
・「我々はいずこから来て、どこへ行こうとしているのか。」
・「人が他人と協調して生きて行くには何が必要か。」
・「どうすれば人間は一度しかない人生に意味を持たせることができるのか。」
・「自然と共存していくために我々は何を為すべきか」
かつて引いた傍線に若き日を思いつつ、いままた心をとらえた箇所に傍線を付け加えた。
--------------------
先生はまた云いました。
「ですからもしもこの天の川がほんとうに川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星はみんなその川のそこの砂や砂利の粒にもあたるわけです。またこれを巨きな乳の流れと考えるならもっと天の川とよく似ています。つまりその星はみな、乳のなかにまるで細かにうかんでいる脂油の球にもあたるのです。そんなら何がその川の水にあたるかと云いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりそのなかに浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水のなかに棲んでいるわけです。そしてその天の川の水のなかから四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集って見えしたがって白くぼんやり見えるのです。この模型をごらんなさい。」
--------------------
するとどこかで、ふしぎな声が、銀河ステーション、銀河ステーションと云いう声がしたと思うといきなり眼の前が、ぱっと明るくなって、まるで億万の蛍烏賊の火を一ぺんに化石させて、そら中に沈めたという工合、またダイアモンド会社で、ねだんがやすくならないために、わざと穫れないふりをして、かくして置いた金剛石を、誰かがいきなりひっくりかえして、ばら撒いたという風に、眼の前がさあっと明るくなって、ジョバンニは、思わず何べんも眼を擦すってしまいました。
--------------------
河原の礫は、みんなすきとおって、たしかに水晶や黄玉トパースや、またくしゃくしゃの皺曲をあらわしたのや、また稜から霧のような青白い光を出す鋼玉やらでした。ジョバンニは、走ってその渚に行って、水に手をひたしました。けれどもあやしいその銀河の水は、水素よりももっとすきとおっていたのです。それでもたしかに流れていたことは、二人の手首の、水にひたったとこが、少し水銀いろに浮いたように見え、その手首にぶっつかってできた波は、うつくしい燐光をあげて、ちらちらと燃えるように見えたのでもわかりました。
--------------------
「カムパネルラ、また僕たち二人きりになったねえ、どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのさそりのようにほんとうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない。」
「うん。僕だってそうだ。」カムパネルラの眼にはきれいな涙がうかんでいました。
「けれどもほんとうのさいわいは一体何だろう。」ジョバンニが云いました。
「僕わからない。」カムパネルラがぼんやり云いました。
--------------------
「カムパネルラ、僕たち一緒に行こうねえ。」ジョバンニが斯う云いながらふりかえって見ましたらそのいままでカムパネルラの座すわっていた席にもうカムパネルラの形は見えずただ黒いびろうどばかりひかっていました。ジョバンニはまるで鉄砲丸のように立ちあがりました。そして誰にも聞えないように窓の外へからだを乗り出して力いっぱいはげしく胸をうって叫びそれからもう咽喉いっぱい泣きだしました。もうそこらが一ぺんにまっくらになったように思いました。
ジョバンニは眼をひらきました。もとの丘の草の中につかれてねむっていたのでした。胸は何だかおかしく熱り頬にはつめたい涙がながれていました。
--------------------
懐かしいジョバンニ、カムパネルラ、ザネイ、赤ひげの鳥捕り・・・、
銀河ステーションの鋼青の野原の表現、 「青白く光る銀河の岸に銀色の空のススキが、もうまるで一面、風にさらさらさら、ゆられて・・・。」 「ごとごとごと汽車はきらびやかな燐光の川の岸を進みました。」
カムパネルラがいなくなったときの、ジョバンニのこころに胸が詰まった。
ロジャー・パルバース氏の思いを参考に、心を整理した。
○ 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない
自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する
・・・・・・・・
新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある
正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くこと」 【農民芸術概論綱要】
○ 人間にとっての本当のさいわい(幸福)とはなんなのか?
○ 『銀河鉄道の夜』には、大切な人を失ったという死に対する悲しみが描かれているのと同時に、
悲しみの乗り越え方、その先の明日への歩みを進めるためのヒントが書かれている。・・・死をテーマに描きながら、それを乗り越えていく希望の物語。
○ 一番伝えたかったことは、「私とあなたは別々の存在ではなく、すべてのものはつながっている。」
○ 他人の悲しみや苦しみを十把一絡げにするのではなく、その一人ひとりと向き合って、その人の悲しみを聞きなさい。
「行ッテ」という言葉は、彼の生涯を見事に象徴する言葉。
東ニ病気ノコドモアレバ
行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ
行ッテソノ稲ノ束ヲ負イ
南ニ死ニソウナ人アレバ
行ッテコワガラナクテモイヽイトイヒ
北ニケンクワヤソショウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイイ
--------------------
年老いて、あらためて読む哀しい物語は、気づかなかった賢治の心を教えてくれた。
この美しくも哀しい旅をして、賢治の描く「天上」を想像した。それは何と、これまで 思っていた世界そのままのような気がしている。
賢治の思いを胸に、この震災に、原発事故に被った幾多の悲しみを、自分なりに受け止めたい。
そして、出来ることを行動に移したい気持ちでいる。