
近くの里山に、山を削り、かなりの林を切り開き灌漑用水路ができた。
昨年秋からの工事で、おそらく全長は1キロを超えるだろう。
山際の林の中の小さな流れが、幅10メートルを超える水路と道路に変わった。
クワガタやチョウが集まるクヌギの大木も、カワトンボの舞う木漏れ日もなくなった。
先日訪ねたその道で、切り崩された斜面に貝を見つけた。おそらく化石だろう。
昨日、孫たちを連れてその貝の化石を拾いに行った。昔ここも海だったことを教えたかった。

梅雨の晴れ間に、気温は31度を超えた。そんな中、孫たちは興味を持って貝を見つけて拾い集めた。
小さなシジミのような楕円形の褐色の二枚貝を沢山採集してきた。
博物館で、化石かどうか、この貝の名前や、いつごろのものかなどを聞いてみようと思っている。
広い道を大きなクスサンの幼虫が這っていた。久しぶりに見る大きな毛虫は真っ白な細かな毛、お腹のさわやかな空色の斑紋がきれいだった。

上空をオニヤンマの雄姿を見た。ミヤマアカネも今年初めてだ。また、蝉の声も初めて聞いた。いよいよ暑い夏到来だ。












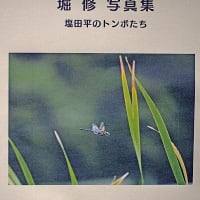








ミヤマアカネの翅の先端から少し入ったところの茶色の帯が何とも言えずお洒落ですね!
翅の途中に茶色のバンドそして、さわやかな白斑が何とも言えまっせん。成熟すると真っ赤になりますよ。
昨日コシアキトンボを初見しました。
コメントありがとう。
工事の賜物でフレッシュな化石が観られてラッキーでしたね。
シジミガイは淡水または汽水に棲むので、採集地あたりは、内湾か河口付近だったのでしょう。
そうですか、≪≫ジミガイは淡水または汽水に棲むので≫、化石でなく、比較的あたらいい可能性もありますね。
そのうち、地層等、博物館で聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。
わたしが卒論で扱ったのは、有孔虫の化石でしたので、二枚貝は鑑定できませんが、シジミガイの一種のようには見えます。
福島県立博物館には、地質学の専門の方がいらっしゃるはずですよ。
早速、県立博物館へ行ってきました。
専門学芸員にいろいろお聞きしましたが、結論は、化石ではなく、今生きているシジミのようです。地層は火山砕屑層や石英安山岩質浮石質などの層で、貝は考えられないとのこと。
私なりに推測すると、昔の堰を大きく広げる工事だったので、コンクリート枠を埋めるのに浚渫した土砂から出てきたのでは? でも、いま棲息しているかも調べる必要もあります。
種類の同定をお願いしてきました。
ネットで調べたら、タイワンシジミによく似ている印象です。タイワンシジミは、日本国内では1985年頃に移入が確認され、北海道を除く全都府県に生息していることが、2008年9月の時点で確認されたとありました。
もう少し現地等調べてみたいと思います。
MOさん、またいろいろ教えてください。
ありがとうございます。
実物を手に取り、採集地の地質を読み取り、科学的に鑑定するのがいいですよね。
学芸員の方に見ていただけてよかったです。
一つのことから知的好奇心が刺激され、探究するのは楽しいです。
なるほど…堰の拡幅工事をしたんですか…
また、面白い話題を取り上げてください。
では、また~