都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
私の正体をこのブログに来ている人だけにおしえましょう。実は私Chord name0029を持ったAgentです。

セイヨウオオマルハナバチの駆除が任務です。

今年は何かと忙しく今回がFirst Missionです。
体長は女王バチで18~22mm、働きバチで10~18mm。マルハナバチ共通の特徴である丸っこく、毛むくじゃらな体は本種も同じである。胸部と腹部は黄色と黒色の縞模様で、腹部第5節から先端までが白く、日本ではこの「真っ白なお尻」が他のマルハナバチ類と本種とを区別するための大きな特徴となります。
在来種のエゾオオマルハナバチとよく似ています。
この蜂は、女王鉢だけが受精した状態で越冬するので、今は女王しかいません。ですから今に時期に捕獲しなくてはいけないのです。


特殊任務コード: 0029
駆除日:5月20日
活動場所:自宅庭
訪花:淀川躑躅
捕獲:女王蜂1頭


刺されたら痛くないのかってご心配のみなさん。刺されたら痛いです。大きい蜂ですから、とても痛いです。しかし、毒はないので痛いだけです。
以前は東京大学と国立情報学研究所が共同で立ち上げ運営してきましたが、2015年5月より「北海道生物多様性保全活動連携支援センター(HoBiCC)」に報告をしなくてはいけません。
※セイヨウオオマルハナバチについては下記を御参照下さい。
本ネタは「夏茱萸咲きました」 MY GARDEN 2015.05.21です。
したっけ。
今年初めて夏茱萸の花が咲きました。写真は5月20日に撮影しました。5年ほど前から何か生えてきたので放置して観察していました。何か分からないものは、正体がわかるまで放置するのが私のやり方です。分かった時点で必要なければ撤去します。面白そうなので今のところは観察を続けます。
山地に自生する春咲きのグミです。名前の由来は、夏に果実が赤く熟すことからつきました。
「グミ」は「グイ実」の略で棘のある木の実という意味です。グイとは(徳島県阿波)(香川県香川)の方言で棘の意です。

花名:ナツグミ [夏茱萸]
科名:グミ科
属名: グミ属
花の色:白 黄色
分布:北海道の南西部から本州の静岡県にかけて太平洋側に分布(日本固有種)
生育地:山野
植物のタイプ:落葉低木
開花時期:: 4~5月
大きさ:2~4m
花言葉:野生美





花の特徴は、葉のつけ根に垂れ下がるように淡い黄色(白)の花をつけます。花弁のように見えるのは萼筒で、先が4つに裂けています。萼筒の外側にはざらざらした斑があります。雄蕊は4本、雌蕊は1本です。
葉は楕円形で、互い違いに生えます(互生)。葉は柄があり、葉の先は鋭く尖っています。葉の表面は緑色で、裏面は銀白色をしており鱗毛を密生させています。
実は長さ12~17㎜くらいの幅の広い楕円形をした偽果(子房以外の部分が加わってできている果実)です。6月ころに緑色から黄色と変化し、真っ赤に熟すと食べられるそうです。
尚、グミは大和言葉であり、菓子のグミ(ドイツ語でゴムを意味する"Gummi"から )とは無関係です。
したっけ。
 |
HARIBO グミ ミニゴールドベアドラム 980g |
| ハリボー | |
| メーカー情報なし |
 |
きゅい~ん’ズ登場! |
| NOBE,Jiao Long,God-i | |
| DUNIVERSE |
今年も淀川躑躅の花が咲きました。写真は5月16日に撮影しました。昨年は5月19日に撮っていました。
日本では栽培品種として愛好されています。 朝鮮半島では自生しているものもあるそうです。「躑躅の女王」とも呼ばれ、牡丹躑躅(ボタンツツジ)の別名があります。
名前の由来になった淀川がどこの淀川なのかは不明だそうです。
先日紹介した「黒船躑躅」も「躑躅の女王」でしたので自宅庭に女王が二人いることになります。
公園や公共施設の周囲にたくさん植えてありますので、見たことがあると思います。(北海道だけかな?)

花名:ヨドガワツツジ[淀川躑躅]
科名:ツツジ科
属名:ツツジ属
花の色:淡い紫色
分布:原産地は朝鮮半島
生育地:庭園や公園
植物のタイプ:落葉低木
開花時期:: 4~5月
大きさ:1~2m
花言葉:想い出





花の特徴花の色は淡い紫色で、八重咲きです。(互生)。
実は、庭に出はなく家の中にも女王がいます。
いや、女王ではなく神さんです。こちらには逆らえません。
したっけ。
 |
【6か月枯れ保証】【山林苗木】ヨドガワツツジ 0.5m |
| クリエーター情報なし | |
| トオヤマグリーン |
 |
きゅい~ん’ズ登場! |
| NOBE,Jiao Long,God-i | |
| DUNIVERSE |
本ネタは「林檎咲きました」 MY GARDEN 2015.05.19です。
これは姪の娘の宣伝です。Twitterのフォローをお願いします。
https://twitter.com/Kyueens_Yukino
《拡散してください》 きゅい~ん'ズ各メンバーのフォロワーさんが 1240人達成すると新曲が増えます
きゅい~ん'ズ各メンバーのフォロワーさんが 1240人達成すると新曲が増えます みんなの力もかしてほしいです。絶対に6人で達成したいです! わたし!愛沢優姫乃っていいます
みんなの力もかしてほしいです。絶対に6人で達成したいです! わたし!愛沢優姫乃っていいます pic.twitter.com/hw9fT3LhXU
pic.twitter.com/hw9fT3LhXU
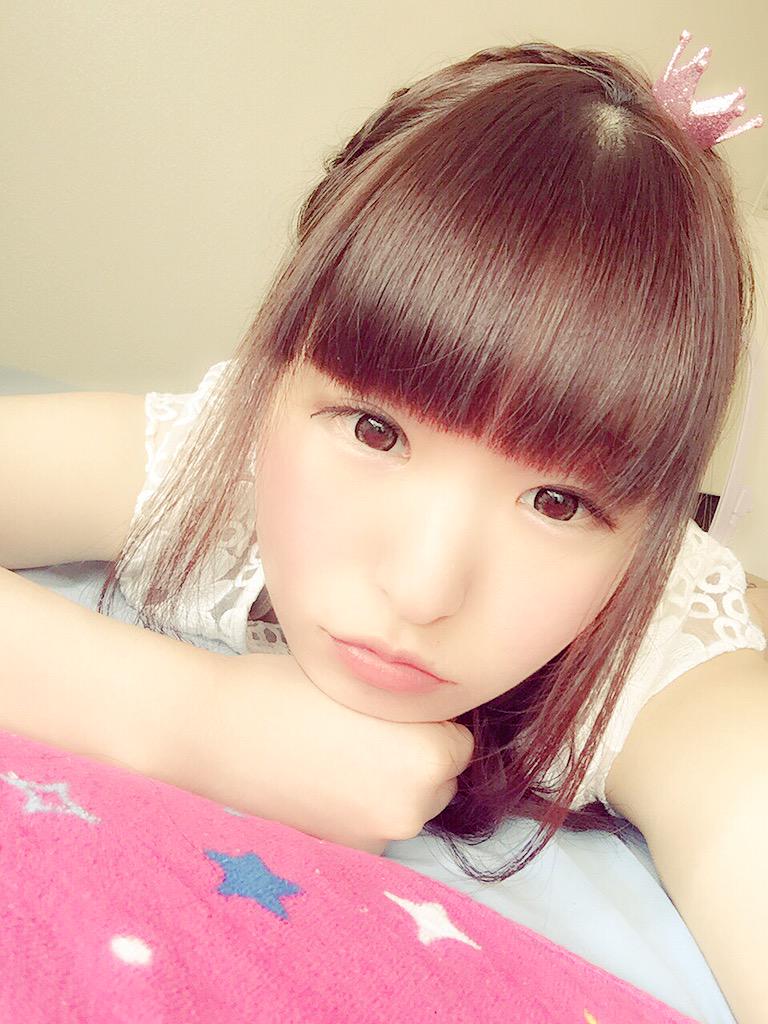

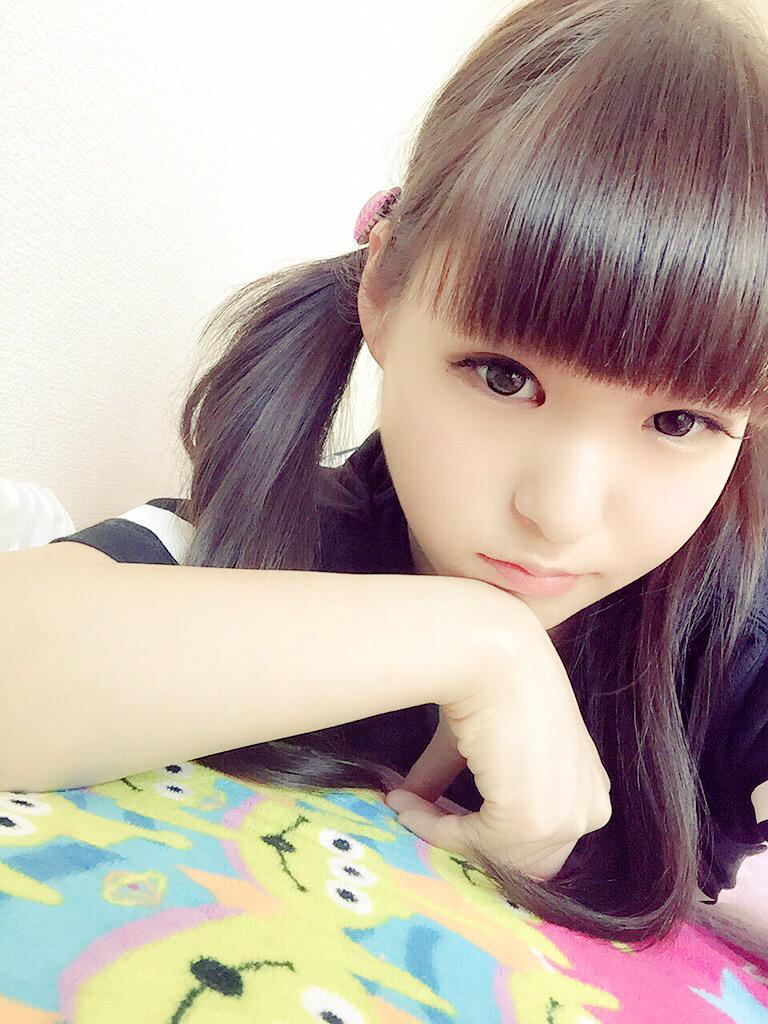

今年も林檎の花が咲きました。写真は5月16日に撮影しました。昨年は5月19日に撮っていました。
りんごは、古く中国を経由して渡来し、西欧系のリンゴの普及以前に日本でも栽培されていました。
林檎は中国語で、「檎」は本来「家禽」の「禽」で「鳥」を意味し、果実が甘いので林に鳥がたくさん集まったところから、「林檎」と呼ばれるようになったそうです。
「檎」は、漢音で「キン」呉音で「ゴン」と読まれることから、「リンキン」や「リンゴン」などと呼ばれ、それが転じて「リンゴ」となったそうです。
平安中期の「和妙抄(わみょうしょう)」では、「リンゴウ」と読んでいます。
一方、江戸時代以前に中国から渡来したものは和林檎(ワリンゴ)と呼ばれますが、現在ではほとんど栽培されていません。

花名:リンゴ [林檎]
科名:バラ科
属名:リンゴ属
花の色:白
分布:原産地は小アジアやコーカサス地方 現在日本で栽培されているものは西洋林檎(セイヨウリンゴ)から改良されたもので、これは明治時代以降に導入されたものです。
生育地:果樹園
植物のタイプ:落葉高木
開花時期:: 4~5月
大きさ:5~10m
花言葉:選ばれた恋





葉の脇から数本ずつ花柄を出し、淡い紅色を帯びた白い5弁花をつけます。
葉は幅の広い卵形で、互い違いに生える(互生)。 葉の縁には粗いぎざぎざ(鋸歯)があります。
果実は偽果(子房以外の部分が加わってできている果実)であです。食用にするのは花托(かたく:柄の上端にあって花弁や雌蕊などをつける部分)の発達したものです。
うちのリンゴは実がなっても小さくて固くて食べられません。摘果もしていません。
誰かさんのように、実にはこだわっていません。果樹園じゃないので、ニャンコの見回り隊もいません。
したっけ。
 |
内堀醸造 フルーツビネガー純りんご酢 1L |
| クリエーター情報なし | |
| 内堀醸造 |
 |
きゅい~ん’ズ登場! |
| NOBE,Jiao Long,God-i | |
| DUNIVERSE |
今年も目木の花が咲きました。写真は5月14日に撮影しました。昨年は棘が痛いといって母が切ってしまったので花は咲きませんでした。今年は切らないように言っておきました。
棘があるので「コトリトマラズ」や「コトリスワラズ」の別名もあります。
枝などを乾燥させたものを生薬で「小蘗(しょうはく)」といい、結膜炎などの目の病気に効くそうです。これが名の由来でもあります。 小蘗(しょうはく)は健胃、整腸、下痢止めなどの薬効もあるそうです。

花名:メギ [目木]
科名:メギ科
属名:メギ属
花の色:淡い黄色
分布:日本固有種 本州の関東地方から九州にかけて分布
生育地:山地や丘陵の草地や林の中など
植物のタイプ:落葉低木
開花時期:: 4~5月
大きさ:1~2m(よく枝分かれをし、針状の細い刺が枝や葉のつけ根に生える。)
花言葉:過敏





短枝から新しい葉とともに短い花序が出て、淡い黄色い花を数個下向きにつけます。花は、同じメギ科の柊南天(ヒイラギナンテン)に似ていて、それを小さくしたような感じです。花径は5~6ミリくらいで、花弁と萼片が6枚ずつある。萼片のほうが花弁よりも大きくて、萼のほうが花びらのように見えます。 雄蕊も6本あります。
葉は倒卵形で、長い枝では互い違いに生え(互生)、短い枝では束になって生えます(束生)。葉の縁にぎざぎざ(鋸歯)はなく「全縁」です。 紅葉もきれいです。
これは、「イボタ」と間違えて買う人がいます。お店でも「イボタ」と書いてあることがあります。棘があったら「イボタ」じゃありません。
したっけ。
 |
〔栃本天海堂/生薬〕鳥不止(刻) 500g とりとまらず・トリトマラズ 別名:目木(めぎ)《健康食品》 |
| クリエーター情報なし | |
| 栃本天海堂 |
 |
きゅい~ん’ズ登場! |
| NOBE,Jiao Long,God-i | |
| DUNIVERSE |
今年も常盤姫萩の花が咲きました。写真は5月14日に撮影しました。昨年は花が咲きませんでした。一昨年は5月24日ですから今年は早いです。
これはたくさんあったのですが、3年前の冬に枯れてしまい、やっとこれだけ咲くようになりました。
その年の冬は雪が少なく小さい植物は影響を受けました。雪が布団替わりなのです。
和名の由来は、「常盤」は常緑で、マメ科の萩に似た小型の花なので「姫萩」と名付けられたそうです。
常盤姫萩は流通名で、正式には「ポリガラ・カマエプクスス・プルプレア」といいます。

花名:トキワヒメハギ [常盤姫萩]
科名:ヒメハギ科
属名:ヒメハギ属
花の色:赤、紫
分布:原産地はヨーロッパ、アルプス山脈などに分布。
生育地:標高900~2、500mの林の中など
植物のタイプ:常緑小低木
開花時期:: 3~5月
大きさ:10~30㎝(地を這ってマット状に広がる。)
花言葉:過敏





葉の脇に花径1㎝くらいの小さな花を1~2個つけます。 花は蝶形で、竜骨弁が黄色く、翼弁と旗弁は紅紫色です。
|
竜骨弁:蝶形花(ちょうけいか)で、翼弁の下位につく左右一対の花びら 翼弁:蝶形花(ちょうけいか)で、左右一対ある花びら。鳥の翼に見立てていう。その上方に旗(き)弁、下方に竜骨(りゅうこつ)弁がある。 旗弁:蝶形花(ちょうけいか)で、上方にある1枚の花びら。 旗を立てたような形なのでいう。 |
葉は披針形で、互い違いに生える(互生)。 葉の質は革質で艶があります。
この奇抜な形と、鮮やかな色が高山植物コーナーで、一際目立っています。
したっけ。
 |
トキワヒメハギ |
| クリエーター情報なし | |
| 岩崎園芸 |



 ユズリハ
ユズリハ






今年も高山植物コーナーの姫石楠花が咲きました。写真は5月13日に撮影しました。昨年は5月14日に撮影していますのでどう時期です。
名前の由来は、花はまったく異なりますが、葉の様子がシャクナゲの葉と似ているところから。ヒメ「姫」はシャクナゲより小ぶりなところからきています。

花名:ヒメシャクナゲ [姫石楠花]
科名:ツツジ科
属名:ヒメシャクナゲ属
花の色:淡い紅色
分布:北海道から本州の中部地方にかけて分布(海外では、北半球の北部に広く分布)
生育地:高層湿原や寒地の湿原 庭木
植物のタイプ:常緑小低木
開花時期::6~7月
大きさ: :10~25㎝
花言葉:危険・警戒・尊厳






また、下から覗いちゃいました。
花の特徴枝先の花芽の間から2~10個の細長い花柄をもつ壺型の花を散状に咲かせます。花の大きさは5mm程。葉の特徴広線形で、長さは1.5~3.5 ㎝、幅は3~7 ㎜です。
これも、ネズミに齧られたので半分しか咲いていません。
したっけ。
 |
姫シャクナゲ ブルーアイス |
| クリエーター情報なし | |
| 岩崎園芸 |

きゅい~ん’ズ登場!
NOBE,Jiao Long,God-i
DUNIVERSE
今年は黒船躑躅が咲きました。写真は5月13日に撮影しました。昨年花が終わって値下がりしてから買いましたので、初開花です。
安土桃山時代から日本に来航する外国船は黒船と呼ばれていました。その黒船で持ち込まれた躑躅というのが名の由来です。別名をカラツツジ(唐躑躅)ともいいます。

花名:クロフネツツジ [黒船躑躅]
科名:ツツジ科
属名:ツツジ属
花の色:淡い紅色
分布:原産地は朝鮮半島、中国北部、東シベリアなど 日本へは1668(寛文8)年に朝鮮から渡来 現在では日本の各地に分布
生育地:山地の林の中 庭木
植物のタイプ:落葉低木
開花時期:4~5月
大きさ: 2~5m
花言葉:愛の喜び





葉の展開と同時に花を咲かせます。花径は6㎝くらいと大きく、花冠は漏斗形で先が5つに裂けます。8~12mになることもあり大輪の花が美しく、「ツツジの女王」と呼ばれることもあります。花の色は淡い紅色で、上部の裂片の内側には赤い斑が入ります。雄蕊は10本あります。
葉の特徴葉は倒卵形で、枝先に5枚ほど集まって輪生状に互い違いに生えます(互生)。若枝には腺毛が密生します。
このツツジの淡いピンク色は、かなり気にいっています。
したっけ。
 |
黒船来航トートバッグ 国産デニム地トートバッグ |
| クリエーター情報なし | |
| メーカー情報なし |
 |
きゅい~ん’ズ登場! |
| NOBE,Jiao Long,God-i | |
| DUNIVERSE |
今年も日高三葉躑躅が咲きました。写真は5月10日に撮影しました。昨年は5月14日に撮影しました。
名前は、枝先に3枚葉を出し日高地方・えりも町にしか自生しないことに由来します。

花名:ヒダカミツバツツジ [日高三葉躑躅]
科名:ツツジ科
属名:ツツジ属
花の色:赤
分布:北海道固有種 日高地方のえりも町にのみ分布
生育地:山地の岩の多い林の中
植物のタイプ:落葉低木
開花時期:5~6月
大きさ: 2~3m
花言葉:節制





花の特徴葉の展開に先立って花を咲かせる。 花の色は淡い朱赤色です。花径は25~30㎜くらいの漏斗状で、先は5つに裂けています。 1つの花芽からは1~3輪の花が開きます。 雄蕊は10本である。葉の特徴葉は菱形状の卵形で、枝先に3枚が輪生します。 葉の柄や縁、表面には短い腺毛が疎らに生える。 葉の裏面には毛が疎らに生えます。
環境省のレッドリスト(2007)では、「IA類ほどではありませんが、近い将来における絶滅の危険性が高い種」である絶滅危惧IB類(EN)に登録されています。
分類上は、三葉躑躅(ミツバツツジ)の変種とされています。本州から海流に乗って種子が運ばれ根づいたものと推測されている。
この珍しい躑躅は、植えたものではなく、ずいぶん前に何処あらかやってきた流れ者です。
したっけ。
 |
ユタカメイク GDX‐M ガーデンバリア (ミニ) |
| クリエーター情報なし | |
| ユタカメイク |
 |
きゅい~ん’ズ登場! |
| NOBE,Jiao Long,God-i | |
| DUNIVERSE |



















