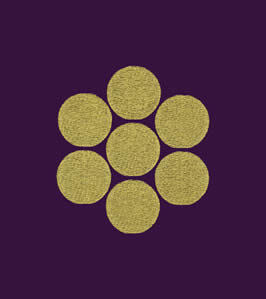△欲望(1966年 イギリス、イタリア 111分)
原題/Blowup
監督/ミケランジェロ・アントニオーニ 音楽/ハービー・ハンコック
出演/バネッサ・レッドグレーブ サラ・マイルズ ジェーン・バーキン デヴィッド・へミングス
△そして自分もいなくなった
不条理、あるいは超現実を映像化するのは、当時の流行だったのかな?
ぼくが大学のときもそうだった。難解な映画を観るという行為そのものが大学生の映画の見方みたいな風潮があって、ぼくも片足を突っ込んでいた。どれだけ小難しく、シュールっぽく撮られているかで、その映画の面白さを、薄暗い喫茶店や居酒屋で語ったりしたものだ。
まあ、それが青春ってやつのひとつの象徴なのかもしれないけど、そんなとき、たいがい挙げられるのが、この『欲望』だった。知り合いの中には、この映画に影響されたものか、羽根のないバドミントンをする場面を入れた自主製作作品を撮ったりした。それほど、当時の映画好きな大学生にとって『欲望』は重要な映画だった。
じゃあ、内容をしっかりと理解できたのかといえば、それは怪しい。
この世に存在するものは、おそらく実体と非実体に分けられるんだけど、通常、実体の世界にいる人間、たとえば写真家のように、実体を被写体として捉えている人間は、見えているものしか信じず、いいかえれば、実体を実体として捉えることはできるけど、非実体を実体として捉えることはほぼ不可能で、むろん、非実体の世界があったとしても、それを捉えることなど出来ない筈が、ある瞬間、たとえば公園とかにカメラを抱えて出かけた際、もしも非実体を自分の目で観てしまったらどうなるだろうか?
非実体の世界に片足を突っ込んだことになり、撮った写真を現像してみれば、自分の目が捉えていたのは、非実体の男女の睦み合うところだったにもかかわらず、実際にはそこに惨殺された死体が転がっていたという残留思念を撮影しており、しかし、これを撮影できること自体、非実体の世界に片足いれた証拠になる。
やがて非実体の世界からお呼びが掛かり、つまり、非実体の女が、実体の世界にあってはならない写真を取りにやってきて、彼女の写真を、よりにもよって裸体を撮ることにより、いっそう非実体の核に触れるという結果を導き、それがために非実体をより多く感じるようになり、たとえば、白塗り非実体人どもがテニスに興じるところを捉えられるようになり、ありもしないボールを(あるいは、もしも非テニスが、過去、現実にあったテニスだったとするなら、かつてあったであろうボールを)自分が追いかけることで、その非実体の世界に完全に両足を突っ込んでしまったがために、自分もまた実体の存在する世界にはいられなくなり、非実体の世界へと移動させられてしまうにちがいない。
で、その実体と非実体ってのがなにかっていえば、この世とあの世。つまり実体と非実体ってのは、生身と幽霊ってことになるじゃないのかな~って話だと、当時のぼくは考えていたし、いまもそんな感じじゃないかな~とおもってる。
まちがってるかしら?
だとしたら、いまだに修行が足りませんな。