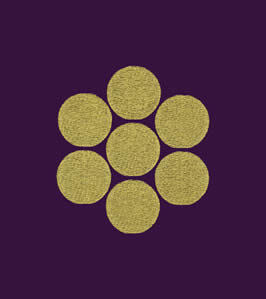◇眼の壁(1958年 日本 95分)
監督/大庭秀雄 音楽/池田正義
出演/佐田啓二 鳳八千代 朝丘雪路 織田政雄 宇佐美淳也 渡辺文雄 左卜全
◇清張好みの題名
未だに題名の意味がよく理解できていないのかもしれないんだけど『眼の壁』ってのは、なにを意味してるんだろう?
中学高校と、ぼくの読む小説はたいがい探偵小説で、それも戦前から戦後まもない頃に世に出た作品で、簡単にいってしまえば、江戸川乱歩、横溝正史、小栗虫太郎、浜尾四郎、夢野久作とかで、松本清張は古代史物は手に取ったけど、社会派推理小説とかいわれてて、どうも学生のぼくには関係のない世界みたいで、触手が動かなかった。
やっぱりサラリーマンが読み手だったんだろね。だから、この原作を読んだのは、社会に出て随分経ってからだ。でも、ほとんど忘れちゃった。これはほかのどんな小説でもそうで、読んだ数も少ないくせに、恥ずかしながらまるで憶えてない。そんな人間が題名の意味とかいってるんだから、駄目だよね。
ちなみに、清張の小説は『眼の壁』みたいに抽象的なものが多い。当時の流行だったのかもしれないんだけど、なんだか文学的っていうんだろうか、よく考えないとわからない。そういう感じの題名でいちばんわかりやすいのは『砂の器』だけど、これについては、いつか触れる機会もあるだろう。
あ、でも、ひとつだけ。ぼくは『砂の器』がかなり好きで、それを観て以来、カメラマンの川又昂のことが気になってきた。で、この作品だ。撮影チーフ川又昂!おお、とおもった。撮影は当時の松竹をしょって立ってるような厚田雄春で、小津の作品では無くてはならない存在だけど、ぼくにとっては「おお、川又昂!」なんだよね。
「この時代から清張物で地方ロケをしてたのね~」
とかおもうだけで、なんとなく嬉しかったりするんだ。
瑞波ロケの雰囲気も良で、病院や郵便局の雰囲気もよく、もはや、この時代の映画は、映像資料としての価値が出てきたんじゃないかな。それと松竹といえば、やっぱり佐田啓二で、これは大庭秀雄との「君の名は・コンビ」で考えられていたのかしら?ちょい根暗だけど、それが上司の仇を討つ役柄にあってたのかな?
あと、役者でいえば、宇佐美淳也と左卜全は好演。音楽も、不気味で好い。脚本も、強引なところはあるけど、ぎっしり詰め込んだ印象は充分ある。死体処理のトリックについてなんだけど、濃硫酸と重クローム酸ソーダを混合した溶液でほんとに死体が溶けるのかどうか、ぼくにはさっぱりわからない。
ただ、松本清張は、実際にあった事件にヒントを得たようで、足立区にあるの日本皮革(現:ニッピ)の工場で起こったらしい。被害者の死体を、今も触れた混合溶液であらかた溶かし、さらに塩酸と硫酸の混合液で全部溶かしてしまう計画が練られたとか。なんともおぞましい話で、こうして書いていても気味が悪い。でも、この溶液が、映画では重要な道具になってんだよね。