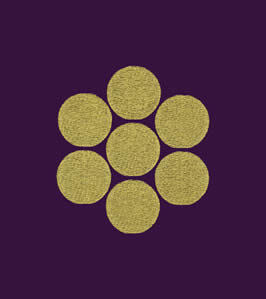◇喜劇一発大必勝(1969年 日本 92分)
staff 原作/藤原審爾『三文大将』
監督/山田洋次 脚本/森崎東、山田洋次
撮影/高羽哲夫 美術/梅田千代夫 音楽/佐藤勝
cast ハナ肇 倍賞千恵子 谷啓 佐藤蛾次郎 犬塚弘 武智豊子 左卜全 田武謙三 佐山俊二
◇半世紀前の記憶
ぼくには忘れられない記憶がある。
もう半世紀近くも前の記憶なんだけど、
そのときの映像も台詞もしっかり脳裏に刻み込まれてる。
その日、ぼくは実家の近くにある消防署の前に立っていた。
ただ、現在、消防署は商工会議所に変わってるんだけど、それについてはいい。
そこは故郷ではいちばんの繁華街で、そのあたりでは最初に街灯がつけられ、
夜になっても明るいとかいって、たくさんの人が暗くなっても歩いてた。
いまでもそのときにつけられた2軒毎に1柱の街灯が夜でもまたたき、
過疎のせいで誰ひとり歩かなくなってしまった通りを照らしてる。
で、その記憶によれば、ぼくの前に乗合バスが停まってて、
扉が開くと同時に、女の車掌さんが、こういうんだ。
「墓場行きですよ」
車掌さんは、それを何度も繰り返した。
「墓場行きです、墓場行きです、墓場行きです…」
その後、
バスは、ぼくよりも小さな男の子と女の子、それと初老の男の人を乗せて発車した。
けど、眼の前の四つ角を右に曲がって、
魚福という魚屋さんと三七福という餃子屋さんの前で停まって向きを変え、
またぼくのいたところまで戻ってきて、同じことを繰り返した。
ぼくはそれをずっと見てた。
「墓場行きです」
と何度も繰り返した女の車掌さんは倍賞千恵子で、
ぼくのすぐうしろには消防署の窓があって、
窓辺には、キャメラを横にした山田洋次監督がいた、はずだ。
そう、その日、ぼくは撮影現場の真ん中にいた。
なんでそんなところに自分がいたのかわからないんだけど、いた。
この記憶は1968年の晩秋あたりの記憶で、以来、半世紀近くぼくの頭の中に残ってる。
記憶はもうひとつある。
消防署の前には、
米兵本店という食料品店、同盟書林運動具店、菊乃屋という中華そば屋さんが並んでたんだけど、
クレージーキャッツの人達が昼食をその菊乃屋さんで取り、
食べ終わったあと外に出て「いらっしゃい、いらっしゃい」と客の呼び込みをしていたことだ。
たぶん、ロケ現場でのサービスだったんだろうけど、ハナ肇、谷啓、犬塚弘の3人がいた。
けど、たしかな記憶はあっても、その後、この撮影について、町の人は誰も話さなかった。
だから、ぼくの中では「あれは夢だったんだろうか」ともおもうようになった。
ところが、あるとき、倍賞千恵子がバスの車掌をやった映画があるということを知った。
それがこの作品で、このたび、ようやく観た。
ただ、どういうわけか、場面場面、断片的に記憶がある。
もしかしたら封切りのときに観たのかもしれないんだけど、それはともかく、
映画のタイトルが映された次の瞬間、ぼくはおもわず「おおっ」と声をあげた。
冒頭ワンカットめから始まるタイトルバックは、ぼくの故郷の駅前だった。
乗合バスのターミナルの奥から車体なめのカットなんだけど、
奥に見えるのは、当時、町でいちばん大きかったスーパー西川屋で、
倍賞さんが車掌さんになって乗り込み、バスは発車する。
「お乗りの方はありませんか、墓場行きですよ」
これが、出だしだ。
ちなみに、
市営公園墓地行き乗合バスあさしお号の後部看板には、
『センスとコストで奉仕するモリ洋装店…』とあり、
さらに当時の住所と電話番号までしっかり写ってた。
駅前から坂を下りていくバスは、
豊坂屋、アサヒヤ、カネマタ、ギフヤといった懐かしい宣伝看板を横目にして通り過ぎ、
新道を南へ曲がり、小学校の西門へ入っていく角口の歩道橋をくぐり抜け、
ぐるりと町を回ってずいぶん北にある消防署前で停まり、
「墓場行きです」
という例の台詞の場面になった。
バスのボディには寺田産業、呼帆荘の宣伝看板。
寺田産業はぼくの同級生の実家で、呼帆荘はぼくの母親の同級生の営んでる旅館だ。
倍賞さんが「墓場行きです」といって現れたバスの向こうには、
米兵本店と同盟書林運動具店があって、同盟書林の店頭にはバットを入れた籠が置かれ、
ガラス戸に手書きで『はかり』『贈り物にヘルスメーター』とある。
その戸の横に店内から眼鏡をかけたお爺さんが覗いてる。
当時のご主人だ。
うわ、なんだこの映画、とぼくはおもった。
それからあとは、ぼくの生まれた町と隣町でのロケが延々と続いた。
隣町は陶器の生産で知られた町で、窯元がたくさん並んでて、今でも風景は変わらない。
映画の中では「煤煙都市」っていう設定になってるんだけど、
もう現在、登り窯の煙突から煙がもくもくと立ち上ることはほとんどなくなってる。
でもその時代の煙突はまだいくつか残ってて、
山の上市営墓地から港の方を眺めると、その煙突越しに海が見える。
その陶器の里とおぼしき長屋の店舗兼住宅に倍賞千恵子は棲んでるんだけど、
家の台所の片隅には、
ぼくの実家近くの酢屋で醸造される酢の一升瓶が6本入る木箱が置かれてたりしてる。
ほんと、なにからなにまで故郷のオンパレードで、
倍賞さんのガイドで観光旅行に出るんだけど、
それすらも、県庁近くにあるテレビ塔前とライン下りだ。
陶器の里に帰ってからはひたすらそのあたりのロケが続く。
いやあ、堪能した。
ただ、物語に堪能したのかといえば、実は微妙だ。
というのも、この作品、ひと言でいってしまえば、喜劇とは程遠い。
えげつない。
陶器の里によくにた貧乏長屋は、三つの厠とひとつの風呂を共同で使っている。
そこにたった一軒だけあるのが、倍賞さんの実家となる食堂兼雑貨屋で、
この長屋にウマさんこといかりや長介が棲んでいたんだけど、
こいつが手におえない乱暴者で、ついに長屋の住人4人が殺してしまい、
その中に倍賞さんのおやじ田武謙三もいたりするんだけど、
こいつらがウマさんの死体をカラーテレビの段ボールにつめてバスに乗り込み、
『東京のバスガール』なんぞを歌い、勝手に火葬しちゃうところから話が始まる。
この住人どもはけしからんどころか相当におぞましい連中で、
ウマさんはフグにあたって死んだとかいって香典を集めるんだけど、
そもそも貧乏人には手の届かないフグなんぞ食えるはずもなく、香典もみんな呑んじゃう。
こんな連中だから、きちんとした火葬を出してやろうなんて殊勝なことは考えない。
あたりには陶器を焼く窯がたくさんあるわけで、かれらがなにをしたのかは充分に想像がつく。
でもって、そこへボルネオ帰りのハナ肇こと寅吉が登場し、
ウマの仇をとってやるとばかり、オコツをとりだし、スリコギもってきやがれと叫び、
スリバチでごりごりと遺骨を粉微塵にし、水だ、醤油だ、と始まり、
もう、信じられないほどえげつない仇討が展開されるんだけど、
ともかく、その後、紆余曲折あって、倍賞さんはいつのまに車掌を辞めたのか、
実家の食堂でかき氷とか出すようになったりしてるんだけど、
その倍賞さんに惚れちゃうのが、ボルネオ帰りのハナ肇と保健所々員の谷啓だ。
ハナ肇の場合は、こういうどうしようもない爪弾き者にはありがちなひと目惚れで、
乱闘の際、賠償さんが、
長屋の道端に落ちてる使い古して棄てられた便器をむんずとつかみ、
それでもって後頭部に強烈な一撃をこうむったことで、
もう、どうしようもないくらいに恋の虜になっちゃう。
この恋話の凄いところは、
そのハナ肇が、倍賞さんの服役中の旦那への手切れ金を稼ぐために、
港湾の再開発の飯場にもぐりこみ、自殺して労災の金をあてこもうとする無鉄砲さで、
さらに凄いのは、これに巻き込まれた谷啓がいともあっさり死んじゃうことだ。
くわえて、葬式のときに棺桶の中から引っ張り出して踊りを躍らせるんだから、ものすごい。
このときのハナ肇の怪演ぶりは、たぶん、誰も真似できないだろう
けど、この無茶苦茶さがよかったのか谷啓は蘇生し、ついに倍賞さんに求婚するんだけど、
それもまた肥溜めに落ちて失敗するという臭いオチまでついてくる始末だ。
とどのつまり、ハナ肇と谷啓は失踪し、倍賞さんは貧乏長屋の店を継ぐという、
あまり幸せな未来が待ってるとはおもえない結末にはなるんだけども、
疾走したふたりが旅の空でまた出くわして喧嘩するというエピローグまでついてる。
ただ、
この傍若無人な作品に主題があるとしたら、いったいなんだったんだろうと考えれば、
浮かんでくるものがないわけでもない。
ウマさんの骨粉汁を飲ませられた親父たちが倍賞さんに不満をもらしたとき、
倍賞さんはひとことこう呟いてみせる。
「足りないのは、あんたたちの勇気なんじゃないの」
そう、この映画の主題は、勇気なんだよね。
倍賞さんは、ボルネオ帰りの御大ことハナ肇に対して、肩をはだけながら啖呵を切る。
「あたしを裸にしたいんだったらしてごらんなさいよ。
でもね、体はあんたの自由になるかもしれないけど、心は自由にできないんだから」
倍賞さんは、片意地はった開き直りながらも、生きる勇気を見せつける。
谷啓は、気の弱さを全面に漂わせながらも無茶で小さな勇気を見せる。
ハナ肇は、単なる蛮勇だけど、自分の体を張っても倍賞さんを助けてやろうという健気さを見せる。
でも、ほかのがらくた連中は、こそこその貧乏長屋の端っこで膝を抱えるだけで勇気を見せない。
これって、結局、日本の縮図なんだよね。
山田洋次のいいたかったことは、たぶん、そのあたりにあるんだろう。
ついでながら、倍賞さんの継いだ食堂は「タイガー軒」っていうんだけど、
このあたりになると、見え隠れしてくる映画がひとつある。
そう、フーテンの寅だ。
ボルネオ帰りのハナ肇は厄病神みたいな野郎で、
こいつが長屋へ戻ってこなければみんな幸せに生きていけるはずなのにっていう展開、
さくら、じゃなくて、鶴代こと倍賞さんはそれでも健気に実家の店を守り続け、
惚れた相手に振られたことで行方をくらますハナ肇や谷啓を、
貧乏長屋の連中が、
「いまごろ、どこにいるのかね~、どうしてるんだろうね~」
とかいって心配したりしてるなんてのは、
これはもはや『男はつらいよ』の原型といってもいいんじゃないだろか?
ハナ肇が期待されもしないのにひょっこり現れるところもそうだし、
エピローグなんかも、まさしく『男はつらいよ』のお約束ごとだ。
ただ、この凄まじくも空恐ろしい爆裂映画は、
山田洋次よりも森崎東の諧謔が色濃く滲んでるような気がしないでもないけど、
まあ、寅だのなんだのだという推論はおいといて、
半世紀近く前のぼくの記憶は、正しかった。
それどころか、
キャメラは消防署(映画では保健所ね)の中から、バスの中に移動して、
倍賞さん舐めの発車のカットになるんだけど、
そのとき、窓の向こうに見えてる消防署の壁際に、
ぼくがいた。
当時、ぼくは10歳になるまで、半ズボンをはいていた。
映画の中のぼくも、
灰色のボタンシャツの上に、
ボタン部分だけ青くなってる白地のカーディガンを羽織り、
紺色の半ズボンをはいている。
ロケの記憶から半世紀、ぼくは当時のぼくに再会したのだ。
感動した。
0・5秒の再会だったけど、こんなことってあるんだね。